慶應義塾大学大学院教授 岸博幸氏×GRANDIT(株)社長山口 対談
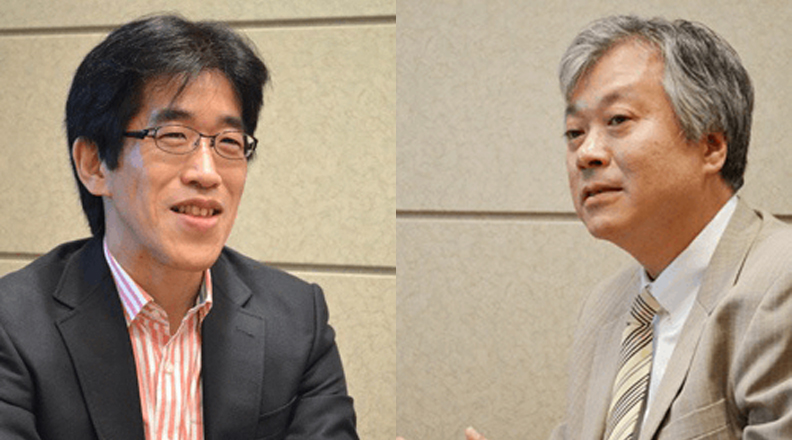
“おもてなし”の
日本型ビジネスモデルで勝つ!
近年、日本企業経営者が考える経営課題上位に「グローバル化」が上がるようになった。これまでも継続的に取り組んできたテーマだが、このところあらためて注目を集めている格好だ。一方、新興国企業の台頭や米国のものづくり回帰の攻勢にさらされ、日本企業は世界での戦い方に自信を失っているという観測も目立つ。日本企業の真のグローバル戦略は、一体どうあるべきなのか。
当社代表取締役社長 山口俊昌が、慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科
教授の岸博幸氏と行った対談では、日本企業が掲げるべきグローバル戦略、そしてその中でのIT活用のあり方について幅広く議論が展開された。
変わる“グローバル化”の意味と意義

──日本企業のグローバル戦略がクローズアップされています。昔から海外進出の必要性は説かれてきましたが、なぜ今ここにきて注目を集めているのでしょうか。
【岸氏】過去と今ではグローバル化の意味が違ってきているからです。今まで日本企業のグローバル化といえば、労働賃金の安い国へ行って生産コストを下げることが目的でした。日本にいたら、人件費、物流コスト、法人税などいろいろ高コストになりますから。だから海外へ出ていったわけです。
しかし、昨年あたりからこうした傾向が変わり始めました。たとえば、米国などで起きている製造業の国内回帰などがその1つです。こうした変化には大きく3つのポイントがあります。1つ目は人件費が下げられるからといって出て行った中国などで労働賃金が上昇していること、米国内の雇用確保の問題もあります。そして、2つ目は社会的にコンプライアンス強化が求められていること。3つ目はITやFA(ファクトリーオートメーション)の徹底活用によって製造工程の自動化が進み、国内で生産しても人件費の抑制が効くようになってきたことです。
ですので、単に生産コストを下げることを考えるよりも、最終消費地に近いところで作って需要の変化や多様化に柔軟に対応するほうが、いい結果を生むということを企業が認識し始めたのだと思います。
もちろんそれでも新興国へのシフトは変わりません。これは新興国の最終消費地としての魅力が、以前よりも増しているからで、そのために海外拠点を設けるようになっているのです。
グローバルで勝ち抜く日本企業ならではの価値とは成功している企業は何が違うのか

このように、どうやって自社の製品・サービスをどの市場へ広めていくかという経営戦略、マーケティング戦略のもと、全世界的に最適なオフィスと工場の配分を考えるようになっています。これが今のグローバル化で、ただ日本の外へ出ていけば海外進出といっていた過去の考え方とは根本的に違ってきています。
【山口】私もそれは非常に感じますね。製造業系のお客さまは積極的にグローバル化を推進しています。現在、当社の国産ERP製品であるGRANDITの多言語化を進めていますが、当初は生産管理系モジュールを中心にその機能を付加すればいいと思っていました。
しかし、現在は企業規模の大小に関わらず、販売拠点、調達拠点なども海外に置かれるようになっており、生産管理に限らず、販売管理や調達管理などのモジュールも同様に多言語化が求められており、開発プロジェクトに組み込みました。
そろそろ米国企業の後追いはやめよう
──お話を伺っているとグローバル化の裾野は広がっているようなのですが、現在のところ、日本企業の対応は十分といえるレベルに至っているのでしょうか。
【岸氏】いろいろな面で不十分だと思います。日本企業は結局のところ、今でも米国企業の後追いをしているに過ぎません。米国がどう出るかを見ていて、それに追いつこうとしているだけです。
IT導入もそうですよね。米国から何か新しいキーワードが出てきたら、それを一生懸命消化して展開しようとする。米国的な価値観に取り込まれてしまっているんです。つまり、日本企業は前例が存在するものだけを取り入れるということ。世界経済が右肩上がりで成長しているときはそれでも伸びる余地はあったんですが、これだけ成熟してくると、後追いでは世界で勝てないと思います。
【山口】本当にそうですね。これは当社も含めた日本のIT業界の反省も込めた話になりますが、米国で普及したITの概念を取り入れ、日本向けに改良を加えて提供します。ある程度経って、これで米国と同レベルになったと思ったら、またそれをひっくり返すような新しい上位概念が入ってきて、またあわててキャッチアップする。その繰り返しに陥りがちでした。
【岸氏】日本はおもしろいですよね。今日は資本主義社会といってもいろいろバリエーションが広がっていて、シンガポールのように国自体が企業と同じような規模のところでは企業国家型資本主義、北欧では福祉が充実した社会民主主義な資本主義、中国、インド、ロシアなどは国家資本主義を志向しています。
それなのに日本は相変わらず米国型の純粋資本主義に固執していて、それでいて、このままでは格差が広がると妙な危機感にとらわれています。どうも新しい価値観を創造する力が弱いんですよね。
日本型ビジネスモデルとは“おもてなし”的な付加価値の提供
──日本ならではの価値観、日本らしさというのはどこにあるとお考えですか。

【岸氏】非常に難しい問題です。ほかの国にはない、日本型のビジネスモデルはぜひとも必要ですが、私もまだ明快な回答を持っているわけではありません。
私はある音楽会社で役員を務めているのですが、音楽の世界もデジタル化の波が押し寄せてきています。CDでの販売からダウンロード配信がグローバルスタンダードになりつつあるのですが、日本でもこれを取り入れることについて、個人的には何か間違っているという気もしています。
安く、大量に音楽を提供するというビジネスモデルは、ハードウェアからプラットフォーム、コンテンツまで垂直方法にすべてを持っているアップルなど、米国企業を中心に数社にしか実現できません。
こうした中、日本型ビジネスモデルで対抗しようとするなら、“おもてなし”的な付加価値の提供ではないかと思います。
ユーザーはただ音楽だけに興味があるのではなく、それを歌ったり演奏したりしているアーティストの情報や、クラシックなどであれば文化的背景までいろいろ知りたいものです。特に日本人はそうした知的欲求が高いので、そうした情報サービスをも合わせて適切な価格で提供するというビジネスはあり得るし、実際、そういう取り組みを始めています。
まだ手探りの面もありますが、それぞれの国の国民性や文化的なよさを製品・サービスに組み込んでいくのは、あらゆる産業、あらゆるビジネスで必要だと思います。
【山口】音楽業界と同様の変化がITの世界でも起こっています。クラウドなどはプラットフォームが世界規模で何社かに絞られていくと言われています。企業文化を支えるアプリケーションも、多様性を打ち消す方向で集約が進んでいます。
ここで日本型ビジネスモデルとして差別化するなら、やはり岸さんのおっしゃった“おもてなし”がキーワードになると思います。システムを導入したあとのたゆみない改善やユーザーの立場に立った運用サポートといった点は、欧米にはない日本のIT企業の強みです。
システムの根本コンセプトを作るのは苦手かもしれませんが、親身になってユーザーをサポートするのは得意です。このような視点をもっと上流工程に持ち込んで、欧米企業にない特長を出すのは重要ではないでしょうか。
【岸氏】欧米と日本の大きな違いは、トップダウンとボトムアップです。欧米はとにかくリーダーが強くて、一方、現場はというとそうでもありません。だからマニュアルがしっかりしていて、そのとおり動けば仕事が回るようになっています。
逆に日本は、リーダーはそれほど大したことありませんが、現場がすごく強いんですね。だから、東日本大震災の際も、混乱は起こらずに極めて迅速に工場などが復旧しました。
ITに関しても、トップが強い企業と現場が強い企業とではそのあるべき姿は違うはずで、戦略を考える際にはその点をしっかり考える必要があると思います。
【山口】ERPパッケージアプリケーションの世界はまさにそうです。一時、外資系企業の製品が志向され、ベストプラクティスの名のもとに自社の業務をパッケージに合わせるのが潮流となりましたが、トップダウンの企業文化の中で作られたものでは現場が回らなかったんですね。
そのため、予算をかけ、その周辺に原形をとどめないほどにアドオンシステムをいっぱい作ってようやく使うような状況でした。これではいけないということで、ボトムアップで業務を回す現場が強い日本の企業文化を尊重した当社の「GRANDIT」がご好評いただいたのだと思います。
グローバルで日本らしく戦うには“目利き”が重要

「目の利く外部企業パートナーが一緒にGRANDITを作り上げています。」
──グローバル化を考えるとき、どこまで日本らしさを残し、どこまで世界を意識するかというのは重要なポイントだと思いますが、軸足の置き方をどう考えればいいでしょうか。
【岸氏】これは業種によって事情が異なるため一般解はないと思いますが、伝統文化にたとえるとわかりやすいかもしれません。今日ある伝統文化の多くは、時代の変化に柔軟に適応してきたから生き残ってきたといえます。それと同様に、世界に向けて100%日本らしさをアピールするというのは無理があると思います。
何が世界に通じる日本らしさか、何がそうでないか、仕分けをしっかりすることですね。ここで大事なのは、その仕分けに第三者の目を入れることです。企業内部の人間はすべてに慣れてしまって、客観的なよしあしが判断できません。“目利き”ができるパートナーの存在が重要です。
【山口】従来、日本のIT業界は、そうしたプロセスをコンサルティングファームに任せてきてしまった側面がありますが、もうそろそろやり方を変えるときが来ているかもしれませんね。
GRANDITでは、コンソーシアムビジネスモデルという方式を採っていて、コンソーシアム加入企業や国内70社を超えるパートナー企業でGRANDITの導入、カスタマイズ、保守・サポートを展開しており、毎月開催している部会にてお客さまのニーズを当社が集約、機能強化やサービス提供に反映させています。
つまり、目の利く外部企業パートナーが一緒にGRANDITを作り上げています。
コンソーシアムで議論する中で、日本らしさをどう発揮するかも少しずつ整理できてきました。簡単にいえば、会計や法制度対応など、企業の差別化につながらない業務に関してはパッケージをそのまま活用、さまざまな管理系業務は他社の成功例を参考にしながら少し手を入れる、販売系業務、営業系業務など企業が独自のノウハウを持っている部分は、可変的な機能を持ったパッケージでその強みをできるだけ生かすという方向ですが、GRANDIT 2.0は、この実現をめざしました。
また、今回のバージョンアップでは、グループ企業やパートナー企業との連携や、海外拠点を含めた形での一元管理、タブレットPCなどのデバイスの多様化対応、ビッグデータの分析・活用に備えたテンプレート機能にも力を入れています。今後も適用の枠を着実に広げていく構想で、運用サービスなどを含めワンストップサービスを提供していきたいと考えています。
コアコンピタンスを熟知している企業は成功している
──GRANDIT活用でグローバルに活躍されている企業にはどんな特徴がありますか。
【山口】経営層が本気でコミットされている企業は導入に成功されています。そうした企業は、現場も経営に命じられたからというのではなく、真剣に業務の改善を取り組んでいるケースが多く、経営と現場の意識がよく揃っているといえます。
日本らしさという点では、日本企業は従業員ケアに配慮する面があって、それが手厚い企業ほど現地で評価されてうまくグローバル化を果たされているように思います。“自分たちの土俵で勝負する”ことの意味をよくご存じのようです。
【岸氏】そうですね。そういう意味では、企業がしっかり自分を理解しているかどうかというのが大きな分かれ目になるのでしょうね。自分たちのコアコンピタンスをしっかり把握して、どこに注力すれば自社が勝ち残っていけるかをよくわかっている企業なら、御社もお手伝いしやすいし、結果も出しやすいのではありませんか。
【山口】おっしゃるとおりです。“本気のお客さまには本気で取り組んで、成果を分かち合う”というのが、当社のポリシーです。厳しい時代ですが、こういう時代だからこそ日本企業が本当の底力を発揮できるときだと考えており、日本らしい強みを生かして勝負するというお客さまを全面バックアップしていきたいと考えています。
欧米のビジネススタイルに対する日本企業の進むべき進路について、GRANDITの特色を加味しながら新鮮な議論が展開された。
