商社の鉄人第3回 鉄人が語る「商社における各業種の営業システムのポイント」とは?
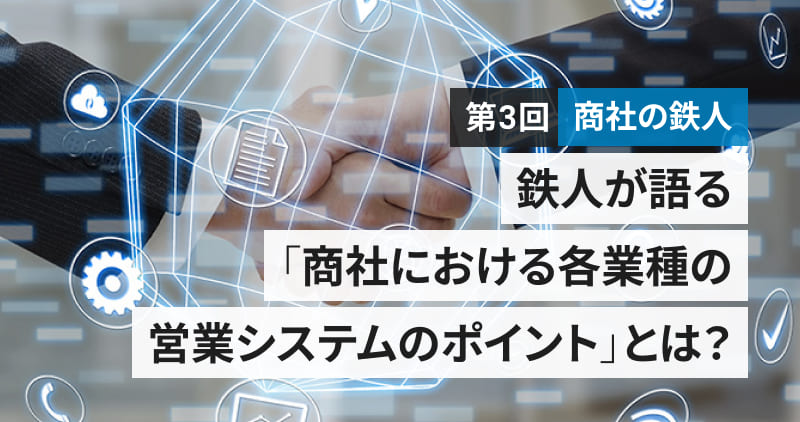
目次
財務会計システムとの連携情報
営業部門の各システムに入る前に、それら最前線の営業システムとコーポレート部門のERPで共通して必要となる情報について整理しておきましょう。
商社と一言でいっても、いろいろな商品を扱っているわけですが、会社として集めるべき情報があり、それはERPと営業システムの双方で同一の粒度にしなければなりません。
営業システムをパッケージあるいはスクラッチで構築するにしても、財務会計システムと同一のフォーマットにして取り込むことが求められます。その主なものを紹介していきます。
仕訳情報
仕訳情報として、取引日、計上日、勘定科目、相手先、金額、消込予定日などがあります。
まず、取引日と計上日。財務会計システムでは取引日と計上日を別にしているのが一般的です。例えば、2月に出荷した分の返品が3月に返品されてきたという時は、取引日は当初の日付で、計上日は現在の日付というように、日付が変わる可能性があるので両方持つようにしています。
そして、勘定科目、取引の相手先、金額、この辺は必須ですね。
消込というのは、売掛残高の明細管理を財務会計システム側で行うことから、回収予定を取り込んでおきます。例えば、10月31日に計上した売上の回収予定日は11月30日なのか12月30日なのかという情報を、消込予定日として持つことになります。未回収の売掛明細を把握することで、資金繰りに役立ちます。
管理情報として取引形態(国内、輸出、輸入、外国間)
一般的な財務会計システムの情報以外に、商社では管理情報として取引形態が必要です。取引が国内、輸出、輸入、外国間なのかという分類です。
国内と輸入には消費税がかかります。輸出は免税、外国間の場合は消費税の考え方そのものがありません。
また、消費税の申告には90%ルールがあり、全体の取引のうち90%が課税取引であれば、簡易申告が認められています。
相手先の国
これは前回のコラムでもお話ししました。取引先の相手先が重要となっており、ERP領域でも管理する必要があります。
毎月経済産業省への届出が義務づけられています。
セグメント種別(有価証券報告書・事業報告書に記載するセグメントの分類)
投資家の判断を支援する情報としてセグメント種別を有価証券報告書・事業報告書に記載するケースがあります。
例えば、食料が40%、機械が20%、繊維が10%というように記載されます。有価証券報告書のこのような記載を見て、どういう系統に強い商社か、投資する価値があるかどうかという判断の資料とします。
商品、数量、単価
商品と数量と単価は、一般的には財務会計システムには持ってない情報であり、営業システムから吸い上げる場合は、これら情報を意識する必要があります。
もっとも販売から会計へ一気通貫しているERPであれば考える必要はありません。個別に構築している場合で、財務会計システム側で商品、数量、単価が必要な場合は、連携する仕組みを用意しておきます。
営業システム[食料・食品]
ここから個別の営業システムに入ります。
食料・食品でポイントとなるのが、トレーサビリティ、数量と重量の管理、膨大な取引明細の3点です。この各論に入る前に、前提として食料・食品は取り扱いの品目によって、営業システムのあり方が大きく異なるということがあります。
食料・食品といいながら、スーパーの生鮮食品を扱ってるケースもあれば、缶詰や小麦粉など分類は多岐にわたります。また、生き物を扱っていると、途中で死んでしまい、数が合わなくなる場合もあります。
個別に取引が発生することはもちろん、EDIで膨大な取引データが一気に流れる業態もあります。一物一価ではなく、お客様や経路ごとに単価が異なる場合もあります。
共通化することがなかなか難しいことから、営業システムはERPでカバーするよりも、パッケージをあてがうことが多いのが現状です。
トレーサビリティ(原産地、製造ロット、流通ロットの管理)
食料・食品で必ず必要となるものに、トレーサビリティがあります。この商品はどこが原産地で、どの工場で作られて、どういう経路で流通してきているかという情報です。
食中毒事件が起きた時に、該当する流通ロットはどれとか、製造ロットはどれというふうに、追いかけることができなければならないからです。
トレーサビリティが、食料・食品の特徴です
数量と重量の管理(重量の目減り)
数量と重量の管理は、販売管理として当然のことですが、食料・食品では、仕入時と販売時に異なってくることがしばしばあり、ここがやっかいなところです。
食料・食品でERPのハードルとなるのが、流通の途中で重量が目減りすることです。例えば豚バラブロックを冷凍で3キロ分買ったとしても、流通の経路の中で氷が溶けて、卸とかスーパーに納める時には2.9キロになってしまいます。こちらは3キロ分を食肉メーカーに払っているにもかかわらず、スーパーは2.9キロ分しか払ってくれない。このあたりがERPの苦手とする部分で、買ったものが途中で数量や重量が変わることを想定していません。
タンクローリーで買って、入れ替えたり小分けしたりすると数量がずれる場合もあります。加工して、重量が変わることもあります。
私も食料・食品の営業システムをERPで構築したのは缶詰や香辛料などで、正直それほど数がありません。食料・食品の営業システムは専用パッケージが多いなあという印象です。
取引明細の件数が膨大(リソースへの投資効果が低い)
食料・食品は、取引明細の件数が膨大になり、システムに負荷がかかります。
商社が食料・食品だけで1千万円の粗利を出そうとすると、ずいぶんの量の取引件数が必要になります。このため、高性能なサーバーを用意しなければならないとか、大容量のストレージが必要ということになり、それなりの投資が求められます。それでいて、対投資効果が低い。ここが、ERP提案がなかなか通りにくい理由となっています。
営業システム[機械・部品]
機械・部品は食料・食品とは異なり、1個が目に見えて数えることができますから、比較的ERPで扱いやすい業種となります。
不良品管理(製造ロット管理、DOA/RMAによる返品、代替品提供)
機械・部品でポイントになるのは、故障や不良品があることです。
「この年月日に出荷した製品は再チェックしてください」とか、「無償点検します」などがあり、故障や不良品の管理が必要になります。
ここでDOA/RMAという言葉がよく出てきます。DOA(Dead On Arrival)は初期不良や着荷不良のこと、RMA(Return Merchandise Authorization)、使い続けているうちに不具合が発生して代替品と交換するものです。
返品に対して代替品を送った場合は、後に修理完了品を再送するケースもあれば、代替品をそのまま使うケースもあります。商品管理が複雑になります。
輸出要件(リスト規制、キャッチオール規制、相手先要件)
輸出に当たって、経済産業省に毎月報告する義務があります。
「リスト規制(品目)」または「キャッチオール規制(用途要件、需要者要件)」に該当する場合は、許可が必要となります。
リスト規制では輸出に許可が必要な品目がリスト化されています。
リスト化されていないものでも、キャッチオール規制で用途要件と需要者要件がチェックされます。用途要件とは最終的に大量破壊兵器や通常兵器の開発などに使用されていないかどうか、需要者要件は大量破壊兵器の開発などを行っていないかどうかです。
完成した機械であれば用途は限られていますが、電子部品になるとミサイルの制御に使われるかもしれないし、パソコンのCPUで使うのかもしれないというように用途がはっきりしません。
相手先要件とはその国がホワイト国かどうかということ。例えばアメリカはホワイト国ですが、韓国がホワイト国から外されて話題となりましたね。
委託加工(部品使用数量、加工賃)
商社では加工作業はしませんが、加工業者に加工を依頼して、完成品をユーザーに売るケースは多々あります。これが、食料の重量目減に近く、100個の部品から1個の完成品ができる設計図があっても、部品不良のために101個使ったり、102個使ったりするケースがよくあります。
その加工業者の加工費用は原価として計上するパターンが多いようです。
加工販売は増加する傾向にあります。これが電子部品になると、目で見える加工だけではなく、チップに組み込みソフトを書き込むということもあります。見た目は同じですが、中にプログラムが入っているか入っていないかで、商品を区別する必要があるのが特徴的です。
組立販売では、完成品と部品を紐付けて管理しておく必要があり、中にはBOM(Bill Of Material:部品表)を使用しているケースもあります。このレベルになると、専門商社に多く、総合商社でも機械を扱ってる部門を子会社化してしまうことが見られます。それだけ特殊な世界といえます。
営業システム[繊維]
次に繊維系、アパレル商社と呼ばれる場合もあり、私たちは「いとへん」と呼んでいます。
材料の数量管理(金額管理)単位が多様
繊維系を扱う商社では、材料の数量と単位が多様で管理が大変になります。
例えば、ボタン。ワイシャツに付けるボタンは、1個それぞれに値段が付けいてるわけではなく、100g単位で仕入れ、その中に80個入っているのか70個しか入ってないのかわからないまま材料の管理をしています。
委託加工(副素材の再利用や販売・買戻)
委託加工が多いのが繊維系の特徴でもあります。その際、布地からシャツを作りますが、端切れが出ますし、副素材の再利用や販売・買戻もあります。
副素材とは例えば糸巻きなど。木製のものとかいろいろありますが、これを糸と同時に販売することもあります。さらには、もう一度違う糸を巻いて買い戻すケースもあります。
製品原価の計算:使用した材料=月初在庫金額+当月仕入金額―月末在庫金額
多種類の原材料から複雑な加工をすることから、製品の原価計算は一般的に月次総平均を採用してるところが多くなっています。どれだけ使ったかを、前月末の在庫と今月末の在庫の差額で算出する方法です。
計算上で求めることから、売上原価が確定するのが月末になります。このあたりが独特なところですね。
営業システム[化学品]
化学品は食品に似て、液体・粉末・固形物など在庫管理が多様で、輸送中/保管中に、蒸発、揮発などにより数量が変化してしまいます。
毒劇物の管理(管理薬剤師が必要)
化学品で特殊なことは、劇薬や毒物などの管理において、国への報告が義務づけられていることです。このため、商社の中に管理薬剤師を雇ってるケースもあります。
液体・粉末・固形物など在庫管理が多様
化学品は液体あり、粉末あり、固形物ありと、在庫の管理がなかなかやっかいです。
これらそれぞれにおいて次に紹介する「輸送中/保管中に数量変化」への注意が必要です。
輸送中/保管中に数量変化
液体は、アルコールのように揮発して、使わなくても量が次第に減っていく現象があります。グラムとかリットルとかで単価を決めてはいますが、通関する時や月末に棚卸する時は袋の数や容器の数しか数えません。いちいち出荷の前に確認することがありませんから、納品して初めて数量の違いに気づいて、クレーム処理が発生することがあります。ここが独特です。
粉末については、購入時は25キロの袋であったものを小分けして販売することが多くあります。トン単位のコンテナで購入し、小分けすることもあります。買う時と売る時で、容量が変わってしまうという特徴があります。
営業システム[プラント・工事]
プラントや工事も商社が扱うことが多くなっています。複数の工事事業者を束ねて、窓口が商社となるわけです。
進捗管理(工事進行基準による計上)
プラント・工事においては進捗管理が必要になります。
商社が窓口になって、海外のダム建設などの大型プロジェクトをすることになりますが、工事進行基準による売上計上や原価計上が求められます。
当該案件・プロジェクトに関する必要経費も原価に算入
窓口となった商社がちょっとやっかいになるのは、海外での工事において、現地で発生した諸経費の計上です。例えば、ブラジルの場合はペソで使用した経費も原価として入れなければなりません。
下請法の未成工事支出金(在庫)計上が必要
商社に大型工事を依頼するメリットは、小さな工事会社を複数社まとめて、大きな仕事を遂行できるところにあります。
この場合、下請法によって、早めにお金を支払う義務が発生します。未成工事支出金の計上です。まだ工事は完成してないにもかかわらず、支出が発生します。
商社は資金力があっても、5年や6年のプロジェクトになると、数十億さらには数百億円になりますので、さすがに無理があります。そこで、エンドユーザーからも進行基準に応じて、受入金をもらう交渉が必要になります。こうしないと、商社も立ち行かなくなります。
ERPのカスタマイズ?それとも別システムからのデータ連携?
以上、主だった業種の営業システムのポイントを解説しました。これら営業システムで求められるのが、ERPとして構築するのか、外付けのシステムとして別途用意するのかという判断です。
ERPが日本に輸入された当初、全社でリソースを一元管理しようという理想の元、最前線の営業システムもバックエンドの財務会計システムもERPでカバーするシステムのあり方が流行した時期がありました。
ところが上記のように、商社には独特の商品の扱い方があり、汎用システムとのギャップを解消するため、大幅なカスタマイズを加えることになります。これが1つの方法です。
もう1つ、各営業システムはERPとは独立させて、冒頭で紹介したように必要な情報のみを吸い上げる仕組みを用意する方法もあります。
前者が全体最適を求め、後者が個別最適を求めています。
ERPで全社をカバーする全体最適は理想ですが、どうしてもERPの制限を受けて一部要求を満たせないシステムとなり、ユーザーに我慢を強いることになります。これを回避するため、日本企業の多くはカスタマイズを加え、構築に時間と経費をかけていました。構築後は維持コストもかかり、ERPのバージョンアップも簡単にできない状態となっています。
後者の個別最適では、ERP本体と営業システムの間に契約・受渡共通システムをかませてデータ連携させます。双方のデータを共通フォーマットにするデータ連携(ETL / EAI)ツールですね。あらかじめ情報の粒度を整えておく必要があります。
現在では、こちらの方が流行りつつあるような感じがしています。
最後に
今回は商社の営業部門の各システムのポイントを紹介しました。これで、商社におけるERPの説明が完了することになります。
第1回で解説したように、商材を右から左に流すことではなく、商社を通すことによる付加価値が求められるようになっています。その付加価値の1つが情報であり、また情報がヒントとなり新たなビジネスチャンスを生み出すことが可能となります。
情報システムの重要性が増していることはもちろん、システムの柔軟性も不可欠になっています。環境変化に対応できること、そして全社情報を集約してさまざまな角度から分析できることが求められています。
商社のERP構築や活用について幅広くご質問や相談を受け入れております。お気軽にお問い合わせください。
またお会いできることを楽しみにしています。

1993年 双日システムズ(現:日商エレクトロニクス)に入社、双日および双日グループ企業向け業務システム開発・保守に従事。
2000年 システムインテグレータ企業おいて、数多くのプロジェクトに、SE、リーダー、マネージャーとして参画。
2006年 SI事業部門の本部長(執行役員)として、ERP事業(GRANDIT)の立上げ、ビジネス戦略を担当しながら、大型重要案件ではプロジェクトマネージャーとして従事。 多数のERP導入プロジェクトを主導した経験を持ち、特に商社業務に精通。
2020年3月 研修講師およびコンサルタントとして独立。
現在は、各種引合い案件に対する提案支援、複数のERP導入プロジェクトの構想策定フェーズや要件定義フェーズに参画し、概算費用見積りの基準作成などの各種コンサルティングに従事している。
保有資格: PMP(Project Management Institute会員)
IPA認定 高度情報処理技術者
PMI🄬R.E.P.(Registered Educational Provider)認定講師
