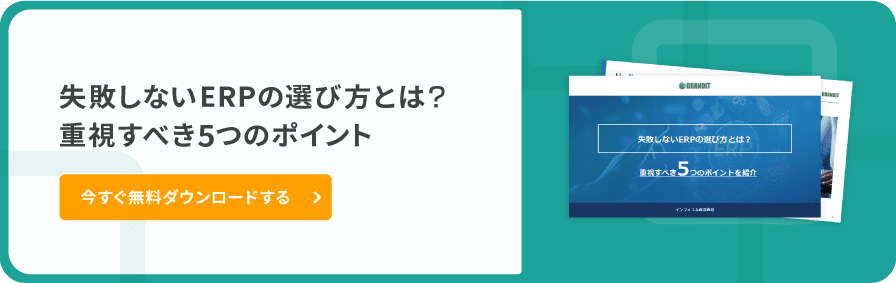SAP 2027年問題と国産ERPという選択肢 〜企業はいま、どう動くべきか?〜

1.はじめに
ERP(Enterprise Resource Planning)とは、企業の会計・販売・購買・在庫・生産管理といった基幹業務を統合的に管理するシステムです。ドイツのSAP社はこの分野のリーディングカンパニーであり、世界中の大企業を中心に幅広く導入されてきました。特に「SAP ERP Central Component(ECC 6.0)」は、2000年代後半から2010年代にかけて多くの日本企業でも採用され、現在も稼働中の企業が数多く存在します。
日本国内でも、製造業を中心に中堅企業まで幅広く導入されており、SAP ERPは事実上「業務の中枢を担うITインフラ」としての役割を果たしてきました。
本コラムでは、SAP ERPや「SAP 2027年問題」の本質を解説。企業が取るべき対応策をご紹介していきます。
SAP 2027年問題とは何か?
現在稼働している「SAP ERP ECC 6.0」の標準保守サポートが2027年末に終了することが、SAP社から正式に発表されています(延長オプションにより2030年までサポートされるケースもありますが、追加費用が発生します)。このサポート終了を指して、業界では「SAP 2027年問題」と呼ばれています。
ERPを含めて、ソフトウェア製品の保守が終了すると以下のようなリスクが現実のものとなります。
(ソフトウェア製品保守終了時のリスク)
- セキュリティパッチが提供されない
- 不具合修正や法令対応が受けられない
- サポート対象外の製品として社内ITの運用が困難に
- ERPを基盤とした周辺システムにも影響が波及する
特に、内部統制やコンプライアンスを重視する企業にとって、サポート切れのERPを使い続けることは致命的なリスクになり得ます。
(SAP ERPサポート終了スケジュール)
| 年度 | 内容 |
|---|---|
| 2020年以前 | ECC 6.0(古いEHP)の一部終了 |
| 2027年12月末 | ECC 6.0の標準保守終了 |
| 2030年12月末まで | 延長保守オプション(有償)あり |
※SAP S/4HANAは既に新しい製品として展開中
上記スケジュールを見てもわかる通り、企業は遅くとも2027年までに何らかの対応を決定・実行しなければならない状況にあります。
「SAP 2027年問題」は中堅企業にとっての深刻な課題
大手企業の多くは既SAP S/4HANAへの移行プロジェクトを開始しています。しかし、中堅・中小企業の中には以下のような理由から移行や対応方針を決めきれずにいるケースも多く見られます。
- ERP刷新のための予算や人材が不足している
- SAP S/4HANAへの移行が自社業務にどれほど影響するか不透明
- 他の業務改革やDX施策が優先され、ERP移行の検討が後回し
特に、現状のSAP ERPが「業務に支障なく使えている」企業ほど、移行の必要性を実感しづらく、結果として「ギリギリまで動けない」構造になっています。
2027年問題は“システムの寿命”ではなく“選択のタイムリミット”
SAP 2027年問題は単なるサポート終了の話ではありません。企業が自社の基幹業務を今後どう設計し、どんなIT基盤で支えるのかという経営判断のタイムリミットでもあります。
特に中堅企業にとっては、次のような観点での意思決定が求められています。
- 業務プロセスの見直しを含めたERP刷新の必要性
- 海外製品に依存しない選択肢(国産ERPなど)の可能性
- IT投資の費用対効果と自社に合った規模感
2.SAP S/4HANAへの移行がもたらす“重い”決断
SAP ERPの後継製品として、SAP社は「SAP S/4HANA(エスフォーハナ)」への移行を強く推奨しています。SAP S/4HANAは、インメモリデータベースであるHANA上に構築された次世代型ERPであり、従来のSAP ERPに比べて次のような特長を持っています。
- 大量データの高速処理を実現するHANA DB
- UIの刷新(SAP Fioriによる直感的操作)
- 分析とトランザクション処理の統合
- クラウド/オンプレミスの両対応
SAP社としては、既存ユーザーに対してSAP S/4HANAへの早期移行を促進しており、実際に多くのグローバル企業はこの新しいプラットフォームへの移行を進めています。
(SAP ERPとSAP S/4HANAの比較)
| 項目 | SAP ERP(ECC 6.0) | SAP S/4HANA |
|---|---|---|
| データベース | Oracle/DB2等 | SAP HANA(インメモリDB) |
| 操作画面 | SAP GUI | SAP Fiori(WebベースUI) |
| 処理スピード | 通常のDBベース | 高速処理(リアルタイム) |
| 導入形態 | 主にオンプレミス | クラウド/オンプレ両対応 |
| 業務プロセスの柔軟性 | カスタマイズが前提 | 標準プロセス推奨 |
SAP S/4HANAは、単なるシステムのアップグレードではなく、データベース・UI・業務設計すべてを刷新する“別物のERP”です。そのため、「移行」というよりも、実態は再導入に近い規模とコストが発生します。
SAP S/4HANA移行に必要なもの ~時間・費用・体制~
一般的なSAP S/4HANAへの移行プロジェクトでは、以下のようなリソースが求められると考えられますが、中堅中小企業にとって、この規模感のプロジェクトは容易に着手できるものではありません。
(SAP S/4HANA移行プロジェクトのイメージ)
- プロジェクト期間:12〜36か月
- 総投資額:数千万円〜数億円
- 必要人員:業務部門・IT部門の長期関与
- 移行方式の選定(現行システムをそのまま移行 / ゼロベースで再構築)
中堅企業にとってのハードル
SAP ERP のサポート終了を機にERPのリプレースを検討している、実際の企業ヒアリングでも、以下のような声が数多く聞かれています。
- 現行システムの内容が複雑で、どこまで移行できるのか不明
- SAP S/4HANAの新機能を活用するほど自社の業務改革が進んでいない
- 国内事業が中心なので、SAP S/4HANAの全機能を必要としない
- 数億円単位の投資判断を出すには、経営陣の納得が得られない
- 業務が忙しく、ERPプロジェクトに人を割けない。導入できるSIerがいない
特に、過去10年以上にわたってカスタマイズを重ねてきた企業ほど、移行の障壁は高くなります。「やらなければいけないと分かっていても、どうしても踏み出せない」のが多くの中堅企業の現状ではないでしょうか。
「SAPありき」からの見直しが必要な理由
SAPは確かに世界的なERPのスタンダードであり、多機能で強力な製品です。しかし、以下のような「SAPありき」の判断基準に縛られることは、企業の将来にとって必ずしも最善とは言えません。
- 製品の進化がベンダー主導であり、柔軟性に欠ける
- グローバル対応が中心で、日本の商習慣にはやや不向き
- 自社にとって“使い切れない”機能が多く、オーバースペック
SAPは、日本におけるERP導入の黎明期に導入が進みましたが、これからは自社の規模・業種・将来ビジョンに応じて「本当に必要なERPは何か?」を見極める時代です。つまり、「SAPだから安心」ではなく「自社に合うかどうか」で判断すべきなのです。
3.本質的な課題は「システムの老朽化」ではなく「業務改革の遅れ」
SAP ERPの保守終了が目前に迫っていても、多くの企業で「移行が進まない」「判断ができない」という現状があります。その背景にあるのは、単なるシステムの老朽化という問題ではなく、業務そのものが変化に追いついていないという、より本質的な課題です。
つまり、ERPの更新を「ITの問題」として捉えるのではなく、「業務改革の一部」として向き合わなければ、根本的な解決には至りません。
ERPは“業務の鏡”である
ERPは企業の業務プロセスをそのまま反映するシステムです。販売から会計、在庫、調達、製造に至るまで、あらゆる業務がERP上に組み込まれ、データとして流れています。つまり、ERPの設計や運用に現れてくるのは、その企業の業務のあり方そのものです。
以下のような状態のままでは、どんなに優れたERPに乗り換えたとしても、その効果を十分に発揮することはできません。
- 担当者しか分からない属人化された業務フロー
- システム外で行われているExcelによる“裏作業”
- 時代に合わない承認ルールや紙ベースの運用
- 課や部門ごとに最適化された“縦割り構造”
これらは、ERP刷新の際に必ず“表に出てくる”問題です。
(ERP刷新時に直面する業務の課題)
| 課題項目 | 具体例 |
|---|---|
| 業務の属人化 | 特定担当者しか処理できない |
| ブラックボックス化 | 既存ERPに複雑なカスタマイズがされている |
| プロセスの非効率 | 紙とExcelの二重管理、重複入力 |
| 全体最適の欠如 | 部門単位で最適化され、全社視点がない |
| 法令・制度変更への非対応 | インボイス制度や電子帳簿保存法への未対応 |
これらの課題を放置したままSAP S/4HANAに移行したとしても、結果として“旧態依然の業務を新システムに載せ替えただけ”という事態に陥りかねません。
「基幹業務の見直し」は避けて通れない
ERPの導入や刷新は、単なるツールの置き換えではなく、企業活動そのものの再設計でもあります。そのため、以下のような問いに真正面から向き合う必要があります。
- 現在の業務フローは本当に必要か?
- 顧客価値に直結していない業務を見直す余地は?
- 社内のデジタルリテラシーは十分か?
- 業務を標準化・共有化できる仕組みはあるか?
ERP刷新は、これまで見過ごされてきた「非効率」や「曖昧さ」をあぶり出し、業務の標準化や全社最適を実現する絶好の機会でもあります。
ERP刷新におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の視点
近年、多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を掲げていますが、ERP刷新はその中核に位置づけられます。ただし、単なる「デジタル化」ではなく、組織・人材・文化を含めた業務全体の変革として捉える必要があります。
ERP刷新=業務改革 × IT活用 × 組織変革
このような観点を持たずに、単に「保守が切れるから急いで移行しよう」と考えてしまうと、かえって高コスト・長納期・低効果なプロジェクトになりかねません。
「守りのIT」から「攻めのIT」へ
従来、ERPは「業務を支えるITインフラ」として、安定稼働とコスト削減が重視されてきました。しかし今後は、ERPを軸にデータドリブン経営や業務の自動化、新たなサービス創出へとつなげる「攻めのIT」としての活用が求められます。
S/4HANAのような高機能なERPも、導入しただけで価値を生むわけではなく、業務改革とセットで初めて成果が出るのです。
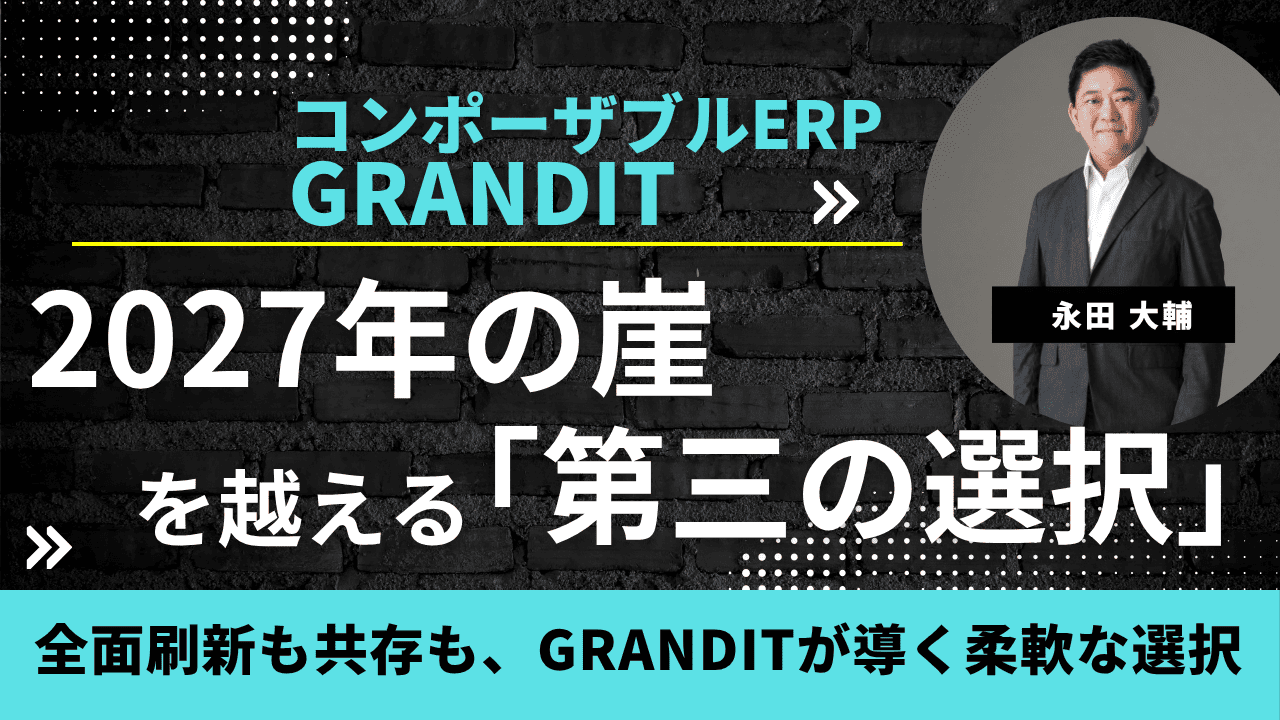
2027年の崖を越える「第三の選択」
2027年問題に備え、S/4HANAへの移行に頭を悩ませていませんか?高額な維持コストやブラックボックス化したアドオンetc...その課題、コンポーザブルERP「GRANDIT」が解決します。
4.選択肢はSAPだけではない―“国産ERP”という現実解
ERPといえばSAP、という認識は日本企業、とくに大手企業に根強く存在しています。これまでSAP ERP(ECC)は、その高い機能性と国際対応力を武器に、さまざまな業種・業態で導入されてきました。その流れを汲んで、中堅企業でも「次もSAPにしなければならない」「SAP S/4HANA移行は避けられない」と考えているケースが多く見られます。
しかし、現在の選択肢は、決してSAP一択ではありません。SAP ERP(ECC)のサポート終了を受け、企業が検討すべき選択肢は主に以下の3つに分類されます。
1)SAP S/4HANAへの移行
2)第三者保守によるSAP ERP(ECC)の継続利用
3)国産ERPへの刷新
このうち、短期的なコスト圧縮を狙った「第三者保守」、および現行SAP環境からの脱却を目指す「国産ERP」の検討が、とくに中堅企業にとって重要な選択肢となります。
(SAP 2027年問題の主な対応策と特徴比較)
| 比較項目 | SAP S/4HANA移行 | 第三者保守 | 国産ERPへの刷新 |
|---|---|---|---|
| 初期導入・移行コスト | 非常に高い(億単位も) | 低コスト | 比較的低コスト |
| 保守サポート体制 | SAP社が公式に対応 | 外部企業によるサポート | ベンダー・パートナーが対応 |
| 対応年数(将来性) | 長期安定(2030年以降) | 数年間の延命に留まる | 長期運用を前提とした設計 |
| 業務改革の実現性 | 要再設計・負荷高 | 業務変革は困難 | フィット型で実現しやすい |
| カスタマイズ対応 | 柔軟だがコストが高い | 現状維持前提 | 標準機能中心で簡潔に対応 |
| リスク | 大規模プロジェクト化しやすい | サポート終了時に対応困難 | リスク分散・段階導入が可能 |
第三者保守の“延命”は時間を買う手段だが、根本解決にはならない
第三者保守とは、SAP社のサポートが終了したERP(ECCなど)に対し、専門の外部企業が保守サービスを提供するモデルです。SAP S/4HANAへの即時移行が難しい企業にとって、コストを抑えながら現状システムを延命できる点で注目されています。
(第三者保守のメリット)
- 本格移行までの猶予期間を確保できる
- 保守コストを抑えられる
- 現場の業務フローを大きく変えずに済む
しかし、この手法は「本質的な解決策ではなく、あくまで時間稼ぎ」であることを理解しておく必要があります。特に以下のような課題があります。
(第三者保守のデメリット)
- セキュリティアップデートや法制度対応が遅れがち
- 現場の業務改善や業務変革が進まない
- ベンダー依存が強く、次の一手が打ちづらくなる
- 終了後は、SAP以外のERPを新たに導入することになる
第三者保守はあくまで“つなぎ”であり、次の戦略的ステップが必須となるのです。
国産ERPの選択肢が現実的な理由
第三者保守に対して、国産ERPは中堅企業が自らの業務に即した形で、無理なく業務改革・DXを推進できる選択肢として注目が高まっています。従来の「機能が少ない」「小規模向け」といったイメージは過去のものであり、今では次のような特長を備えています。
- クラウド対応による導入の容易さと柔軟性
- 日本の商習慣や法制度への標準対応(インボイス、電子帳簿保存など)
- 中堅企業の業務にフィットした標準テンプレートの充実
- ベンダーと密なコミュニケーションが可能な支援体制
とくに、「複雑すぎないERPを、限られたリソースで、きちんと使いこなしたい」という企業のニーズに対しては、国産ERPが最もバランスの取れた選択肢となり得ます。
ケーススタディ:国産ERPを選んだ企業の決断
【事例1】製造業A社(従業員約300名)
SAP ERP(ECC)を利用していたが、移行費用が億単位になることから、まずは第三者保守を検討。しかし「変えないことによる業務の非効率」が明確化し、国産クラウドERPへ刷新。約1年で移行を完了し、各部門の業務が可視化・標準化されたことで、経営判断の迅速化にもつながった。
【事例2】卸売業B社(従業員約150名)
分断された基幹システムと、SAPの保守期限への不安から、SAP S/4HANAと国産ERPを比較検討。当初は第三者保守も考えたが、「保守延命は変革の機会を逃す」との経営判断で、業種特化型の国産ERPを採用。会計・販売・在庫を一元管理し、内部統制と業務効率が飛躍的に改善された。
「守りの保守」ではなく「攻めの刷新」へ
SAPのサポート終了に直面する中で、単に今のシステムを延命する“守り”の対応では、これからの経営環境の変化に適応することは難しいでしょう。
中堅企業にとって今必要なのは、コスト・人材・スピード・業務改革のすべてにおいてバランスの取れた現実解=国産ERPを選び、自社に合った形で着実に「変わる」ことです。
5.国産ERPで実現する“持続可能なシステム運用”
ERP導入において最も重要なのは、「導入した後に、どれだけ使いこなせるか」という運用フェーズです。大規模なIT投資をしても、現場に定着せず活用されなければ、本来得られるべき効果――業務効率化、データの可視化、経営の迅速化――は実現されません。
とくに中堅企業では、「IT専門の部門や人材が限られている」「属人化された業務が多い」といった背景から、“現場に寄り添った運用設計”と“シンプルでわかりやすいシステム”が必要不可欠で、国産ERPの強みが真価を発揮します。
(ERP運用フェーズの課題と国産ERPの対応力)
| 課題 | 従来型ERPの対応 | 国産ERPの特徴 |
|---|---|---|
| IT部門の負荷が高い | システムが複雑で保守作業に手間がかかる | パートナー支援やクラウドで社内保守作業が最小限 |
| 業務部門が使いこなせない | 専門知識が必要、UIが複雑 | 日本語UI、直感的操作で現場定着 |
| カスタマイズが多く属人化 | ベンダー依存が強く、変更に時間とコスト | 標準機能重視、業務テンプレート活用 |
| 改善活動が停滞する | システム変更が大がかりになり改善進まず | 小規模改修でPDCAが回しやすい |
「国産ERP」こそ、中堅企業にフィットする理由
中堅企業にとって、ERPは“改革のためのツール”であると同時に、日常業務を支えるインフラでもあります。以下の観点で、「運用に強い国産ERP」は中堅企業の経営にマッチしています。
1)中長期的な運用コストを抑えやすい
初期導入だけでなく、保守・運用フェーズでもクラウド活用や標準機能の活用により、システム維持コストが抑えられます。
2) “日本の商習慣”へのフィット感
請求書処理、債権管理、インボイス制度や電子帳簿保存法といった日本独自の要件に標準で対応している国産ERPは、追加開発や外部連携の手間が少なく済みます。
3)ベンダーとの距離が近い
中堅企業の場合、ERPの専門人材が社内に少ないことも多いため、導入後も相談しやすい距離感の支援体制が大きな安心材料となります。
導入後の「PDCA」サイクルを回す仕組みが整っているか
ERPの価値は、導入直後よりも運用を通じて業務改善を積み重ねる中で高まっていきます。この運用段階でPDCA(Plan-Do-Check-Act)をうまく回すには、以下の3つが重要です。
1)見える化されたKPI
販売実績、在庫回転率、予算実績などのKPIをERP上でリアルタイムに可視化し、意思決定に活かす。
2)部門横断の改善プロジェクト
ERPを共通基盤とし、経理、営業、生産など部門間で連携した改善活動が可能。
3)小さく回せる改善サイクル
ユーザー自身で設定変更や項目追加ができる柔軟な設計により、ベンダー依存せずスピーディに改善を実行。
これらの仕組みを支えるERPこそが、“持続可能な経営基盤”となり得るのです。
成功の鍵は「ベンダー選定」と「運用設計」
国産ERPが持つポテンシャルを最大限活かすには、導入時の「要件定義」と「運用設計」が極めて重要です。導入ベンダーやパートナー企業との連携体制、業務とのすり合わせ方次第で、その後の運用難易度や改善スピードに大きな差が出ます。
成功企業の共通点は以下のとおりです。
- 業務部門を巻き込んだ導入体制を構築
- ベンダーと二人三脚で、現場業務に沿った運用設計を実施
- 導入後も月次・四半期ごとの活用状況レビューを継続
このように、SAPの2027年問題が迫る中、単に“移行するか、しないか”という視点にとどまらず、「自社がERPをどう活かしていくか」を主軸にした選択が求められています。
国産ERPは、「自社に合った業務システムを、自分たちの手で運用し、改善を重ねていける」環境を実現します。これは中堅企業にとっての “現実解”であると同時に、成長戦略の基盤となるのです。
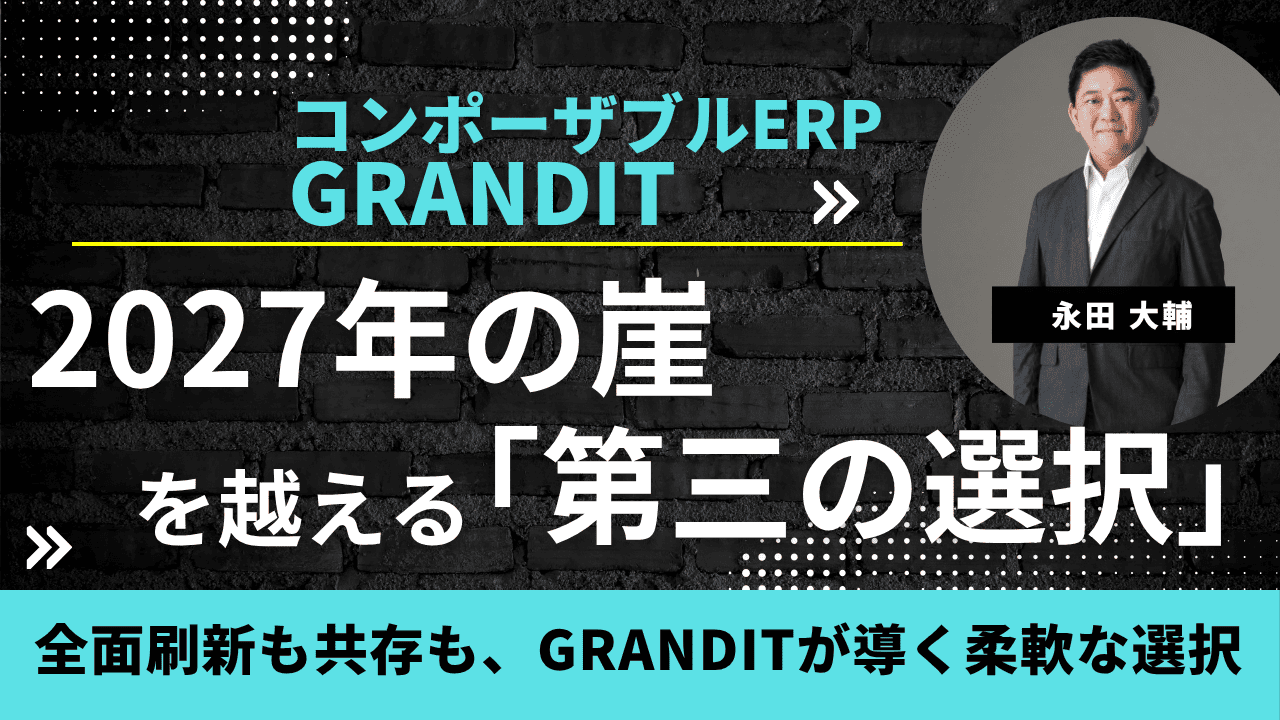
2027年の崖を越える「第三の選択」
2027年問題に備え、S/4HANAへの移行に頭を悩ませていませんか?高額な維持コストやブラックボックス化したアドオンetc...その課題、コンポーザブルERP「GRANDIT」が解決します。
6.導入から定着へ―国産ERPを成功に導く5つのステップ
SAPのサポート終了が迫るなか、「何を選ぶか」だけでなく、「どう導入・活用するか」が中堅企業にとって極めて重要です。ここでは、国産ERPを導入し、継続的に活用するための“5つの成功ステップ”を具体的に解説します。
ステップ1:目的を明確にする ――「何のためのERPか?」
ERP導入プロジェクトが失敗に終わる原因の多くは、「導入そのものが目的化してしまう」ことにあります。まずは経営層と現場の間で、“導入の目的”を明文化することが最初の一歩です。
(目的の例)
- 業務の標準化と属人化解消
- 業績データの一元化による経営判断の迅速化
- インボイス制度・電子帳簿保存法などの法対応
このように目的を明確にすることで、ERP選定や機能要件の判断軸がブレなくなります。
ステップ2:パートナー選定 ――「システム導入の“伴走者”を見極める」
ERPの成否を大きく左右するのがパートナー企業の選定です。特に国産ERPでは、業種業態に強いパートナー企業が多数存在し、手厚い導入支援が期待できます。
(パートナー選定のチェックポイント)
| チェック項目 | 確認ポイント例 |
|---|---|
| 導入実績 | 同業種・同規模の企業での導入事例があるか? |
| 導入支援体制 | 専任担当の有無、現地訪問や定例ミーティングの頻度 |
| コンサルティング力 | 単なる操作説明でなく、業務改善提案があるか? |
| サポートの継続性 | 導入後の保守・活用支援まで継続しているか? |
ステップ3:段階的な導入 ――「スモールスタートで確実に定着」
中堅企業では一度にすべての機能を入れ替える「ビッグバン導入」よりも、段階的な導入(フェーズ導入)が現実的でリスクも少ない方法です。
(段階的導入の例)
1)まずは会計・販売・購買など“共通業務”から着手
2)次フェーズで製造・在庫・人事給与などの“業種特有業務”を追加
3)最終的にはBIや経営ダッシュボードなど高度な活用に展開
このようにシステムを段階的に導入することで、社内の業務改革とシステム定着を同時に進めることが可能になります。
ステップ4:教育とマニュアル ――「現場に“使いこなす力”を」
ERP導入の成功は、現場でシステムが“使われるかどうか”にかかっています。そのためには、ユーザー教育と現場目線のマニュアル整備が不可欠です。
(具体的な施策)
- 操作トレーニングの開催(動画・マニュアルも併用)
- よくある業務パターンに合わせた「業務別操作フロー」
- 部門ごとの“スーパーユーザー”の育成
システム導入時点で「業務に合わせたトレーニング設計」ができているかどうかで、定着率が大きく変わります。
ステップ5:活用の仕組み化 ――「改善サイクルを回す」
ERPは“導入して終わり”ではなく、改善の起点となる仕組みです。定期的な活用レビューや、部門横断の改善会議を設定することで、導入効果を持続的に高めることができます。
(改善活動の運用モデル)
| 活動内容 | 頻度 | 目的 |
|---|---|---|
| 活用状況の振り返り | 月次 or 四半期 | 定着状況の把握・課題の洗い出し |
| 改善テーマの検討 | 半期に1回 | ERPを活用した業務改善施策の立案 |
| ベンダー相談会 | 年2~4回 | 操作・機能改善に関するフィードバック |
ERPを軸にした継続的改善活動(カイゼン)は、国産ERPベンダーや導入パートナーが支援するケースも多く、社内の取り組みに外部知見を取り入れる好機となります。
(国産ERP導入 成功の5ステップ)
1)目的を明確にする ── 導入の意義と目標を全社で共有
2)パートナー選定 ── 信頼できる支援体制を持つ企業を選ぶ
3)段階的導入 ── 無理のないスモールスタートで推進
4)教育とマニュアル ── 現場が自走できる仕組みを整備
5)活用の仕組み化 ── 継続的な改善サイクルを構築
7.システムの入れ替えをチャンスと捉え、持続可能な業務基盤づくりを
SAP 2027年問題を単なる“システムの入れ替え”として捉えるのではなく、自社にとっての業務変革とデジタル活用の再設計と考えることが重要です。
国産ERPという選択肢は、「現場に強い、運用に強い、継続性に強い」解決策であり、中堅企業にとっては極めて実践的なソリューションです。
この機をチャンスと捉え、「持続可能な業務基盤づくり」に踏み出してみてはいかがでしょうか。
※ERPシステム選定のポイントについて、以下コラムも参照ください。
・基幹システムの入れ替え失敗事例、原因と対策
・正しいERPリプレイスの進め方5つのステップと成功事例