消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
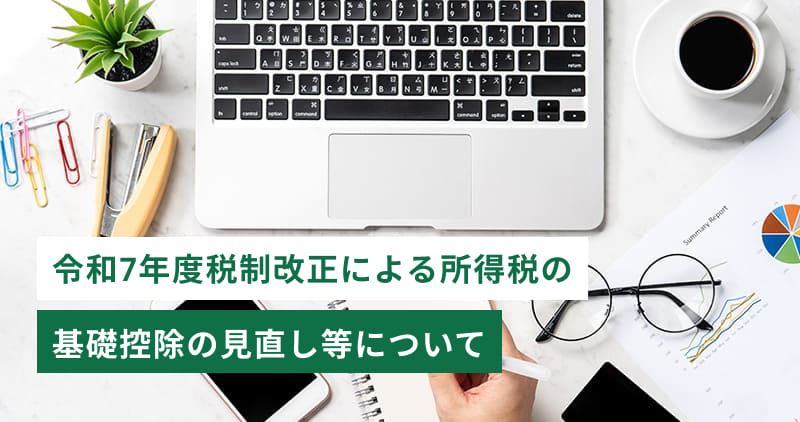
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
令和7年4月21日に、国税庁から公表されている「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が更新されました。改訂及び追加が行われています。今回は追加された問(抜粋)のポイントに関して、簡単に紹介を行います。
以下、要約になります。
【問17-2】
適格請求書発行事業者が、基準期間における課税売上高が 1,000万円を超えることとなった場合、「消費税課税事業者届出書」の提出が必要か否か。
(回答要約)
適格請求書発行事業者の登録を受けている課税期間については、「消費税課税事業者届出書」を提出しなくて差し支えなし。
【問72-2】
交付する領収書において、HPのURLを案内しておき、当該URLに適格請求書の記載事項の一部である事業者の名称及び登録番号、適用税率を表示した上で、当該領収書を受領した事業者はいつでも確認可能な状態にしている。このような場合、適格請求書の記載事項を満たしているか否か。
(回答要約)
- 適格請求書は、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、書類相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引を正確に認識できる方法で交付されていれば、全体により、適格請求書の記載事項を満たす。
- インターネット上のサイトを通じた方法も可能だが、基本的に、取引に応じて交付した領収書等とは関係なく、適格請求書の記載事項の一部を自社のホームページに掲載しておくだけでは、当該領収書等と電磁的記録の相互の関連が明確とはいえない。
- 領収書等にインターネット上のページに係るURLを表示しておき、当該URLにアクセスすることで適格請求書の記載事項として不足する事項が補完されるのであれば、相互の関連が明確であるものとして、双方の記載を合わせて適格請求書の記載事項を満たすこととして差し支えなし。
- 売手がホームページの該当箇所を、各税法に定められた保存期間が満了するまで随時確認可能な状態で提供しているなど一定の要件を満たす場合、買手においては必ずしも当該電磁的記録をダウンロードせずとも、その保存があるものとして差し支えなし。
【問77-3】
1年を超える期間にわたって毎月保守を行う役務を提供している。課税期間をまたぐような長期間にわたる課税資産の譲渡等について、対価の前受け時にまとめて適格請求書を交付する事は可能か否か。
(回答要約)
- 「課税資産の譲渡等を行った年月日」については、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき、まとめて適格請求書を作成する場合には、当該一定の期間を記載する。
- ただし、「課税期間の範囲内で」とあるとおり、一定の期間をまとめて適格請求書を交付するとしても、取引の期間が売手の課税期間をまたぐ場合には、適格請求書は課税期間ごとに区分し交付することが原則。
- 他方、課税期間をまたぐ期間に係る取引をまとめて一の適格請求書に記載することも妨げられるものではなく、また、課税資産の譲渡等を行う前に適格請求書を交付することも可能。
【問106-2】
古物営業法上の許可を受けて古物営業を営んでいる個人事業者が、フリーマーケットアプリやインターネットオークションを通じて商品を仕入れる際、取引の相手方が匿名の場合がある。この場合における仕入税額控除の適用を受ける要件。
また、固定資産などを仕入れるような場合や、古物商以外の者が仕入れるような場合に、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除することができる経過措置の適用は可能か否か。
(回答要約)
- フリマアプリ等による仕入れに係る古物商等特例の適用について、古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、※「適格請求書発行事業者以外の者」から棚卸資産として古物を買い受けた場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることが可能。
-
古物商が、フリマアプリ等により商品の仕入れを行った場合、対価の総額が1万円未満であれば、古物台帳に相手方の住所、氏名、職業及び年齢の記載は不要であるため、匿名で取引が行われていたとしても古物商等特例の適用は可能。
ただし、1万円以上の場合、それらの記載が必要となるため、これらの点について、古物営業法に規定された方法により相手方の確認を行う必要がある。
※適格請求書発行事業者以外の事業者や消費者が該当。例えば、適格請求書発行事業者である個人事業者であったとしても、消費者として譲渡する場合には、適格請求書発行事業者以外の者と取り扱って差し支えなし。
また、メッセージ機能等により「適格請求書発行事業者としての譲渡である場合は登録番号を教えてください。連絡がない場合には、消費者としての譲渡と考えさせていただきます。」と確認を行った上で、何らの連絡がない場合には、仕入先を適格請求書発行事業者以外の者と取り扱って差し支えなし。
-
古物商以外の者がフリマアプリ等で仕入れた場合には、80%・50%経過措置の適用を受けることは可能。
この点、80%・50%経過措置の適用を受けるに当たり保存する必要がある区分記載請求書等に記載すべき「書類の作成者の氏名又は名称」及び帳簿に記載すべき「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」については、「フリマアプリ等の名称及び当該フリマアプリ等におけるアカウント名」として差し支えなし。
| 古物商による仕入れ ※1 | 古物商以外の事業者 による仕入れ (古物営業外) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古物 | 準古物 | |||||
| 1万円以上 | 1万円未満 | 1万円以上 | 1万円未満 | |||
| 本人確認 | 住所・氏名 職業・年齢 把握可能 |
古物商等特例 適用可能 |
80%・50% 経過措置 |
|||
| 住所・氏名 職業・年齢 把握可能 |
※2 | 古物商等特例 適用可能 |
80%・50% 経過措置 |
古物商等特例 適用可能 |
||
※1:適格請求書発行事業者以外の者から行った棚卸資産としての仕入れに限ります。
※2:古物営業法上、古物台帳に住所、氏名、職業及び年齢を記載する義務が生じる事から、それらの情報が把握できない場合は想定されません。
<参考>
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

公認会計士・税理士。大手監査法人勤務を経て現職。
大手監査法人において12年にわたり、公認会計士として、主に会計監査業務及び会計支援業務、内部統制監査業務及び内部統制支援業務、IFRS支援業務に従事するほか、IPO支援業務、任意監査業務、不正対応業務、財務デューデリジェンス業務等を多数手掛ける。上場準備会社を東証1部上場会社まで支援した実績あり。
上場企業はもちろんのこと中小企業の会計支援、管理体制支援及びスタートアップ企業のIPO支援、M&Aを得意とする。
大田区蒲田の税理士 税理士法人Right Hand Associates
