2025年問題とは何か?

1:「2025年問題」「2025年の崖」とは?
「2025年問題」というキーワードを耳にしたことがあるのではないでしょうか。日本の人口は2010年を境に減少を続け、2025年までに高齢者の人口が約709万人増加します。これにより国民の4人に1人が後期高齢者という、世界のどの国も経験したことのない超高齢化社会が到来。一方で生産年齢人口が約1,089万人減少するため、このままでは社会保障や医療・介護など多くの領域での破綻が懸念されています。
ITの分野においてもその影響は少なくありません。2018年9月、経済産業省はDX(デジタルトランスフォーメーション)レポートと呼ばれるレポートを発表しました。アーキテクチャも、使われているプログラミング言語も、古い既存の基幹系システム(レガシーシステム)が複雑化・ブラックボックス化しているため、2025年以降、その維持・管理コストがIT予算の9割以上に達し、企業は衰退して国際競争力を失うことになるというのがその趣旨です。しかし、エンジニアに代表されるIT人材の高齢化や定年退職がこのブラックボックス化に拍車をかけているのです。
たとえば、レガシーシステムで使われている古いプログラミング言語を知るエンジニアは、ベテランエンジニアの引退により圧倒的に減少しています。しかし、若いエンジニアが古いプログラミング言語を学ぶ機会などほとんどないのが現状です。レガシーシステムに使われている言語を知らないエンジニアばかりになれば、自ずとそのシステムはブラックボックス化してしまいます。
現実は、大手企業で運用されている基幹系システムの過半数が導入後20年以上経過しており、2025年には21年以上稼働し続けている基幹系システムが6割に達するというシステム老朽化の時代を迎えます。にもかかわらず、保守・管理できる人材はどんどん減り続けるばかり。2015年には17万人が不足していたIT人材が、2025年には43万人にまで拡大するのではと懸念されています。
DXレポートが指摘しているブラックボックス化の要因としては、ほかにも「ユーザー企業よりSIer(システムインテグレーション事業を行う企業)やベンダー企業にITエンジニアが多く所属している」事実も挙げられます。ユーザー企業には、システムの詳細を知る人材が元々少ない状況です。そんな数少ない人々も、定年退職で社を去っていく。SIerやベンダー企業でも同様の事態が頻発するという悪循環が起きています。加えて企業の合従連衡やビジネスの多角化・多様化などにより、屋上屋を重ねる形でシステムが統合され、ますます複雑度が増している事実もあります。DXレポートでは、レガシーシステムの維持だけで2025年以降は年間約12兆円もの損失を被る可能性があると警告しています。
これが、DXレポートが「2025年の崖」と名付けた危機で、企業経営のみならず社会的にも大きな課題となっています。DXとは最新のデジタル技術を駆使することで、企業が戦略やプロダクト、業務フローなどを変革させ、新たなビジネスモデルを創出・改変していくことを表す概念です。主にシステムを刷新することでDXを実現し、2030年には実質GDP130兆円超の押上げを目指すことがDXレポートでは標榜されています。
2:もう一つの「2025年問題」
「2025年問題」には、ERPパッケージベンダーの最大手である独SAP社に由来するものもあります。同社のSAP ERPや、SAP ERPにSCM(サプライチェーン管理)やCRM(顧客関係管理)機能を追加したSAP Business Suiteの保守期限が2025年で終了してしまう「2025年問題」です。一企業に端を発する問題ながら、こちらのインパクトも絶大です。なにしろSAP ERP は30年近くも業界トップを走り続けてきた製品であり、日本国内に限っても、2,000社に及ぶ企業で稼働しています。
ところが2020年2月、SAP社は2025年末から2年後の2027年末までの保守期限延長を発表しました。さらに、2%の延長保守料を支払えば、2030年末まで伸ばせるようにもなりました。保守期限の延長が発表されたのは今回が初めてではなく、2005年の現行SAP ERPリリース当初は2015年末までだったのが、2020年末、さらに2025年末と保守延長を重ねてきました。ユーザー企業から、それだけ多くの要望があったからです。
2年間延長されて「2027年問題」になったものの、前述した「崖」とこの「問題」がほぼ同時期に到来すること、2,000社ものSAP ERP導入企業が事業の根幹を支える情報インフラの更新を迫られている本質的状況に変わりはありません(DXレポートには「2025年の崖」を構成する要素として、「SAP サポート終了」が技術面の課題として挙げられていました)。通常であれば後継ERPにすんなりと移行できれば良いのですが、SAP ERPスイート製品の最新版であるSAP Business Suite 4HANA(S/4HANA)は、現行バージョンとは異なるシステムとなっており、移行は一筋縄にはいかないのです。
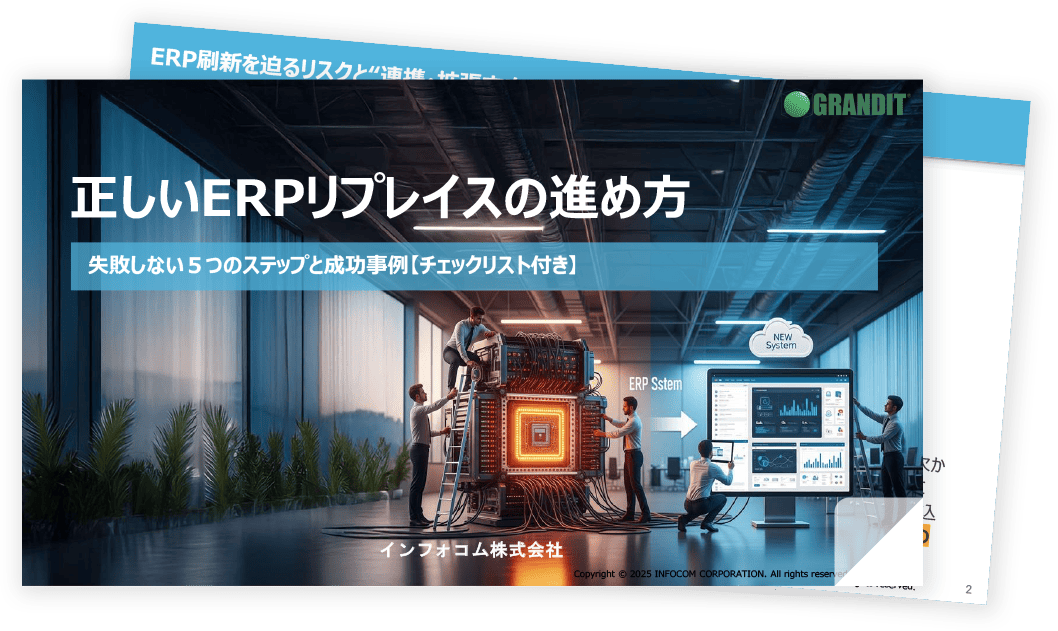
【ERP導入成功チェックリスト付き】正しいERPリプレイスの進め方
ERPリプレイスに取り組む前に確認したい3つのポイントと、計画から運用定着まで5段階で進める実行プロセス、さらに実践企業の事例を紹介します。

3:「2025年の崖」「2027年問題」への対処法
SAP ERPを導入しているユーザー企業がこれらの問題に対処するにはどうしたらいいのでしょうか。選択肢は3つです。
① S/4HANAへの移行
S/4HANAは現行SAP ERPの後継に位置付けられながら、アーキテクチャやデータベースは別物です。UNIX、Linux、WindowsといったさまざまなOS上で、さらに複数データベースで稼動可能な従来のマルチプラットフォームとは異なり、専用データベースの利用が前提です。このデータベースの構造が既存のものと異なるため、従来のシステム用に開発されたソフトウエアの利用はできません。しかも、データベース環境の移行中は新旧2種のデータベース保守を余儀なくされますから、維持管理の作業量が激増。自ずと大規模なシステム移行となり、期間や稼働工数は他社のERP製品への移行と同等視されています。
システム移行に携わるエンジニアの人材不足という逆風もあります。SAP ERPは大企業を中心に、グループ全体のIT基盤として導入されているケースが多々あります。S/4HANAへの移行プロジェクトが一定期間に集中することで、その担い手たるエンジニアが大幅に不足しているのです。前述したように、導入プロジェクト経験者が定年退職しているユーザー企業も多く、この種の大規模プロジェクトの知見を持つ人材に乏しい事情があります。
② 現行のSAP製品を使い続ける
2027年に保守期限が終了するとはいえ、対象となるのはセキュリティプログラムやデザイン・機能の更新、システム品質改善などを含む「メインストリームサポート」です。以降は自動的に「延長サポート」期間に切り替わり、デザインや機能の更新、システム品質改善は行なわれなくなる一方、セキュリティプログラムの更新は継続されます。現行のSAP ERPが使えなくなったり、セキュリティ面でのリスクが劇的に高まったりするわけではないのです。ただし、人事や会計など法規制対応が頻繁な領域では、メインストリームサポートは必須とされています。
保守サービスに関しても、サポート専業のベンダーによる第三者保守サービスを利用する方法があります。最大のメリットは料金の安さ。このサービスを活用することで、保守料金を下げられる可能性もあります。
とはいえ、前述したように現行のSAP ERPにはリアルタイム性やビッグデータの処理に懸念があることを忘れてはなりません。つまり「2025年の崖」を乗り越えることは難しい選択肢です。
③ ほかのERP製品への移行
現行のSAP ERPが限界を迎えつつある中では、ほかのERPへの移行を検討することは十分に現実的な選択です。SAP以外にも、現在では多くの優れたERPが存在しています。何よりもゼロからシステムを再構築できる点、最新の技術を利用できる点は最大のメリットでしょう。
むろんコストと時間はかかり、データの移行量も膨大になりますが、それはS/4HANAへの移行にもいえること。DXを実現して「2025年の崖」というリスクを乗り越えるには、いずれにせよ新たなERPへの移行が求められます。
4:まとめ
前述した通り、SAP社の「2025年問題」は「2027年問題」に先延ばしされていますが、度重なる延長ですから、これ以上、延長の期待はできません。しかも、「2025年の崖」を乗り越えなければ企業は存続の危機に瀕してしまう可能性もあります。ERPの刷新という一大プロジェクトにおいて、2年は「わずか」といってもいい短期間。一日でも早くシステムを刷新すれば、リソース的なアドバンテージが劇的に高まることは述べるまでもありません。
2025年~2027年に起きる一連の問題。ならばこれを、企業の根幹を担うERP=統合基幹業務システムを抜本的に見直す好機と捉えてはいかがでしょうか。まずは自社の業務を全面的に見直して、形骸化した業務や大きく変貌を遂げた業務、効率の悪い業務などを抽出し、改善を検討した上で、次世代で運用させる最適なERPを選択する――。滅多に訪れない機会ともいえるのです。
純国産のERPであるからこそ、日本企業の商習慣を熟知。その上で製造業、商社・卸売業や情報サービス業など、さまざまな業種業界に特化したソリューションを提供する進化系ERP「GRANDIT」。「RPA」「IoT」といった最新テクノロジーとも調和し、周辺システムとの連携もスムーズです。「2025年の崖」「2027年問題」といった課題を機に新たなERPを検討されるなら、GRANDITは有力な選択肢になり得るに違いありません。
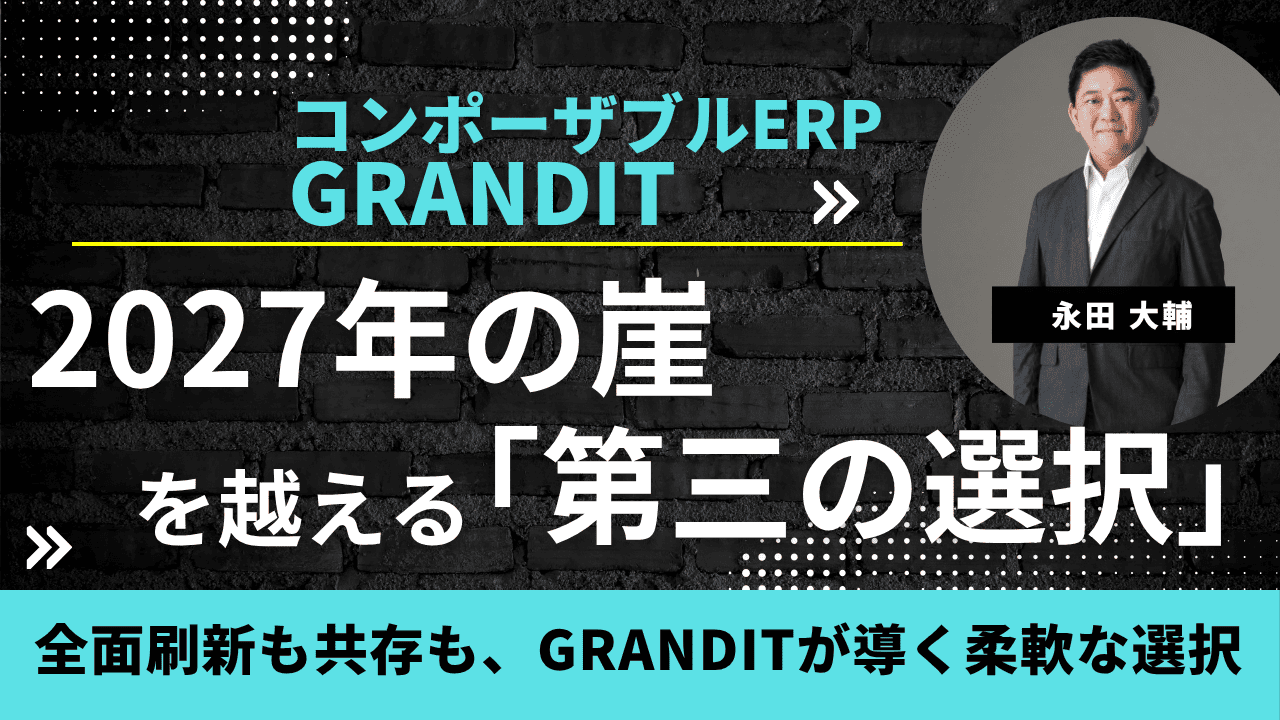
2027年の崖を越える「第三の選択」
2027年問題に備え、S/4HANAへの移行に頭を悩ませていませんか?高額な維持コストやブラックボックス化したアドオンetc...その課題、コンポーザブルERP「GRANDIT」が解決します。
