国産ERPのメリット・デメリット、外資系との違い

国産ERPは、日本企業が開発し、国内の業務や制度に合わせて設計された基幹システムを指します。
グローバルで利用されている外資系ERPと比べると、日本特有の制度や法改正、商習慣などに適合していることから、国産ERPはDX推進の選択肢のひとつとなっています。
本記事では、ERPの選定で迷われている担当者様向けに、国産ERPのメリット・デメリットや外資系との違いについてわかりやすく解説します。
1.国産ERPの特徴とは?
ERP(Enterprise Resource Planning)とは、会計、人事、販売、生産、在庫管理などの企業の基幹業務を一元的に管理できるシステムを指します。
国産ERPは、日本の税制や労働法に対応した設計となっており、日本企業の商習慣や取引先との連携もしやすい特徴を備えています。
国内では、業務に合わせたスクラッチ開発や汎用パッケージのカスタマイズが多くなる傾向があります。その結果、メンテナンスやバージョンアップ時のコスト増大につながるケースも少なくありません。
IPAが公開している「DX実践手引書 ITシステム構築編」においても、業務をシステムに適合させていくアプローチが重要視されていますが、それはERPパッケージ側の適合度が高くなければ実現できません。
そのため、日本市場に特化した国産ERPを採用したシステム刷新は、DX推進における有力な選択肢となっています。
2.国産ERPと外資系ERPの違い
国産ERPと外資系ERPの違いは、「どの企業を主な対象として設計されているか」という点に大きな特徴があります。以下では、両者の違いを主要な観点ごとに比較します。
| 比較項目 | 国産ERP | 外資系ERP |
|---|---|---|
| 設計思想 | 日本企業の商習慣・制度を前提に設計 | グローバル標準で設計 |
| 想定企業規模 | 中堅・中小企業から大企業まで幅広く対応 | 大企業やグローバル展開企業を中心に利用を想定 |
| グローバル対応 | 海外拠点向けの機能は劣る傾向あり | 多言語・多通貨・国際会計基準に強み |
|
カスタマイズ 難易度 |
比較的容易にカスタマイズ可能 | 標準利用が基本で、カスタマイズは高コスト |
| サポート体制 | オペレーター・ドキュメントともに日本語対応 | オペレーターは国内代理店にて日本語対応可能だが、ドキュメントは英語が多い |
外資系ERPはグローバルに展開する大企業を前提としているケースが多く、海外拠点や多通貨・多言語対応に強みがあります。一方で、日本独自の法制度や商習慣には標準機能だけでは十分に対応できないこともあり、追加開発や運用コストの増大につながる場合があります。
国産ERPは、稟議の承認フローや伝票処理など、日本企業で一般的に行われている業務プロセスを前提に設計されているため、現場に浸透しやすく、運用のしやすさに強みを持っています。
そのため、企業がERPを選定する際には、自社の事業規模や海外展開の有無を踏まえ、国産ERPと外資系ERPのどちらがより自社に適しているかを判断することが重要です。
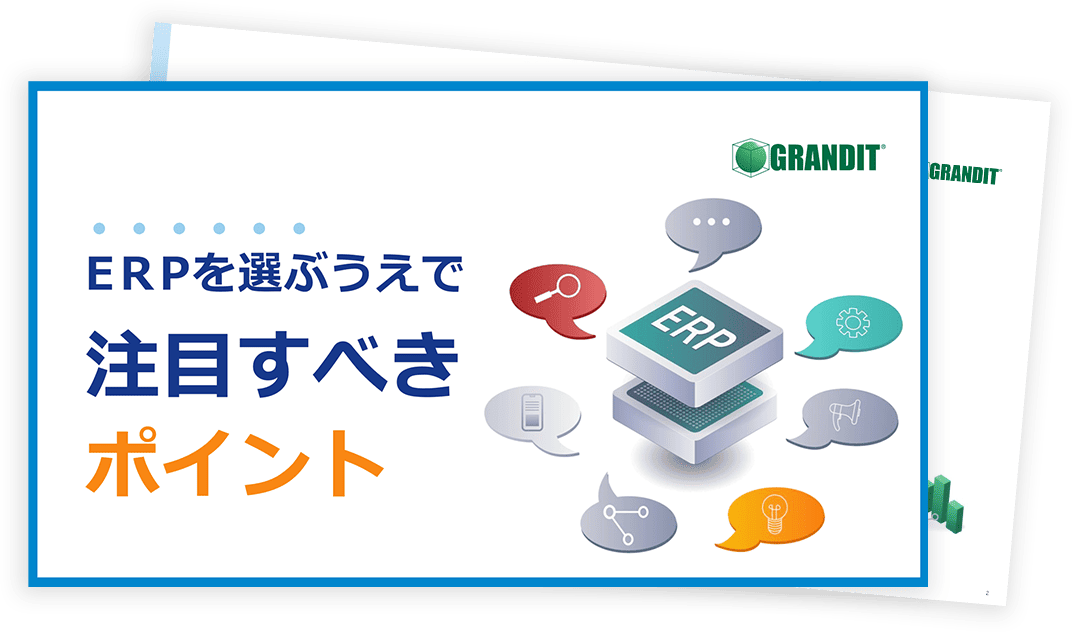
3.国産ERPの5つのメリット
ERPを導入するにあたり、「海外製と国産、どちらが自社に合うのか」と悩む企業は少なくありません。国産ERPには、日本の制度や商習慣に適したメリットが数多く存在します。ここでは、そのなかでも導入検討の判断材料として欠かせない以下の5つのメリットを紹介します。
- 日本独自の制度への対応が早い
- 日本企業の商習慣に適した設計
- 現場で定着しやすい
- 安心してサポートが受けられる
- 国内のデータセンターを利用できる
1.日本独自の制度への対応が早い
国産ERPの大きなメリットは、日本特有の制度変更に素早く対応できることです。消費税やインボイス制度、電子帳簿保存法といった会計・税務関連の制度改正は定期的に行われており、企業は常に最新ルールへの対応を求められます。
国産ERPであれば、こうした改正内容をバージョンアップで迅速に反映でき、安心して運用を続けられます。
対して外資系ERPでは、各国共通の基準を優先して開発されるため、日本独自の制度対応は後手に回ることが少なくありません。
たとえばインボイス制度に伴う適格請求書の発行では、国産ERPなら標準機能としてすぐに対応できますが、外資系ERPでは帳票や登録番号管理のために追加開発やローカライズ設定が必要となり、時間やコストが増えるリスクがあります。
このように、制度改正にスピーディーに対応できる点は、国産ERPが多くの企業に選ばれる理由のひとつです。
2.日本企業の商習慣に適した設計
国産ERPは、日本独自の業務プロセスを前提に設計されている点が大きな特徴です。承認フローや伝票処理、下請法に基づく取引処理といった日本特有の商習慣に標準で対応しており、現場業務に適合しやすい設計になっています。
外資系ERPの場合は、グローバル全体での標準化を重視しているため、日本企業に特有の稟議・多段階承認や下請法対応といった機能は標準では備わっていないケースが少なくありません。そのため、外資系ERPを導入する場合は追加開発や設定変更が必要となり、導入・運用コストの増大につながる可能性があります。
国産ERPであれば、これらの機能を標準で利用できるため、追加開発の負担を抑えながら業務にスムーズに適合させられる点がメリットです。
3.現場で定着しやすい
国産ERPは、国内ユーザーの使いやすさを意識して設計されているため、現場に定着しやすいメリットがあります。画面上のラベルや確認メッセージが自然な日本語で表記されており、専門知識がなくても直感的に操作できます。
これに比べて外資系ERPは、多言語対応しているものの以下のように日本語表記が機械的な翻訳にとどまるケースもあり、分かりにくい表現も見受けられます。
| エラーメッセージ例 | 国産ERP | 外資系ERP (翻訳後のメッセージ) |
|---|---|---|
| 承認フロー | 「承認者が未設定のため、申請を進められません」 |
「Approver Not Found」 (承認者が見つかりません) |
| 重複登録 | 「この伝票はすでに登録されています(重複登録)」 |
「Duplicate Record」 (重複したレコード) |
また、マニュアルやヘルプ資料が英語のみで提供される場合も多く、現場の担当者に展開する際に余分な翻訳作業や教育コストが発生する可能性があるため、注意が必要です。
4.安心してサポートが受けられる
国産ERPは、日本人スタッフによる手厚いサポート体制が整っているため、導入後のトラブルや操作に関する不明点を迅速に解決できるのが強みです。
国内ベンダーが提供するサポートであれば、電話やチャットでリアルタイムに相談でき、現場の業務を止めるリスクを最小限に抑えられます。
一方、海外ベンダーのERPでは日本国内の代理店が対応することが多く、解決できない内容や不明点を海外ベンダーにエスカレーションして回答するため、正確な回答が出るまでに時間がかかることがあります。
利用者向けポータルサイト内から問い合わせチケットを英語で発行し、数日待ってようやく返信が届くといった状況も珍しくありません。
その点、国産ERPであれば国内の担当者が直接対応するため、日本語でのサポートを迅速に受けられる安心感があります。
5.国内のデータセンターを利用できる
国産ERPは、国内のデータセンターで運用されるケースが多く、法制度やセキュリティの観点から安心して利用できるのが特徴です。
国内でデータを管理することで、個人情報保護法や電子帳簿保存法などの法規制にもスムーズに準拠でき、内部統制の強化にもつながります。
外資系ERPでは海外拠点のサーバーを利用する場合があり、データの保管場所やセキュリティ基準に不安が残るケースがあります。企業によっては、自社のセキュリティポリシーに抵触してしまい、導入そのものが難しいと判断される場合もあるでしょう。
そのため、外資系ERPを検討する際には、データ保管場所や法規制への対応状況を事前に確認することが欠かせません。
こうした背景から、国内データセンターでの運用を前提とする国産ERPは、多くの企業にとって導入しやすい選択肢となっています。
4.国産ERPの4つのデメリット・注意点
国産ERPは日本企業に適した利点が多い一方で、導入・運用にあたっては注意すべき点も存在します。
- グローバル対応機能が不足している
- パッケージで標準対応している機能範囲が異なる
- 製品を取り扱う導入パートナー数が少ない場合がある
- 外資系ERPから国産ERPに乗り換える場合はデータ移行に注意
上記の4点について詳しく解説します。
1.グローバル対応機能が不足している
国産ERPは国内業務に強い一方で、海外拠点管理や国際取引を想定した機能には弱さがあります。多通貨・多言語・IFRS(国際会計基準)対応といった要件が、標準機能で対応されていないケースが多いためです。
外資系ERPの場合はこうしたグローバル要件に標準対応しているため、海外展開企業に適しています。したがって、国際的に事業を広げる企業は、国産ERP導入時に機能不足が生じないかを慎重に見極めることが重要です。
2.パッケージで標準対応している機能範囲が異なる
国産と外資系では標準機能で対応されている機能の範囲が異なるため、パッケージ機能の確認とすり合わせが大切です。
外資系は会計・人事に加えサプライチェーン管理(SCM)や製品ライフサイクル管理(PLM)まで提供している場合もあります。一方、国産ERPは主要業務に特化し、不足する機能領域はアライアンス製品やAPI連携で補うケースも少なくありません。
導入前に自社のシステム化範囲を整理し、ERPの標準機能が有する機能や各種アライアンス製品との連携可否を入念に確認しましょう。
3.製品を取り扱う導入パートナー数が少ない場合がある
外資系ERPは大手コンサルタントやSIerが幅広く参入しており、豊富なアドオン開発実績や専門人材を抱えています。そのため、導入後のシステム拡張や運用体制の強化をスムーズに行える環境が整っています。
一方、国産ERPは市場規模が限定的で、対応可能なパートナーやベンダーが少なく、支援体制に制約が生じるケースがあります。継続的なシステム拡張や開発・運用人材の確保を重視する企業は、導入前に慎重な検討が必要です。
4.外資系ERPから国産ERPに乗り換える場合はデータ移行に注意
外資系ERPは独自のデータ構造やマスタ管理を採用しており、ユーザー側では抽出できないデータが存在する場合があります。そのため、外資系ERPから国産ERPへ乗り換える際は、新規導入以上に入念な準備が必要です。
移行時にはベンダーへの作業依頼が必要になるケースも多く、追加費用や調整の手間が発生します。したがって、データ移行を円滑に進めるには、事前に対象データや移行プロセスを綿密に確認しておくことが重要です。
5.自社の状況に合わせて国産ERPを選ぶか判断を
国産ERPは、日本独自の商習慣や法制度に対応した機能、現実的な導入コスト、国内サポートの安心感など、多くのメリットがあります。一方で、グローバル対応の弱さや機能範囲の制約といった注意点も存在するため、導入検討にあたっては、自社に適しているかを入念に検討していきましょう。
【自社が国産ERPにマッチしているか確認するチェックポイント】
- 海外拠点よりも国内事業が中心である
- 法令対応や制度改正時の迅速な対応を重視している
- 初期導入や運用コストを抑えたい
- 稟議の承認や伝票処理など日本特有の商習慣に合わせたい
- 国内ベンダーのサポート体制に安心感を求めている
上記のポイントに複数当てはまる企業にとって、国産ERPは有力な選択肢となるでしょう。自社の状況に応じたERPを慎重に見極めることで、長期的な運用の安定と投資効果を高められます。
自社に合ったERPを選ぶためには、メリットやデメリット、注意点の理解だけでなく、近年のERPの導入トレンドを押さえた検討を進める必要があります。下記のホワイトペーパーでは、ERP選定時に注目しておきたいポイントを解説していますので、ぜひご活用ください。
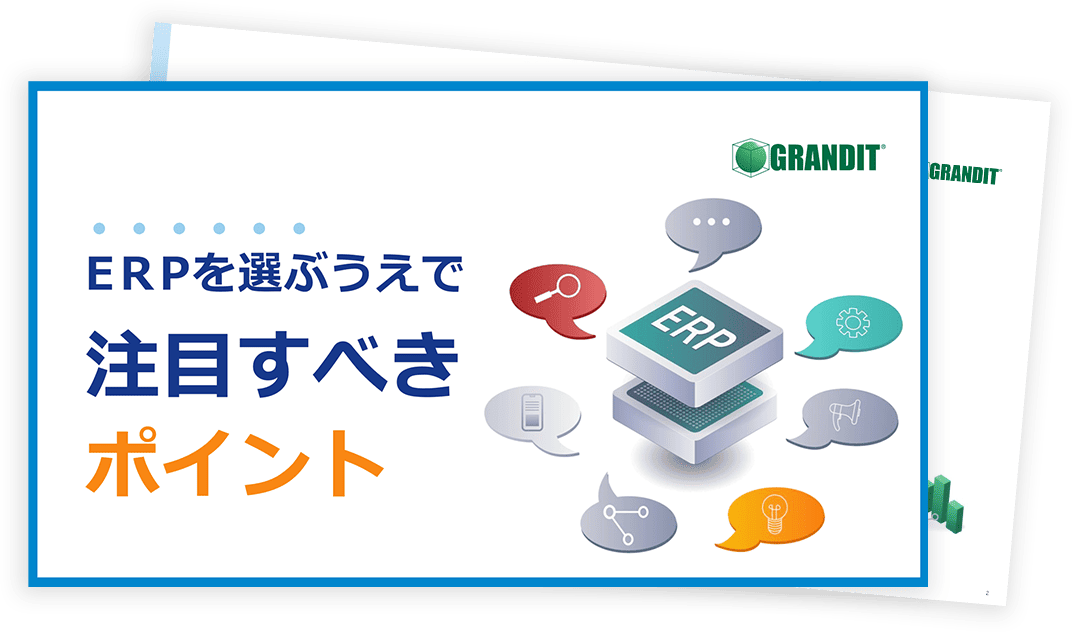
※記事の内容は、制作時点に一般公開されている情報に基づいています。また、記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
