ペーパーレス化はなぜ必要?メリットや推進のポイント、成功事例を紹介
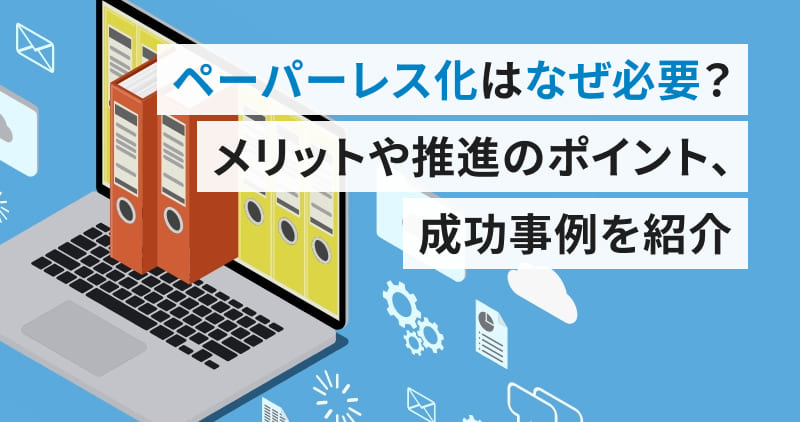
本記事のまとめ
- ペーパーレス化とは、電子化によって紙の使用をなくすこと
- 企業の業務レベル・経営レベルの双方にメリットをもたらす
- ペーパーレス化は「目的策定」や「ツール選定」「スケジュール策定」など正しいステップで実施する必要がある
- 官民学において、ペーパーレス化の成功事例が存在する
近年では、テレワーク対応や業務効率化を図る取り組みとして「ペーパーレス化」が注目されています。本記事では、ペーパーレス化のメリット・デメリットや実施方法、成功事例について紹介していきます。
目次
1. ペーパーレス化とは
ペーパーレス化とは、電子化によってデータを保存・活用して、紙の使用をなくすことを指します。ペーパーレス化した書類や文書は、ネット上のクラウドに保存される場合が多いです。ペーパーレス化を実施することで、「業務効率化」や「コスト削減」などさまざまなメリットを享受できます。
2. ペーパーレス化のメリット(業務面)
ペーパーレス化は、業務面と経営面の双方にメリットがあります。まずは、業務面でのメリットについて見ていきましょう。
コスト削減
ペーパーレスに対応できれば、大幅なコストカットが見込めます。具体的には、「印刷コスト」や「人件費」の削減が可能です。
「印刷コスト」とは、プリンターや紙、インクに関わるコストです。モノクロ印刷1枚あたりのコストが2〜3円程度であるため、1日3,000枚印刷をすれば6,000〜9,000円、年間200日だとすると80万〜120万円かかる計算になります。ペーパーレス化を推進するだけで、これだけのコストをカットできます。また、「人件費」は、印刷業務やホチキス止め、配布作業などにかかる費用のことです。たとえば、これらの業務に1人1日10分かかっているとすると、245日勤務の会社の場合、約40時間分の人件費を削減できます。数百人レベルの会社であれば、更に大幅な人件費の削減が可能となるでしょう。
業務効率化
紙ベースで行っていた仕事をオンライン上ですることにより、大幅な業務効率化を実現できます。たとえばペーパーレス化によって、稟議書や決済書に判子をもらうために必要な一連の作業(会議や対面で会う機会など)が不要となります。
さらに、物理的な紙を業務に介さないことにより、出勤の必要性が低くなるため、出勤や移動時間のカットにもつながり、効率的に業務を進められるでしょう。
セキュリティ向上
ペーパーレス化は、情報セキュリティの向上にもつながります。重要な情報を紙の資料で保管していると、紛失や盗難などのリスクが高まります。加えて、金庫に保管するなど、物理的なセキュリティ対策が必要です。
ペーパーレス化によってデータをクラウド上に保存すれば、盗難や紛失のリスクが軽減するほか、物理的な保管場所の確保も必要ありません。
3. ペーパーレス化のメリット(経営面)
ペーパーレス化は業務面だけではなく、経営面においても多くのメリットがあります。経営面でのメリットを3つ紹介します。
多様な働き方に対応可能
物理的な紙を使って業務を行う場合、判子を押したり文書をファイリングしたりする作業が必要となるため、会社に出勤しなければなりません。
一方でペーパーレス化を推進すれば、働く場所の制約がほぼなくなり、リモートワークをはじめとした多様な働き方に対応できるようになります。
デジタル社会から取り残されない
利益を出し続けている大企業の多くは、すでにペーパーレス化を進めています。たとえば、日本の大手飲料メーカーでは「PPLP(ペーパーレスプロジェクト)」を発足させ、約10万時間分の紙を扱う業務を削減しています。
その他にも、世界中の大企業では紙を無くす流れがあります。こういった時代の流れのなかペーパーレス化の推進は、「時代に取り残されていない」と企業イメージの向上につながります。
環境への配慮による企業イメージの向上
ペーパーレス化の推進により「環境に配慮している」姿勢を市場に示すことができ、企業イメージの向上に貢献できます。SDGsでも「つくる責任、使う責任」というゴールがあり、世界中の大企業がこの目標に沿ってペーパーレスを進めています。紙資源を使わずに環境に配慮した取り組みは、社会的責任のひとつといえるでしょう。
4. ペーパーレス化のデメリット
上記のように、ペーパーレスには業務面と経営面の両方にメリットがあります。一方で、ペーパーレス化にはいくつかのデメリットもあり、導入の際は注意が必要です。正しい手順で実施することでデメリットを解消できる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
業務の変更が発生する
ペーパーレス化を実施すると、既存の業務内容に大きな変更が発生する可能性があります。たとえば、今まで紙で稟議書や企画書を決済していた企業がペーパーレスを実施すると、かかる工数や必要な作業がすべて変わってきます。
中小企業・成長企業であれば影響範囲は限られますが、関係するステークホルダーが多い大企業や公的な機関の場合は、影響は非常に大きくなるでしょう。業務変更に関しても上層部の認可が必要となる場合があり、影響範囲が大きいほど大掛かりな作業となるおそれがあります。
ITに不慣れな社員には不便な点がある
ペーパーレス化を実施すると、PCやタブレットなどのデバイス上で作業を行うことになります。IT機器に日常的に触れている社員には問題はありませんが、そうでない社員の場合は、IT機器に慣れることから始めなければなりません。それまでIT機器をほとんど使っていなかった業界や会社では、別途研修を設ける必要性も出てくるでしょう。研修にかかる工数の発生や、慣れるまでの不便さは、ペーパーレス化のデメリットといえます。
すべての紙をペーパーレスにすることはできないため、管理が煩雑になりやすい
管理が煩雑になるおそれがあることもペーパーレス化の注意点のひとつです。ペーパーレス化を実施したとしても、すべての書類をデジタル上で保管できるわけではありません。その一例が、不動産業界で用いられる書類です。令和4年5月以前まで、不動産の重要事項説明書は電子保管が認められていませんでした。不動産業界のような、電子保管ができない契約書類を取り扱う業界でペーパーレス化を実行すると、電子データと物理的な紙が混在することになります。その結果、内容の整合性を取る業務が新たに発生したり、管理業務が煩雑になったりすることが予想されます。
5. ペーパーレス化の実施方法
メリットを最大化しつつ、リスクを軽減してペーパーレス化を実施するためには、以下のステップに沿って進めるのが効果的です。
ステップ1:目的を明確にする
まずは、ペーパーレスを実行する目的を明確にしましょう。業務効率化やコスト削減、リモートワークへの対応など、企業によってペーパーレス化の目的はさまざまです。目標を定めずにペーパーレス化を進めてしまうと、メリットを最大限に活かすことができず、中途半端になってしまうおそれがあります。
例えば、多くの企業が導入しているからという理由でなんとなくペーパーレス化を実施してしまうと、どの業務がペーパーレス化によって効率化できるかわからず、業務効率が上がらない業務をペーパーレス化してしまうリスクが高まります。ペーパーレス化によってどのような効果を得たいのかをしっかりと検討しましょう。
ステップ2:対象となる書類を決める
目的が明確になったら、ペーパーレスの対象となる書類を選定していきます。たとえば「業務効率化」を目的としてペーパーレス化を実施するのであれば、紙を使った業務で多くの工数を費やしている業務(経理部門の領収書処理など)を洗い出します。
また「経費削減」が目的であれば、印刷をする紙の数が多い業務(営業部門の営業用資料など)を洗い出していきましょう。
ステップ3:対象となる書類をペーパーレスにするツールを選定
次に、ペーパーレス化をするツールを決定していきます。さまざまなペーパーレスのツールが存在しているため、対象とする書類や業務・業界に合わせて最適なツールを選定しましょう。たとえば、経理部門の領収書処理をペーパーレスにするのであれば、経理業務に特化したソフトを選定します。
ステップ4:スケジュールを策定
ツールを選定した後は、ソフトを導入していくスケジュールを策定しましょう。具体的には、「関係者とのすり合わせ」「業務変更点の理解」「運用上のルールの策定」などを行います。たとえば、経理部門の領収書処理をペーパーレス化するのであれば、領収書に関わる部門へペーパーレス化することを共有し、どのように領収書に関わる業務が変更されるのか、提出する際のルールはどうなるかなどを策定していく必要があります。
ステップ5:ペーパーレス化を実行
ステップ4まで完了したら、ペーパーレス化を実施していきます。ペーパーレス化を実施するうえでは、注意点が2つあります。
1つ目が「ペーパーレス化実施のスケジュールの周知」です。ペーパーレス化によって既存業務に大きな変更が生じる可能性があるため、いつからペーパーレスになるのかを関係部署や担当者にしっかりと伝えたうえで実施しなければなりません。
2つ目が「疑問点の相談窓口の設置」です。ペーパーレス化を実施すると、既存業務の多くがクラウド上へ移行します。システムの操作方法のほか、クラウド上での業務の進め方など、多くの質問が出てくるでしょう。それまでIT機器に触れていなかった会社や組織の場合、より多くの疑問点や不明点が生じるかもしれません。このような質問へ迅速に回答できるよう、相談窓口となる担当者や部署を選定する必要があります。
6. ペーパーレス化の成功事例
以下では、民間企業、研究所、大学におけるペーパーレス化の成功事例を紹介します。
例1:ペーパーレス化により、年間54万枚の紙を削減し、2,400時間のファイリング作業をカット
日系の製造業大手では、多くの紙を使う経理業務のペーパーレス化を実施し、年間54万枚の紙の削減と、2,400時間の作業工数の削減に成功しました。印刷を1枚2円と計算しても、年間110万円以上の経費を浮かせることに成功しています。「作業効率」と「コスト削減」を目標として定め、紙が多く発生する業務にペーパーレス化の対象を絞ったことで、大きな成果につなげた事例です。
例2:多くの業務のリモートワークを実現
ある大学では、大学運営業務で多くの会議があり、多くの紙を使用していました。そこで会議に関わる紙を電子化することにより、大幅なコスト削減につなげました。また、ウェブ上で完結できる業務が増えたため、出勤の必要性が下がり、柔軟な働き方を実現しています。ペーパーレス化を実施することで、コスト削減だけではなく、業務効率化や多様な働き方への対応にもつながった成功事例です。
例3:オフィススペースの削減を実現
「オフィススペースの削減」を目標にして、成功した事例もあります。ある研究所では、業務に関わる紙が多く、オフィススペースを圧迫していることが問題となっていました。ペーパーレス化によって、共用キャビネットの69%と個人サイドキャビネットの56%を削減し、文書を保存する箱を810箱廃棄して195箱分を電子化することに成功しました。「物理的なスペースの削減」だけではなく、紙を介する業務の電子化により「業務効率化」も同時に実現したケースです。
まとめ
本記事では、ペーパーレスのメリットやデメリット、導入方法、ペーパーレス化の成功事例について解説しました。ペーパーレス化のメリットは以下のとおりです。
- コストの大幅な削減が見込める
- 業務の効率化が見込める
- 書類紛失がなくなり、セキュリティが向上する
- テレワークをはじめとした多様な働き方への対応が可能
- 時代に取り残されず、新たなビジネスチャンスを獲得できる
- 環境に配慮している姿勢を示すことができ、企業イメージが向上する
ペーパーレス化にはメリットだけではなく、「既存業務が変更される」「管理が煩雑になりやすい」といったデメリットもありますが、正しいステップで実施すればリスク回避につながります。大企業はもちろんのこと、中小・成長企業にも大きなメリットをもたらすペーパーレス化をぜひ実施してはいかがでしょうか。

