システム導入はどのような流れ?中小企業のシステム導入におけるポイントを解説
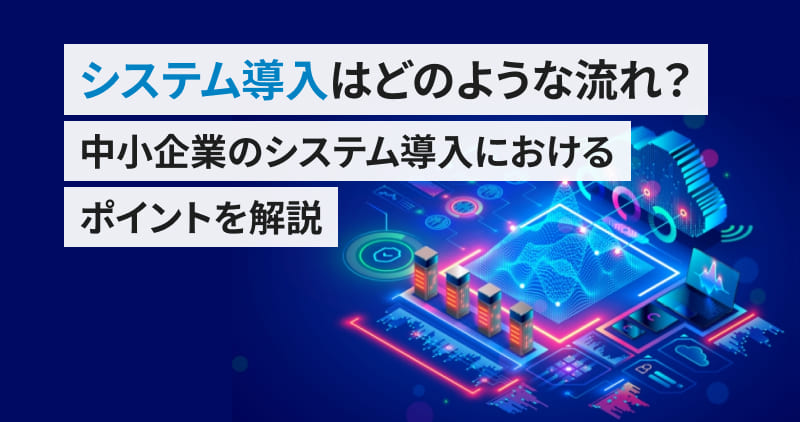
システム導入で業務効率化を図ろう
本記事のまとめ
- システム導入前に導入の目的を整理する
- 外部のシステムベンダーへの導入依頼を検討する
- システムのクラウド化で業務効率化を図る
社内にシステムを導入した経験はあるでしょうか。簡易的な業務用ツールであれば短時間で導入可能ですが、大規模なシステムになると管理や運用方法・コストなどさまざまな観点を考慮しなくてはならず、事前準備や導入に多くの時間を要します。そこで本記事では、中小企業において効率的にシステム導入を行うポイントや、導入の流れを解説します。
目次
1. システム導入のポイント
中小企業はITシステムの導入・利用を進めようとする際、「コスト負担」や「導入の効果が分からない・評価ができない」「従業員がシステムを使いこなせない」など、さまざまな課題を抱えています。そのため、費用対効果や人材面が大きな導入障壁となっているといえます。
ここでは、自社の課題や問題点を洗い出したうえで、システム導入を行う際のヒントとなるポイントを紹介していきます。
システム導入は外部のシステムベンダーに依頼しよう
自社内のみで導入するシステムを検討すると、必要な機能がわからずに業務に適していないシステムを選んでしまうケースが多く、導入後に十分な効果が得られないリスクがあります。
そのため、システム導入実績が多い外部のシステムベンダーに依頼し、必要な仕様について相談しながらシステム導入を進めていくのがおすすめです。
システム導入による効果や評価の仕方を説明してくれる外部の支援者がいると、システムに関して日ごろから相談ができ、導入後に期待した効果が得られやすくなります。
システム導入の費用対効果を考える
システムを導入する際には、費用対効果を考慮することが重要です。かかるコストに見合った効果が得られなければ、システムを導入してもあまり意味がありません。
また、実際にシステムを導入して運用し、費用対効果を算出することで、システム導入が成功したかどうかを判断できます。システムを導入して満足するのではなく、システム導入によって企業にプラス効果を生み出せているのかを確認しましょう。
費用対効果が得られない場合には、原因を検証し、システムを導入する前の運用に戻したり、システムを改修したりするなど、対策方法を考える必要があります。
導入想定システムと既存システムについて比較する
既存システムと新たに導入するシステムをよく比較することも重要です。新しいシステムを導入しても、既存システムのほうが利用しやすかったり、必要な機能がなくなってしまったりして、逆に業務効率が低下するケースがあります。事前に比較して最適なシステムを選択することで、無駄なコストがかかるリスクを回避できるでしょう。
社内の理解を得る
システム導入に関して、事前に社内の理解を得る必要があります。システムを導入すると、新しいシステムに使い慣れるまでに時間がかかるため、今まで利用していたシステムのほうが良いという意見が出る場合もあります。また、システムの機能が不十分と感じた場合、多大なコストをかけて導入しても使用されなくなるケースもあり損失となりかねません。
トラブルを招かないためにも、システム導入をすることで得られるメリットを社内で共有し、理解を得たうえでシステム導入を進めていくことが大切です。
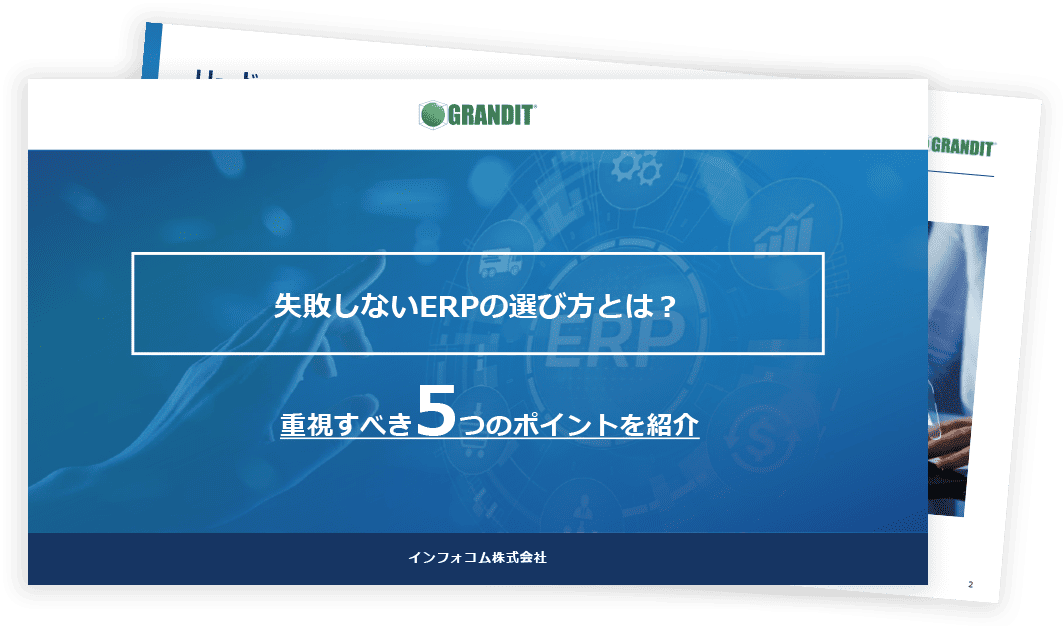
失敗しないERPの選び方とは?重視すべき5つのポイント
近年では大企業だけでなく多くの企業においてもERPを導入するケースが増加しています。ERPの種類と選び方を学んでみませんか?
2. システム導入の流れ
システム導入の流れは、事業規模や業種によってもさまざまですが、ここでは一般的な流れを解説していきます。
現状の課題とシステム導入の目的を整理
まずは、社内の課題を整理し、システム導入の目的を明確にする必要があります。
システム導入が失敗する原因として多いのが、現状の業務や課題を整理しないまま導入したために、後から見つかって作業の手戻りが発生してコストがかさんでしまうことです。現状の業務を洗い出して社内の課題を整理することで、どのような機能が必要か、どの部署で利用しているシステムが必要なのか、システム導入によって課題をどのくらい改善できるのかを検討でき、システム導入をスムーズに進められます。
また企業の発展のためには、新しい製品やサービスを生み出すことも欠かせません。業務の改善に加えて、新しいアイデアやビジネスにつながるようなシステムが理想といえるでしょう。
システムベンダーへ依頼
システム導入の目的が決まったら、システムベンダーへシステムの開発を依頼します。システムベンダーによってシステムの品質やコストは大きく変わってくるため、十分な検討を行い、自社に最適なシステムベンダーを選定しなくてはなりません。複数のシステムベンダーに提案や見積もりを出してもらい、実績やアフターフォローなども比較しましょう。
システムベンダーへ依頼をしたら、要件定義にてどのようなシステムを導入したいのか、どのような機能が必要なのか、スケジュールや予算などを話し合います。システムベンダーとの認識のずれがないよう、決定事項を書面やメールに残しておきましょう。システムベンダーの提案をすべて受け入れるのではなく、企業の業務フローを十分に理解している社員がシステムベンダーと協力して仕様整理や設計を行うことも重要です。
そして、要件定義後もシステムが導入されるまでは、システムベンダーとのコミュニケーションを積極的に取りましょう。意思疎通をしっかりと図ることで、希望に合うシステムを導入できるはずです。
開発管理
システムの開発は基本的にシステムベンダーに任せることになりますが、想定通りのシステムになっているか、スケジュール通り開発が進んでいるかの管理は自社で行う必要があります。管理もすべてシステムベンダーに任せてしまうと、意図したものとはまったく違うシステムになってしまうおそれがあります。そのため可能な限り開発の途中経過をヒアリングしたり、実際に開発が完了した一部機能を試したりして、要望通りのシステム開発が進んでいるかを確認しましょう。
また、システム開発は計画通りにいかないことがほとんどです。例えば、スケジュールに遅延が発生したり、想定していなかった不具合が生じたり、開発に必要な情報が足りていなかったりすることは多々あります。もしこのようなトラブルが発生した場合には、システムベンダーと協力して、早急に原因の追究と解決方法を考える必要があります。
システムのUAT、リリース
システムの開発が完了したら、次はUATです。UATとは、ユーザー受け入れテストのことです。実際にシステムを導入し運用していくユーザーが、システムを利用することで依頼内容と照らし合わせ、目的や意図通りにシステム開発ができているかを確認します。確認の際には、実際にシステムを使用して運用する担当者が、問題なくシステムを運用できること、業務要件とシステム導入の目的が満たされており会社の課題を解決できるシステムとなっていることを確認する必要があります。
そして、UATが問題なく完了すればいよいよリリースとなります。しかし、リリースした後も安心はできません。システムリリース直後には不具合が発生しやすく、想定通りのシステム動作をしないことも多いです。想定通りの動作ではない場合、障害の発生やステークホルダーへの影響もあり得るため、システムベンダーとともにシステムの改修を行わなくてはなりません。
また、リリース直後はシステムが正常動作していても、数ヶ月後に不具合が発生することもあります。そのため、システムベンダーにシステム導入を依頼する段階で、リリース後はいつまで保守対応を行ってもらえるかを交渉するべきです。
システム運用とサポート
システムを運用していくうえで、システムの使い方に慣れていない社員がいればサポートをする必要があります。多くのコストをかけて導入したシステムでも、社内で定着しなければ意味がありません。
実際のシステムの利用方法や運用手順をまとめた手順書を作成して、社内で共有しましょう。システム利用者は、システムに慣れるまでは手順書通りに進めていけばよくなり、スムーズに業務を行えます。また、全社員が同じ手順で業務を遂行できるため、作業漏れが発生するリスクを軽減できます。さらに、一度手順書を作成しておくことで、業務の属人化を防ぐほか、新入社員への業務引き継ぎコストの軽減にもつながります。
大規模なシステムを導入した場合は、手順書に加えて、システムに関する研修も設けるべきです。大規模なシステムは多くの機能が搭載されているため、手順書だけでは理解しづらく、システムが定着しないケースもあります。そのため、研修の時間を設けてシステムの利用方法を社員に詳しく解説して、システムの定着化を図りましょう。
システム導入における効果の確認
業務効率化やコスト削減など、システムを導入して得られた効果を確認しましょう。効果を測定することで、システム導入が成功したかどうか、費用対効果はどれくらいであったかがわかり、業務の改善につながります。また、新しいアイデアやビジネスが生まれる可能性もあるため、効果測定は一度で終わらせるのではなく、何度か実施することがおすすめです。
効果測定の結果、システム導入の効果がないと判断できれば、システムの廃止や改修を検討しなくてはなりません。システムの稼働にはランニングコストがかかるため、効果が見込めないようであれば早急に対策を考える必要があります。
3. システムのクラウド化
システムのクラウド化には多くのメリットがあることから、採用する企業が増えています。特徴やメリットを理解して、前向きにシステムのクラウド化を検討しましょう。
クラウドとは
ネットワーク経由でユーザーにサービスを提供するものです。物理的なサーバーやインフラ、ソフトウェアなどが不要で、インターネット環境があればサービスを利用できます。
クラウドには、主にソフトウェアを提供するサービスのSaaS(Software as a Service)、開発環境を提供するサービスのPaaS(Platform as a Service)、インフラを提供するサービスのIaaS (Infrastructure as a Service)があります。
システムのクラウド化のメリット
メリット1. 物理的サーバーを用意する必要がなくなる
物理的なサーバーを使用する場合、サーバーを用意する導入コストと、サーバーを設置するスペースが必要となります。また、ハードウェアの故障が発生した際の修理費用のほか、定期的なメンテナンスや運用・監視のための人的コストも必要です。
クラウドサーバーでは、月額の利用料はかかりますが、導入コストやメンテナンスにかかる技術者の常駐も不要となるため、コストが削減できる可能性は高いです。
メリット2. ネットワークに接続できる場所であればどこからでもアクセス可能
PCやスマートフォン・タブレットなど、インターネットに接続できる端末であれば、世界中どこにいてもクラウドにアクセスして業務を行うことが可能です。離れた場所にいるチームメンバーともクラウド内で共同作業でき、業務の効率化につながります。
メリット3. 容量や機能の拡張が容易となる
オンプレミスで容量や機能を拡張する場合、新たにHDDを増設したり、ソフトウェアをインストールしたりしなければならず、多くの時間を要します。一方でクラウドであれば、サービスの契約内容を変更するだけですぐに容量や機能の拡張が可能です。アクセスやデータ量が増加し拡張が必要なときはリソースを拡張し、不要な月は契約を元に戻すことにより、月額の課金額を最適化できます。
メリット4. バックアップが簡単
多くのクラウドサービスには、バックアップ機能が標準搭載しており、一度設定をしておけば定期的にバックアップの取得が可能です。万が一データが消えてしまっても、すぐに最新の状態にリカバリーできます。
また、クラウドであればクラウドベンダーが管理する外部のサーバーにデータを保存するため、地震・火事・水害など災害に遭った際にも早急にデータを復旧でき、重要なデータを守ることが可能となります。
メリット5. セキュリティが強固である
自らシステムを構築する場合には、データの消失や情報漏洩を防ぐために、セキュリティについて考慮しなければなりません。しかし、強固なセキュリティ体制を構築するには、専門的な知識や技術が必要となります。また日々高度化するサイバー攻撃に対して、自社の要員だけで対処し続けることは困難ともいえます。
クラウドサービスであれば、高度なセキュリティ対策をベンダー側で実施していることが多いため、自社で環境を構築する場合と比べて時間やコストをかけずに高いセキュリティを構築・維持できます。
メリット6. 運用作業の負担を軽減できる
オンプレミス環境では、ハードウェアの故障などが発生した場合、自社で運用要員を用意し対処しなければなりません。また、アップデートやメンテナンスを行うために、社内で保守体制を保持する必要もあります。
システムをクラウド化すれば、ハードウェアに関する運用をクラウドサービス事業者側に任せられるため、運用工数を大幅に削減できます。また、SaaSであれば、アプリケーションもクラウド事業者側が運用をカバーしてくれるため、よりユーザーの負担は少なくなります。その結果、運用要員に別の業務を割り振ることができるため、生産性の向上につながるでしょう。
まとめ
システム導入には、準備から導入後のフォローまでさまざまなステップがあり、多くの時間とコストがかかります。しかし、システム導入に成功すれば、業務の大幅な改善やコスト削減につながるため、積極的に実施しましょう。社内でシステム導入におけるノウハウや知識が不足している場合は、システム導入実績の多い外部のシステムベンダーに依頼することがおすすめです。コストは発生しますが、豊富な経験やノウハウをもとに、最適な提案や導入を行ってもらえます。
情報化社会となったいま、業務をシステム化して業務効率化に成功している企業が競争優位性を獲得できることは間違いありません。いち早くシステムを導入できるように動き出しましょう。
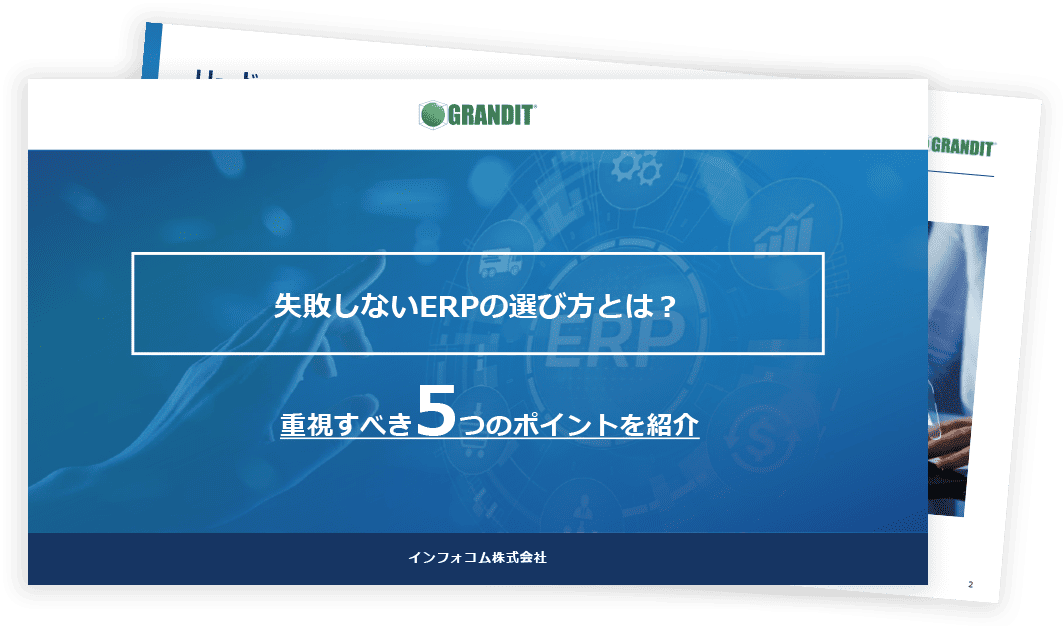
失敗しないERPの選び方とは?重視すべき5つのポイント
近年では大企業だけでなく多くの企業においてもERPを導入するケースが増加しています。ERPの種類と選び方を学んでみませんか?
