デジタル化とは?メリットや推進方法、具体的な事例について解説
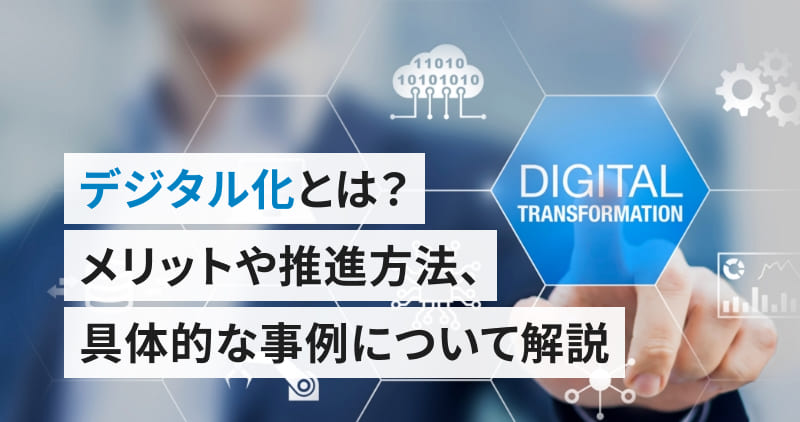
デジタル化は業界や企業規模に関係なく求められている
本記事のまとめ
- デジタル化は業務効率化やコスト削減などさまざまなメリットを享受できるため、多くの企業で導入が進んでいる
- デジタル化を推進する上では、目的を明確化することがポイント
- 小規模で資金が少ない中小企業でもデジタル化の推進は可能
デジタル化は社会全体で推進されており、業務効率化やコスト削減、リモートワークの普及など多方面にわたり効果が確認されています。近年ではクラウド技術の発展などに伴い、中小企業でもデジタル化の導入が活発化し、新しい価値を生み出すことに成功した企業も多く見られます。今後、ビジネスにおいて競合優位性を高めていくには、デジタル化が重要なファクターとなるでしょう。デジタル化を成功させるためには、その目的や対象を明確にする必要があります。また、さまざまな業界でデジタル化が進んでいますが、業界によって進め方やポイントが異なる点にも注意が必要です。本記事では、デジタル化のメリットや推進方法、業界別のポイントについて解説します。
目次
1. デジタル化とは?なぜ求められる?
近年では、社会全体でデジタル化が活発化しています。オンラインでの買い物や授業、新聞や雑誌のような紙媒体の電子化など、私たちが日常で利用するあらゆるもののデジタル化が進んでいます。そして、業界や規模に関わらず多くの企業も、デジタル化の実施に積極的です。リモートワークの普及、ペーパーレス化によるコスト削減、単純作業の自動化による業務効率化など多くのメリットがあるデジタル化は、いまやビジネスを成功させる上で必要不可欠な取り組みといえるでしょう。
デジタル化とは?
デジタル化は、社会や企業にとってメリットが非常に大きいソリューションです。もともとは紙のようなアナログで管理していた情報を、デジタル化してデータへ変換することで、私たちの日常生活はますます便利になってきています。また、企業もデジタル技術を活用し、従来の業務を効率化させたり、ビジネスモデルを大きく変化させて新しい価値を生み出したりすることに成功しています。そして、デジタル化は行政が強く力を入れている分野でもあります。経済産業省は「デジタルガバナンス・コード」をホームページで公開し、デジタル化の加速を図っています。デジタルガバナンス・コードとは、主に以下の内容について情報をまとめた経営者向けの提言です。
- デジタル人材の育成や確保
- デジタル化活用の行動指針
- デジタル化の重要性
(参考:https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913002/20220913002.html)。
デジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションの違いとは?
- デジタイゼーション
アナログの情報をデジタル化したものです。情報をデジタル化することで、保存や加工などがしやすくなるメリットがあります。デジタルカメラがその一例です。アナログのカメラはフィルムに保存するため、写真を現像する必要があり、加工も基本的にはできません。一方デジタルカメラであれば、写真の背景色の調整や、撮影の際に映り込んでしまった不要なものの削除など、その場で写真を確認して加工することが可能です。
- デジタライゼーション
プロセスをデジタル化することです。例えば、シェアリングサービスが代表的です。現代ではプロセスをデジタル化する技術により、車や自転車、傘といった「モノ」を他の人と共有する形で使うことが可能となりました。
- デジタルトランスフォーメーション
「DX」と呼ばれているもので、デジタル化技術を利用して経営戦略、業界、業務などを再構築し、従来の仕組みを抜本的に変えることを指します。デジタル技術は、日常生活や企業のビジネスモデルなどを大きく変え、まったく新しい価値を生み出すことが可能です。
デジタル化のメリット
デジタル化は、業務の効率化や、パンデミックによりニーズが高まっているリモートワークの実現など、企業にとって非常に大きなメリットがあります。業務効率化の観点では、従来の業務を見直し、そのすべてまたは一部を自動化することが可能です。例えば、会社の各部署間のデータを連携させ、単純作業を自動化することで、マーケティング活動に新たな付加価値を生み出せる可能性があるでしょう。
また以下のように、顧客のアクションに合わせてリアルタイムで適切なコミュニケーションを取れるようになり、製品やサービスに新しい価値を生み出すことが可能となります。
- クライアントがECサイトで商品を購入した際、関連する商品のプロモーションを行うメールを送信する
- 商品を購入してから一定の期間時間がたった際、メールでアンケートへの回答を依頼する形で商品に対する不満などがないか確認する
- クライアントが商品に関する質問のメールを送った際、後ほど担当者から回答するという一旦の連絡やQ&Aサイトの案内メールを出す
このように、デジタル化の導入は従来の仕組みをまったく新しいものへ進化させる可能性を秘めています。今後の社会でビジネスを推進していく上で、必要不可欠な要素となるでしょう。
2. デジタル化のポイントと進め方
デジタル化を推進する際の主なポイントを解説します。正しい進め方と注意点をしっかりと理解しておくことで、失敗のリスクを軽減できるでしょう。
ポイント1.目的を明確化する
デジタル化を進める上でもっとも重要なポイントは「目的を明確にすること」です。企業が自社の業務やサービスなどをデジタル化する場合、その目的は企業によって異なります。たとえば、業務の効率化や生産性の向上、コストの削減、リモートワークの導入などが考えられます。「なんとなく便利になりそうだから」r「必要かどうかわからないけれどライバル企業が導入しているから」といった曖昧な目的でデジタル化を進めるのはおすすめできません。費用がかさむだけで、デジタル化のメリットを最大限に発揮できずに失敗してしまう場合がほとんどです。まずは「なぜ自社でデジタル化を推進するのか」を関係者間で認識合わせした上で、目的を明確化させましょう。
ポイント2.優先順位付けを行う
優先順位をつけてデジタル化を推進していくことも、デジタル化を成功させるために有効な手段です。自社のビジネスで何をデジタル化すべきかを検討すると、緊急度や優先度が高いものと、そこまでではないものを分類できます。仮にデジタル化すべき対象が複数あった場合でも、経営方針などに従い、優先順位をつけて一つずつ進めていくことで、失敗のリスクを大幅に抑えられます。
ポイント3.PoCなど検証を行っておく
デジタル化は既存の仕組みを抜本的に変えるため、PoCの実施も有効です。PoCとは「Proof of Concept」の略で、新しい技術や仕組みを導入する際、その効果が期待通りのものであるかどうかを検証することです。従来にはない試みを導入する際は、実施しておくことが推奨されます。
ポイント4.スモールスタート
実際にプロジェクトを進めていくと、あらかじめ決めた予算やスケジュールの範囲内では対応できなくなる場合があります。プロジェクトを中止するとリスクや損害を招いてしまうため、事前に対策を打っておくことが推奨されます。その有効な手段の一つが、プロジェクトのスコープを小さく設定することです。プロジェクトが大規模なものであればあるほど、後で変更や中止するのが難しくなります。特に実績がないものである場合、スモールスタートで一つずつ対応する形で進め、個別に期待した効果が得られているかどうかを評価しながら推進していくとよいでしょう。そうすることで、万が一想定通りの効果が得られなかった場合も、損害を最小限に抑えられます。
ポイント5.スコープは都度入念に確認する
デジタル化の対象は、進めていく過程でもその詳細を入念に確認していく必要があります。検討段階でスコープを決定している場合でも、詳細部分は決め切れていないことがあります。その際、開発チームだけでスコープを判断してしまい、実際にシステム利用する業務チームが想定していたものが実現できないという事態に陥ることはよくあります。
ポイント6.過去に実績がある手段を利用する
類似のデジタル化プロジェクトが過去にあれば、その実績を参考にすることも有効です。デジタル化の対象となるものの実績だけではなく、実装を依頼するシステム開発ベンダの実績も参考になります。例えば「リモートワーク導入のためのデジタル化」を検討する場合、その手段や実績のあるベンダを調査し、成功実績があるものを選定します。
デジタル化の進め方
デジタル化は従来のものを抜本的に改革することが多いため、以下のような失敗を招くリスクも高いです。
- 思った通りの成果が得られなかった
- スケジュールと予算をオーバーしてしまった
- 技術的な問題に直面しそもそもデジタル化することができなかった
そのため、デジタル化を進める上では、入念な事前確認と計画が欠かせません。もちろんプロジェクトを進めていく過程で、想定外の問題が発生するケースは多く、失敗のリスクをゼロにすることは極めて困難です。しかし、進め方を工夫することで、失敗のリスクを軽減できる可能性はあります。「デジタル化推進のポイント」をしっかりと理解し、準備を徹底することが重要です。
3. 業界別にみるデジタル化
デジタル化の取り組み状況は業界ごとに大きな差があります。総務省の情報通信白書によると、情報通信業が先行しており、次いで製造業、金融業などで取り組みが進んでいます。ここでは業界別にみるデジタル化の特徴を整理していきます。
業界ごとにデジタル化の特徴が異なる背景
業界や企業により、デジタル化の主な目的や対象となるプロセスは異なります。
従来の業務プロセスを変えることは容易ではなく、既存を重視する傾向がある業界ではデジタル化の促進がうまく進まないケースも少なくありません。
しかし、どの業界であっても、デジタル化の活用はこれまでにない新規ビジネスを構築できる可能性を秘めています。デジタル技術を活用し、新しいビジネスモデルを展開する形で、大手企業よりも価値の高い製品やサービスを展開するベンチャー企業も出てきています。そのため、どの業界・どの企業であっても、デジタル化の検討・導入を進めていくことは、今後市場価値を高めていく上で重要といえるでしょう。
製造業
製造業ではデジタル化を活用することで、主に以下の効果が期待できます。
- ヒューマンエラーの防止
- 生産性の向上
- 製品の品質改善
IoTの導入が活発化しており、従来は人が行っていた作業をロボットが対応する形で製造プロセスが改善されてきています。
金融業
金融業では、キャッシュレス決済、入出金・振込などサービスのオンラインでの利用、投資・資産運用のための分析ツールやロボアドバイザーなど、デジタル化を利用したさまざまなサービスが開発されています。「FinTech(フィンテック)」と呼ばれる金融サービスにIT技術を融合する動きが活発になっており、デジタル技術によって従来と比べて大きく仕組みが変わりました。
物流業
物流業では、SCM(Supply Chain Management)という原材料を調達し生産した製品を顧客に届けるまでの仕組みを構築できるITシステムの開発が進んでいます。ピッキングや配送の自動化、在庫情報の管理、最適な配送ルートの探索など、デジタル化技術によって高度な業務効率化が推進されています。
小売業
小売業では、顧客データを活用したサービス、ロボットの遠隔操作による品出しの自動化、スマートショッピングカートの導入による会計プロセスの効率化、などの仕組みが構築されています。コスト削減だけではなく、人手不足を解消する効果も期待できます。
教育業
教育業では、学生一人ひとりの学習データを蓄積して活用する形で、パーソナライズ化された学習方法の提供が進んでいます。リモート授業の環境も整備が進んでおり、場所を問わず学習することが可能です。そして、テストの採点業務の自動化などもできるため、教育提供側の業務効率化も進んでいます。
4. 中小企業のデジタル化
現代では技術の発展により、企業の規模に関係なくデジタル化を推進できます。中小企業やスタートアップ企業など規模が小さい場合であっても、デジタル化の推進は可能です。ここでは、中小企業のデジタル化について紹介していきます。
中小企業におけるデジタル化
一昔前までは、デジタル化を含むシステムの導入全般は、大企業でなければ難しいものでした。オンプレミスではサーバーなどインフラの導入や保守は自社で行う必要があり、予算の少ない小規模な企業では高額な初期・運用コストが障壁となっていたためです。
しかし、現代ではクラウドサービスの発達と普及により、デジタル化推進のハードルはかなり下がっています。クラウドサービスであれば、インフラはクラウド事業者が提供しているものを共有するため、従来のオンプレミスの場合と比べると初期費用を大幅に抑えることが可能です。また、インフラの導入や保守運用は、クラウド事業者側が対応してくれる場合が多く、ノウハウや知識がない企業でもデジタル化を導入できます。トラブル対応やメンテナンスを行う担当者を自社でもつ必要もありません。
中小企業のデジタル化の導入事例/ユースケース
すでに数多くの中小企業でデジタル化技術を利用した仕組みが導入されています。中小企業の場合、前述の通り目的に沿ったデジタル化の促進が有効です。
過去の事例を確認すると、中小企業では主に「人手不足の解消」「業務の効率化」「コストの削減」を目的としたデジタル化の導入が多くみられます。
目的別に具体的なデジタル化の導入事例/ユースケースを見ていきましょう。
事例1: 「人手不足の解消」
制御機器を生産するメーカーでは、製造プロセスにIoT端末を導入し、作業員が遠隔地から製造業務の管理・操作ができる仕組みを取り入れ、地方における慢性的な人手不足の解消に成功しました。
事例2: 「業務の効率化」
SaaSの開発や運用などを手掛ける情報通信業の企業では、営業やマーケティング活動を支援する中小企業向けのサービスをリリースしました。導入した企業では、従業員の業務効率化を実現できたほか、SaaSはクラウドサービスで運用されるため運用要員が社内で不要となり、従業員を他の業務に割り振ることが可能となりました。
事例3: 「コストの削減」
機械工具や工事用消耗品の商社では、「在庫が余ってしまう」「予定していたスケジュール通りに納入ができない」などの課題を抱えていました。しかし、デジタル化技術を利用して顧客の需要を分析し、必要なモノを必要な時に届けられる仕組みを構築したことで、コストの大幅な削減に成功しました。
上記の事例からも分かるように、人手不足の解消や業務の効率化などは、少ない人数で今まで以上に生産性を上げようとする試みとして、今後より重要視されるでしょう。日本の生産年齢人口は1990年代より下降しており、特に中小企業では人手不足は深刻な問題となりつつあります。デジタル化はそのような課題を解決する施策として大きな期待が寄せられています。
また、コストを削減することで顧客に対して費用対効果の高いサービスを届けようとする努力も、企業価値を高める上で有効であり、数多くの企業で取り組まれています。
まとめ
デジタル化は企業の規模に関係なく進めていくことが可能で、今後企業がビジネスを推進していく上で不可欠なものです。業界によって程度の差はありますが、基本的にはすべての業界においてビジネスを成長させていくために重要な取り組みといえます。デジタル化関連の技術を詳細に理解し、自社ビジネスに導入できないかの調査および検討を進めていくとよいでしょう。

