2022年1月施行!電子帳簿保存法改正のポイントと対応方法
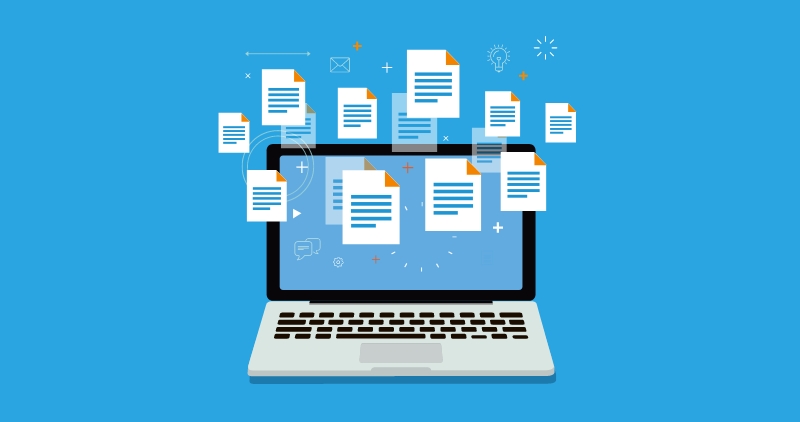
2022年1月施行!電子帳簿保存法改正のポイントと対応方法
本記事のまとめ
- 2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法は、各種保存要件の緩和により企業にとって利用しやすいものとなった
- 電子帳簿保存法に基づき帳簿・書類を電子化することには様々なメリットがある
- 電子化においては、クラウドERPをはじめとしたシステムやツールをうまく利用することが有効
1998年に制定された電子帳簿保存法ですが、煩雑な要件が求められることなどから普及が進まず、帳簿・書類の電子化に取り組む企業はわずかでした。
一方で、2022年1月施行の法改正により帳簿や書類を電子的に保存する際の要件が大幅にされたことから、電子帳簿保存法への注目が集まっています。
そこで本稿では、電子帳簿保存法の概要や改正による主な変更ポイント、必要な対応などについて解説を行います。
目次
1. 電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿・書類について、電子データでの保存を認める法律のことです。各税法では貸借対照表や損益計算書、仕訳帳に代表されるような「帳簿」と、注文書や請求書、契約書等に代表されるような「書類」については、原則紙での保存が義務付けられています。しかしながら、電子帳簿保存法が定める一定の要件を満たせば電子データにて帳簿・書類の保存が可能となります。
電子帳簿保存法における電子データでの保存方法には、大きく以下の3つの区分が存在します。
- 電子帳票等保存
電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存する方法。
例: PCで作成した自社の貸借対照表や損益計算書などの決算関係書類を、そのまま電子データとして保管する。 - スキャナ保存
紙で受領・作成した書類を画像データで保存する方法。
例:取引先が作成し、郵送にて受領した請求書について、スキャンの上、電子データとして保管する。 - 電子取引
電子的に授受した取引データを電子データで保存する。
例:取引先がPCで作成し、メールにて受領した請求書について、そのまま電子データとして保管する。
2. 2022年1月の電子帳簿保存法改正のポイント
1998年に施工された電子帳簿保存法ですが、当初の制度では保存要件が厳しく、段階的に要件の緩和が行われたものの、普及は進みませんでした。そこで、社会のデジタル化も踏まえつつ、経理の電子化を進めるべく保存要件の緩和などを含めた抜本的な法改正が実施され、2022年1月に施行されました。
2022年の電子帳簿保存法改正により、国税関係の帳簿・書類のペーパレス化が大幅に実施しやすくなります。改正による主な変更ポイントは以下の通りです。
事前承認制度の廃止
従来では、電子帳簿保存法が定める「①電子帳票等保存」および「②スキャナ保存」を行うためには、利用開始3か月以上前に所管税務署へ申請を行う必要がありました(事前承認制度)。改正法により、事前承認制度は廃止され、申請は不要となりました。
タイムスタンプ付与期間の延長
従来では、「②スキャナ保存」および「③電子取引」において電子データとして帳簿や書類を保管するためには、データに対してタイムスタンプと呼ばれる作成時刻証明をつける必要がありました。しかしながら、定められた要件に対応したクラウドシステム等を活用することで、タイムスタンプ付与を省略できることになりました。
検索機能要件の緩和
従来は、日付に対する範囲指定や複数項目での絞り込みなど、電子データに対する複雑な検索機能要件が定められていました。法改正により、電子データの必須検索項目が「取引年月日」「取引金額」「取引先名称」のみに限定され、検索要件が緩和されました。
適正事務処理要件の廃止
「②スキャナ保存」において、従来は不正を防止するために書類の受領者以外によるダブルチェックが必要でした(適正事務処理要件)。チェック時には紙の原本を用いる必要があり、負荷が高いものとなっていました。法改正により、適正事務処理要件が廃止され、スキャナ保存が利用しやすくなります。
3. 電子保存の対象となる帳簿・書類
電子帳簿保存法において保管対象となる帳簿・書類は、その種類により「①電子帳票等保存」「②スキャナ保存」「③電子取引」のうちどの方法で扱うかが異なります。
対象となる帳簿・書類以外をそれぞれの方法で保存しても、正しく証跡として利用できませんので、注意が必要です。以下に、それぞれの具体例を紹介します。
- 電子帳票等保存の対象書類 ※1
国税関係帳簿:仕訳帳、総勘定元帳、売掛帳、買掛帳など
決算関係書類:貸借対照表、損益計算書など
自己が作成する書類の写し:見積書、契約書、請求書など - スキャナ保存の対象書類 ※2
取引先から受領した書類:請求書、見積書、納品書、注文書など
自己が作成する書類の写し:見積書、契約書、請求書など - 電子取引の対象書類 ※1
電子取引により取引を行ったもの:インターネット取引、電子メール取引など
※1参考:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 問1 電子取引の制度はどのような内容となっていますか。」より
※2参考:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】 問2 どのような書類がスキャナ保存の対象となりますか。」より
4. 電子帳簿保存法に対応するメリット
以下では、電子帳簿保存法に対応するメリットについて解説します。
書類保管スペースとコストの削減
一つは、保管スペースやコスト面のメリットです。従来は紙で管理していた書類について、電子化することで保管スペースを削減することができます。
税法や会社法などによって、確定申告書類や取引関連書類は「7年」もしくは「10年」保管しなければならないと定められており、会社の規模によってはオフィスに保管スペースを設けたり、倉庫をレンタルしたりする対応をとっているケースもあると思われますが、これらのコストを削減可能です。
また、印刷にかかる紙代やインク代についても削減できるというメリットもあります。
経理業務の効率化
紙で書類を管理している場合、書類を探すのも一苦労です。特に大量に書類を保管している場合は、書類置き場から必要な書類を探すのにはそれなりの時間が必要となります。
電子化により書類を検索できるようにすれば、これらの苦労は不要です。書類を電子化し、名称や日時、分類などの情報を付加することで、検索システムで検索可能となります。これにより、業務効率化につながるでしょう。
さらに近年ではテレワークも一般化しており、オフィスの外からでも書類を探したいというニーズも生じています。紙書類はオフィスにいないと確認できないというデメリットがあり、テレワークが一般化した時代においては不便です。テレワークの推進という観点でも、電子化は有効といえるでしょう。
DX化の一歩として
DXという言葉が浸透し一般化する中で、DXの必要性を認識しつつも、実現できていないという企業は多いのではないでしょうか。
DXのスタートは、いわゆる「デジタイゼーション」と呼ばれる、アナログデータをデジタルデータ化する取り組みから始まるとされています。DXのポイントはデータの活用にあると言われていますが、一方で紙などに記載されたアナログデータはコンピュータで読み取ることができません。そこで、書類を電子化しつつ、後述するOCRなどでテキストデータを読み取り、デジタルデータ化します。紙を電子化する取り組みは、DXの第一歩として有効といえるでしょう。
電子化してデータを活用できるようにすることで、データ分析による競争力強化や生産性の向上など、DXの施策につなげていくことが期待できます。
5. 電子帳簿保存法 改正後の注意点と対応すべきこと
電子帳簿保存法への対応についてはどのような点に注意すべきなのでしょうか。以下では、特に気を付けるべきポイントについて解説します。
電子取引のデータは電子形式での保管が必須に
電子帳簿保存法の改正の多くは容認規程、すなわち実施したい事業者が任意で実施するものです。一方で、電子取引データの電子形式での保管については義務規定、すなわち必須で対応しなければならないものとなります。
具体的には、電子契約やECサイトでの仕入れなど、Web上やメールなどで取引を行った電子取引データについては、紙に出力して保管することが認められず、電子形式での保管が必須です。これまですべての書類を紙に印刷して保管していた企業においては、社内ルールの変更やシステム面の整備など、対応が必要となります。
ただし、本件については2年間の猶予期間が設けられています。2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法ですが、認知度が高まらなかったこともあり、2023年12月31日までは対応が必須となっていません。企業においては、この期間の間に対応を進める必要があるでしょう。
保管要件の確認
電子帳簿保存法に対応して電子化を行うためには、同法が定める保管要件を順守しなければなりません。
例えばスキャナ保存であれば、以下のような要件を順守する必要があります※3。
- スキャンデータの解像度は200dpi以上
- カラー画像での読み取り(赤・緑・青それぞれ 256階調、約1677万色以上)
- 解像度及び階調情報の保存
- 大きさ情報の保存
- バージョン管理の実施
など
これらの要件に対応しないと、法律上電子保管されているものと認められないため注意が必要です。
※3参考:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」 P7
電子データの消失に注意
7年もしくは10年の保管が必要となる帳簿・書類ですが、電子化してPCやシステムで保管する際は、期間中にデータが消失しないように注意する必要があります。PCのハードディスクやSSDに電子データを保管している場合、機器が故障してデータが取り出せなくなるリスクがあります。必ずバックアップデータの取得について考慮するようにしましょう。
クラウドERPをはじめとしたクラウドサービスでは、データのバックアップが自動で行われるサービスも多いです。電子化を行う際は、バックアップに対応しているシステムの利用やバックアップ方法の用意なども含めて検討する必要があります。
6. 電子書類管理の効率化に有効なツール
大量の電子書類をうまく管理していくためには、ツールを活用することで効率化していくことが重要です。以下では、電子書類を管理する上で有効なツールを紹介します。
OCR
上述の通り、電子帳簿保存法の改正により、スキャナ保存要件が緩和されました。スキャナ保存を活用していくうえで検討したいのが、OCRの導入です。
OCRは、紙に記載されているアナログなテキストデータを、デジタルデータに変換することができる仕組みです。通常、紙に記載された文字情報はコンピュータ上では文字として認識できず、単なる画像データとして認識されます。OCRを利用することで、画像に映っている文字情報を、コンピュータも文字として認識できるようになります。
OCRを活用することで、単に書類を電子化するだけではなく、書類の情報を検索したり、データとして蓄積し分析に活用したりできるようになります。特に、電子帳簿保存法の検索要件への対応を容易にするためにも、OCRの活用は有効でしょう。
近年では、AI-OCRと呼ばれるAI技術を活用したOCRも一般化しつつあります。AI-OCRはこれまでのOCRよりも読み取り精度が向上しており、十分実用に耐えうる性能を持っています。
電子帳簿保存システム
電子帳簿保存法に対応した、専用の電子データの保管システムも存在します。これらのシステムでは、タイムスタンプの付与機能や、要件として求められている検索機能を備えています。また、製品によってはスキャン保存制度の要件を満たしたスキャン機能やOCR機能が備わっているケースもあります。
専用のシステムは電子帳簿保存法に対応するためには有効な仕組みではありますが、個別にシステムを導入しなければならずハードルが高い面もあるといえるでしょう。
クラウド型ERP
ERP(Enterprise Resource Planning:企業資源計画)とは、「製造」「販売」「会計」「人事」「物流」などの企業の基幹となる業務を統合し、効率的な業務の実施や情報の一元化を図るためのシステムです。近年では、クラウド上でERPの機能を提供するクラウド型ERPも一般化しました。従来はオンプレミスで導入することが一般的であったERPですが、クラウド型ERPの登場により、短期間かつ低コストで導入できるようになりました。
クラウド型ERPの製品によっては、電子帳簿保存法へ対応するための機能を備えているものもあります。電子帳簿保存法に対応したクラウドERPを活用することで、経理処理と帳簿・書類の電子化を一元的に実施することができるでしょう。
当社では、電子帳簿保存法に対応したクラウドERP「GRANDIT miraimil」を提供しています。GRANDIT miraimilでは関連コンポーネントを利用することでスキャナ保存や電子取引へ対応できます。加えて、自社の業務システムなど、他システムとの連携も可能です。
まとめ
本稿では、電子帳簿保存法の概要や改正による変更ポイント、必要な対応などについて解説しました。電子帳簿保存法で定められた電子化をうまく活用することで、コストメリットや業務の効率化につなげることができます。一方で、電子化を効果的に進めていくためには、OCRやクラウドERPをはじめとしたツールをうまく利用することもポイントとなるといえるでしょう。

