雑所得と事業所得の判断基準の明確化

令和4年度、所得税確定申告(令和5年3月15日提出期限)における、昨年度からの変更点のひとつを今回は御紹介致します。
パブリックコメントの反響の多さから、昨年令和4年夏に話題になった変更点の「雑所得と事業所得の判断基準の明確化」について御紹介したいと思います。
- 「事業所得」と「業務に係る雑所得」の関係
- 原則的な判断基準(事業所得と業務に係る雑所得の区分)
- 具体的な判断基準(事業所得と業務に係る雑所得の区分)
1、「事業所得」と「業務に係る雑所得」の関係
- 当該活動が事業的規模である場合→「事業所得」
- 当該活動が事業的規模でない場合→「業務に係る雑所得」
なお、事業所得の場合、税金計算においての以下の優遇措置があります。
- 青色申告特別控除(10万円~65万円)
- 事業専従者給与の必要経費算入
- 所得が赤字の場合、他の所得との通算が可能
- 純損失の繰越控除
- 少額減価償却資産の特例
2、原則的な判断基準(事業所得と業務に係る雑所得の区分)
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が社会通念上事業と称する程度で行っているかどうかで判断します。
社会通念上による判断は、以下の判決に示された諸点を総合勘案する必要があります。以下、判示内容になります。
- 事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得
- いわゆる事業にあたるかどうかは、結局、一般社会通念によって決めるほかないが、これを決めるにあたっては営利性・有償性の有無、継続性・ 反復性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無、その取引に費した精神的あるいは肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、その者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点が検討されるべきである
3、具体的な判断基準(事業所得と業務に係る雑所得の区分)
- 記帳・帳簿書類の保存ありパターン
事業所得と業務に係る雑所得の区分については、その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられます。
(留意事項)
その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります- その所得の収入金額が僅少と認められる場合
例えば、その所得の収入金額が、例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます ※「例年」とは、概ね3年程度の期間
- その所得を得る活動に営利性が認められない場合
その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます
※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます
- その所得の収入金額が僅少と認められる場合
- 記帳・帳簿書類の保存なしパターン
その所得に係る取引を帳簿に記録していない場合や記録していても保存していない場合には、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有しているとは認め難く、また、事業所得者に義務付けられた記帳や帳簿書類の保存が行われていない点を考慮すると、社会通念での判定において、原則として、事業所得に区分されないものと考えられます。
(留意事項)
その所得を得るための活動が、収入金額300万円を超えるような規模で行っている場合には、帳簿書類の保存がない事実のみで、所得区分を判定せず、事業所得と認められる事実がある場合には、事業所得と取り扱います
(参考)事業所得と業務に係る雑所得等の区分(イメージ)
| 収入金額 | 記帳・帳簿書類の保存あり | 記帳・帳簿書類の保存なし |
|---|---|---|
| 300万円超 | 概ね事業所得(注) | 概ね業務に係る雑所得 |
| 300万円以下 | 業務に係る雑所得 ※資産の譲渡は譲渡所得・その他の雑所得 |
(注)次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
①その所得の収入金額が僅少と認められる場合
②その所得を得る活動に営利性が認められない場合
※参考資料:国税庁「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」
※コラム記載の内容は、あくまで個人的見解になります。
以上
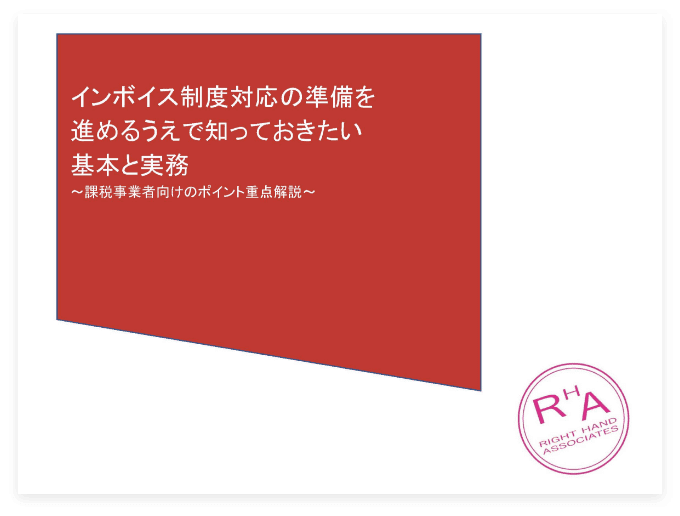
- 第1回:なぜ消費税は理解しづらいのか。法人税と消費税の計算方法の違い
- 第2回:なぜ利益が出ているのに、お金がないのか
- 第3回:令和4年1月1日施行、短期退職手当等について
- 第4回:「収益認識に関する会計基準」のポイント・対応状況について
- 第5回:中小企業向けの令和4年度税制改正のポイント
- 第6回:不正会計は他人事ではない
- 第7回:会計監査人(監査法人)が実施する棚卸立会に関して
- 第8回:会計監査人(監査法人)が実施する確認状関連の作業に関して
- 第9回:期末監査における会計監査スケジュール及び会計監査の実施内容に関して
- 第10回:決算日後に発生した「後発事象」。その種類と対応方法。
- 第11回:中小企業でも必要!会社の大小問わず必要な内部統制の解説
- 第12回:インボイス制度とは?税理士が解説する基礎知識
- 第13回:インボイス制度の解説②
- 第14回:インボイス制度の解説③
- 第15回:インボイス制度の解説④
- 第16回:インボイス制度の解説⑤
- 第17回:インボイス制度の解説⑥

公認会計士・税理士。大手監査法人勤務を経て現職。
大手監査法人において12年にわたり、公認会計士として、主に会計監査業務及び会計支援業務、内部統制監査業務及び内部統制支援業務、IFRS支援業務に従事するほか、IPO支援業務、任意監査業務、不正対応業務、財務デューデリジェンス業務等を多数手掛ける。上場準備会社を東証1部上場会社まで支援した実績あり。
上場企業はもちろんのこと中小企業の会計支援、管理体制支援及びスタートアップ企業のIPO支援、M&Aを得意とする。
大田区蒲田の税理士 税理士法人Right Hand Associates
