ITプロジェクトのプロセス
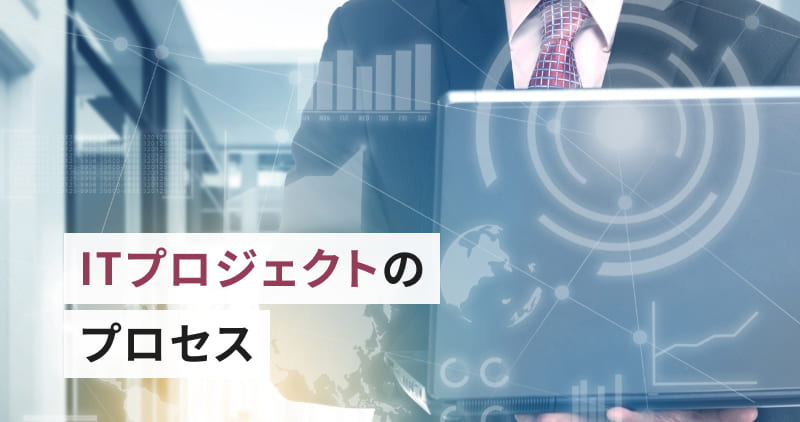
今回は、ITプロジェクトのプロセスについて解説させていただきます。
ITプロジェクトといっても、社内の1部門のみで使用するシステム、1台のPCのみで活用するシンプルなIT化から、全社を一気通貫するような、複数部門が関わる大規模システムの導入まで、様々な規模のITプロジェクトがあるかと思います。
今回は、一般的なプロセスについて、理解していただければ幸いです。
IT化構想段階から本格稼働までのプロセス
ITプロジェクトのプロセスには、主に次のようなフェーズがあります。
IT化構想段階プロセス
- IT戦略立案
- RFP策定
- システム選定
システム開発プロセス
- 要件定義
- 設計
- プログラミング
- マスタ作成
- 導入
- 受入テスト
- 並行稼働テスト
本格稼働
IT戦略立案
IT化構想段階の最初に、IT戦略立案フェーズがあります。
実際には、IT戦略立案フェーズの前に、「経営ビジョン策定」「経営戦略策定」「中期経営計画策定」といった、経営の方向性を議論するフェーズがあります。
経営ビジョン、経営戦略に沿ったIT戦略が何か、を検討、意思決定していくのが、IT戦略立案フェーズとなります。
RFP策定
RFPとは、Request For Proposalの略で、ITベンダーに提示する提案依頼書を指します。
RFP策定フェーズには、主に3つの目的があります。
1つ目は、自社にとって最適なシステムを選ぶ基準(システム化要件)を作ることです。
2つ目は、RFP策定のプロセスを通じて、社内業務の見える化を行い、現行業務の見直しを推進することです。
3つ目は、社内でブラックボックスになっている業務を取り除くことです。
システム選定
RFPでまとめたシステム化要件に沿って、自社の要件に最も近いソフトウェア、クラウドサービス、パッケージ型システムなどを選定していきます。
要件定義
システム開発の最初のフェーズが要件定義です。要求定義という場合もあります。
要件定義とは、ITベンダーとの間で、新システムに求める要件を、RFPをベースにしながら細部まで決定していくことです。
要件定義にあたっては、「FIT&GAP分析」と呼ばれる、パッケージ型システムの標準機能がシステム化要件を満たすかどうかをひとつずつデモ画面や業務フローを見ながら検証・ヒアリングをしていきます。
RFP策定フェーズと要件定義フェーズを混同されるケースがありますが、RFP策定時には、まだパッケージ型システムが確定していない状態のため、当該システムのデモ画面など見ることはできません。また、パッケージ型システム導入のための初期設定値なども、要件定義フェーズ(または次の設計フェーズ)で決定していきます。
RFP策定フェーズと要件定義フェーズでは、全く異なる進め方を行います。
設計
要件定義フェーズ完了後、設計フェーズに進みます。
設計フェーズには、基本設計フェーズと詳細設計フェーズがあります。ユーザー企業にとって関係するのは、基本設計フェーズです。
基本設計は、一般的には、カスタマイズする機能をどういう方法で具体化していくか、画面や帳票の設計を決定する作業です。
ITベンダーによっては、要件定義フェーズのなかで、基本設計に該当する内容まで行う場合もあります。
プログラミング・マスタ作成
要件定義フェーズ完了後、カスタマイズ開発がある場合は、設計フェーズを経てプログラミングフェーズへと進みます。プログラミングフェーズでは、ITベンダーによる、カスタマイズ機能のコーディング、単体テスト、結合テストが実施されます。
プログラミングフェーズと並行して、ユーザー企業ではマスタ作成を行います。
「マスタ」とは、マスタデータ、マスタファイルの略で、システムを運用する上で元となる基礎的データのことです。「商品マスタ」「取引先マスタ」「価格マスタ」などが一般的ですが、システムは多種多様なマスタによって稼働しています。
現行システムからマスタデータを取り出して、新システムに合わせてアレンジしたり、新システムにて全く新しいマスタが必要であれば、新規でマスタを作成していくことになります。
導入・受入テスト・並行稼働テスト
新システムのサーバー等へのインストール、パラメータ設定等の初期設定作業、マスタデータの反映などが完了すれば、新システムの稼働確認のためのテストを開始します。
テストは大きく、受入テストと並行稼働テストの2種類があります。
受入テストでは、業務フローが想定通りに流れるか、カスタマイズ開発した機能が正常に稼働するか、RFPや要件定義書通りに機能が稼働するか、などを確認します。
並行稼働テストでは、現行システム(現行業務)と同じデータを1ヶ月分入力して、売上金額、仕入金額などが、新システムと現行システム(現行業務)で一致しているかなど、新システムの正確性をチェックします。
本格稼働
並行稼働テストが完了すると、本格稼働に進んでよいか否かを決定する判定会議を開きます。
それまで使っていた現行システムの使用を停止し、新システムでの業務を開始するのが、本格稼働です。
社内を横断するような重要なシステムを導入する際には、判定会議には、プロジェクトメンバーだけでなく、経営層も参加します。本格稼働に進めて良いかどうかの経営意思決定を行います。
PMOに求められる役割
ここまで、ITプロジェクトのプロセスの概要を見てきました。
導入対象のシステムやその規模によって、各フェーズの有無や、期間の長さなどが異なりますが、一般的なプロセスを紹介いたしました。
PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)では、こうしたITプロジェクトのプロセスをスムーズに進めるために、社内の合意形成と、ITプロジェクトへの協力体制の構築、ITベンダーとの円滑なコミュニケーションを図ることがたいへん重要であります。
経営ビジョン、経営戦略実現のために、ITプロジェクト成功が不可欠であることを関係者にご理解いただき、全社が一丸となって邁進していけるよう、環境整備を行うことが、PMOの役割として求められます。

システムアナリスト
ITプラン株式会社 代表取締役
外資系IT企業にて、システムエンジニアとして、都市銀行の営業店システム、インターネットバンキングシステム、マルチペイメントネットワークシステム、システム統合を担当。
2008年に中小企業診断士として独立し、ITプラン株式会社を設立。IT戦略コンサルタントとして、中小企業、中堅企業の製造業を中心に、コーチング・ファシリテーションを用いたIT戦略立案・遂行、基幹システム更改プロジェクト推進、業務改善のサポートに取り組む。
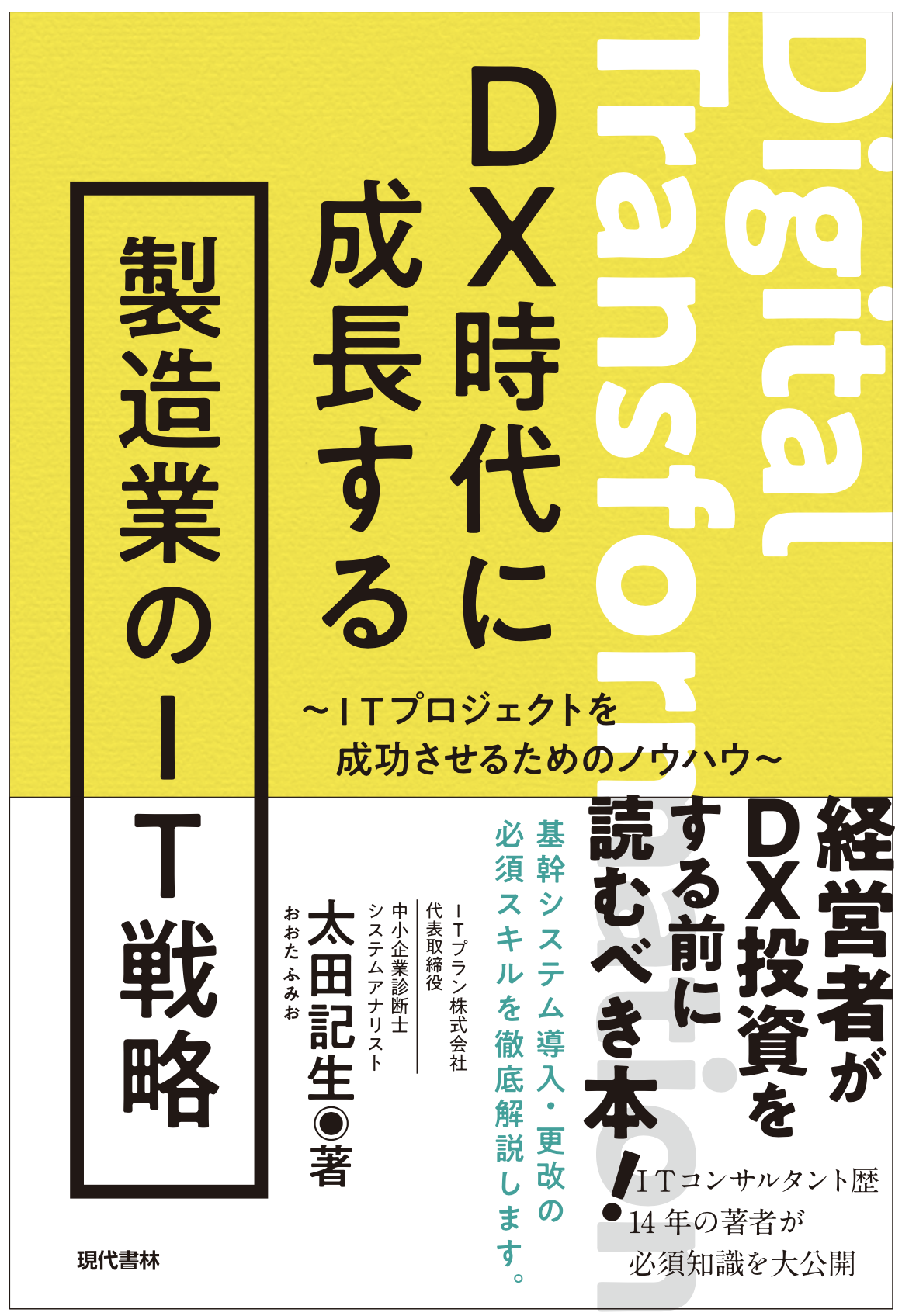
2022年10月に『DX時代に成長する製造業のIT戦略〜ITプロジェクトを成功させるためのノウハウ』を全国出版した。
