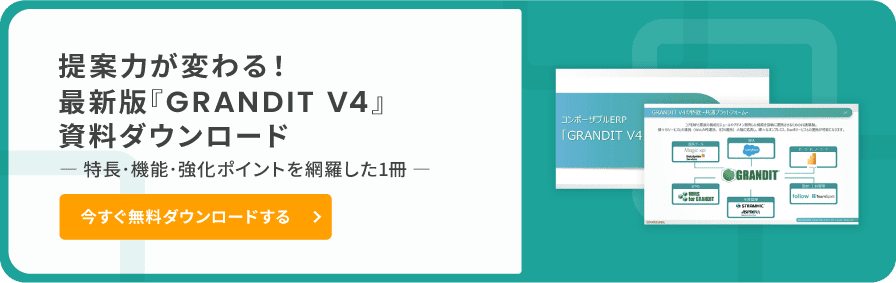多重下請け構造からの脱却へ!中堅SIerがプライマリーを目指すための戦略による成長モデル
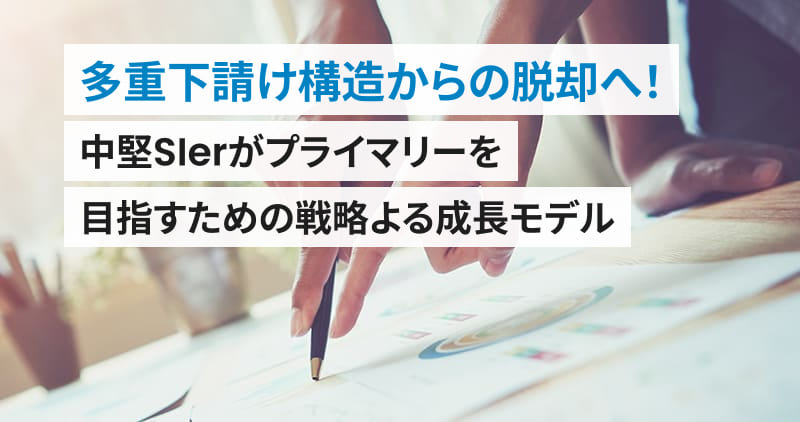
現在、貴社は大手SIerからの下請け案件が中心で、収益性や将来性に課題を感じていませんか?「いつか自社でプライマリー案件を獲得し、顧客と直接向き合って高付加価値を提供したい」――そうお考えの経営者や幹部の方も少なくないでしょう。
日本のIT化を長年支えてきたSIer業界は、今、大きな転換期を迎えています。本記事では、日本のSIer業界が抱える共通の課題、特に中堅SIerの成長を阻む「多重下請け構造」に焦点を当てます。そして、この構造から脱却し、プライマリー案件を獲得して持続的な企業成長を遂げるための具体的な戦略を解説していきます。
1.日本のSIer業界が抱える根本的な課題
日本のSIer業界は、高度経済成長期から今日に至るまで、企業のIT化を牽引し、経済発展に大きく貢献してきました。しかし、近年、国内外のIT環境の変化や社会情勢の変遷とともに、多くの課題に直面しています。これらの課題は、SIer各社のビジネスモデルや収益性、ひいては持続可能性に大きな影響を与える可能性があります。
主な課題は以下の通りです。
| 課題 | 概要と現状 | 中堅SIerへの影響 |
|---|---|---|
| IT人材不足と高齢化 | 少子高齢化に伴う労働人口の減少に加え、IT技術の進化にスキルが追いつかない「スキルギャップ」も深刻化しています。若年層のIT業界離れや、熟練エンジニアの引退も進んでいます。 | 限られたリソースの中で、新規案件の獲得や技術革新への対応が難しくなります。特に、新しい技術(クラウド、AIなど)に対応できる人材の確保が急務です。 |
| クラウドサービスの普及と内製化の加速 | AWS、Microsoft Azure、GCPなどのクラウドサービスが一般化し、企業がシステムを自社で構築・運用する「内製化」の動きが加速しています。 | 従来の「システム構築・運用」というSIerの主戦場が縮小傾向にあります。既存のビジネスモデルの見直しが迫られ、受託開発以外の収益源の確保が課題となります。 |
| 旧態依然としたビジネスモデル | 顧客の要望をそのまま形にする「言われた通りに作る」という受動的なビジネスモデルが根強く残っています。これでは高付加価値を提供しにくい傾向があります。 | 顧客の真の課題解決に踏み込んだ提案が難しく、価格競争に巻き込まれやすい体質になります。結果として、収益性が伸び悩む要因となることがあります。 |
| 国際競争力の低下 | 日本独自の開発手法や商習慣が、グローバルスタンダードから乖離している「ガラパゴス化」が指摘されます。海外市場への進出も遅れがちです。 | コスト競争力で優位性を持つ海外のオフショア開発などとの競合が激化します。グローバルな視点でのビジネス展開や、最新技術への対応が求められます。 |
これらの課題の中でも、特に多くの中堅SIerの成長を阻み、収益構造に大きな影響を与えているのが「多重下請け構造」です。
2.中堅SIerにとっての「多重下請け構造」の深い闇
前章で触れた様々な課題の中でも、中堅SIerの収益性や成長を特に強く阻害しているのが、日本特有の「多重下請け構造」です。この構造は、長年の商習慣として定着していますが、その弊害は計り知れません。
1)多重下請け構造とは?
システムの開発プロジェクトにおいて、エンドユーザーから案件を直接受注する元請け企業から、二次請け、三次請け……と、間に何社ものSIerが介在する構造のことです。まるでピラミッドのように階層が深くなるのが特徴です。
2)なぜ多重下請け構造が生まれるのか?
多重下請け構造が存在する主な要因は以下の通りです。
| 主な要因 | 説明 |
|---|---|
| 大手SIerの戦略 | 大手は多くの案件を抱え、リソースが不足する場合、下請けに依頼することで開発体制を確保します。 |
| リスク分散 | プロジェクトの規模が大きくなるほど、リスクを分散させる目的で下請けに業務を切り出すことがあります。 |
| 専門性の不足 | 特定の技術やノウハウが不足している場合、その専門性を持つ下請けに依頼します。 |
3)中堅SIerへの具体的な影響
このような多重下請け構造は、特に元請けになれていない中堅SIerにとって、以下のような深刻な影響を及ぼします。
| 弊害 | 概要と中堅SIerへの影響 |
|---|---|
| 収益性の低迷 | プロジェクトの費用から、各階層で中間マージンが差し引かれます。結果として、最下層に近い中堅SIerには極めて限定された利益しか残らず、労働の対価が十分に得られません。頑張って開発しても、なかなか利益に繋がりづらい構造です。 |
| 技術力の伸び悩み | 下請け案件では、要件定義や設計といった上流工程に携わる機会が限定的です。多くの場合、元請けから指示された範囲の「言われた通り」の開発やテストが中心となりがちで、より複雑な問題解決能力や新しい技術への応用力を養う機会が失われやすいです。 |
| モチベーションの低下と離職 | 自身が開発したシステムが最終的にどう使われているのか、顧客の顔が見えにくい環境では、エンジニアのモチベーションが低下しやすくなります。低賃金や限定されたキャリアパスも相まって、優秀な人材の定着が難しくなる一因となることがあります。 |
| 顧客との接点の喪失 | エンドユーザーと直接対話する機会がほとんどないため、顧客の真のニーズや課題を把握できません。これは、将来的に自社で顧客に直接提案できるような「提案力」を磨く上での大きなハンディキャップとなります。 |
| 企業ブランディングが困難 | 元請けとしてプロジェクト名や顧客名を明かせないため、自社の実績をアピールしにくく、外部からの評価や認知度を高めることが困難になります。 |
このような状況を打破しない限り、中堅SIerが目指す「持続的な成長」は絵空事で終わってしまうかもしれません。
3.多重下請け構造から脱却する!中堅SIerのための戦略パス
これまでの章で、日本のSIer業界が抱える課題、特に中堅SIerを悩ませる多重下請け構造の弊害を明確にしてきました。しかし、この現状をただ嘆いているだけでは何も変わりません。重要なのは、この構造を打破し、自社がプライマリー案件を獲得するための具体的な道筋を描くことです。
多重下請け構造からの脱却は、単に「仕事を増やせばよい」という単純な話ではありません。それは、ビジネスモデルそのものを、「単なる労働力提供」から「高付加価値なソリューション提供」へと転換し、ひいては「受動的な下請け」から「能動的な元請け」へとシフトすることに他なりません。
この大きな変革を成功させるために、ここでは以下の3つの戦略を組み合わせることを強く推奨します。これらの戦略はそれぞれが独立しているだけでなく、互いに連携し、相乗効果を生み出すことで、プライマリー獲得への道を力強く後押しします。
| 戦略パス | 目指す方向性 | なぜこの戦略が有効なのか |
|---|---|---|
| メジャーなパッケージ製品を取り扱う | 自社が提供する「商材力」を強化し、市場におけるニーズと信頼性を獲得します。 | ゼロから開発するリスクを回避し、実績のある製品を基盤にビジネスを展開できます。これにより、顧客への提案がしやすくなり、新規顧客獲得のハードルを下げられます。 |
| 導入ノウハウを持った人材を育成する | パッケージ製品を「売るだけ」ではない、真の課題解決能力と「高付加価値」を生み出す人材を育てます。 | 製品の選定から導入、カスタマイズ、運用まで一貫してサポートできる専門家は、競合との明確な差別化要因となります。顧客の業務に深く入り込み、信頼を得る鍵です。 |
| 顧客との接点を拡大し元請け化を図る | エンドユーザーと直接対話することで、真のニーズを把握し、利益率の高いプライマリー案件を継続的に獲得する体制を築きます。 | 中間マージンが削減され、収益性が大幅に向上します。また、プロジェクトの主導権を握り、顧客のビジネスに直接貢献できるため、やりがいとブランド力が高まります。 |
これらの戦略は、一朝一夕に実現できるものではありません。しかし、明確なビジョンと計画を持って取り組むことで、貴社が多重下請け構造の「深い闇」から抜け出し、明るい未来を切り開くための強力な武器となるでしょう。
4.プライマリー獲得への戦略「パッケージ×ノウハウ×直接関係」
多重下請け構造から脱却し、プライマリー案件を獲得するためには、前章で示した3つの戦略を組み合わせ、相乗効果を生み出すことが重要です。ここでは、それぞれの戦略について、より具体的に掘り下げていきましょう。
1)メジャーなパッケージ製品を取り扱う
プライマリーを獲得するために「自社開発製品」を持つことは有効な手段ではありますが、ゼロからシステムを開発する「スクラッチ開発」は、時間もコストもかかり、リスクも大きいものです。そこで、まずは市場で実績があり、多くの企業に導入されているメジャーなパッケージ製品を取り扱うことを検討しましょう。
| メジャーパッケージ製品のメリット | 具体的な効果 |
|---|---|
| 市場ニーズの獲得 | 多くの企業が導入を検討しているパッケージは、すでにその製品自体に潜在的な顧客ニーズが存在します。貴社がその製品を扱えることで、新規顧客へのアプローチが格段に容易になり、商談のハードルを下げられます。 |
| 事業立ち上げの短期化、リスク低減 | 事業立ち上げの初期段階で製品ベンダーの支援を受けることができます。営業支援や案件紹介、開発要員の支援などを受けながら事業立ち上げを進めることで、リスクを抑えた早期の事業立ち上げが可能です。 |
| 開発リスク・コストの削減 | ゼロからシステムを構築するスクラッチ開発に比べ、パッケージ導入は開発工数を大幅に削減できます。これにより、プロジェクト期間の短縮や開発費用の最適化が可能となり、結果として収益性向上に繋がります。 |
| 安定した保守・運用収益 | パッケージ製品には、導入後の保守やバージョンアップ、機能追加といった継続的なサポートが必要不可欠です。これらのサービスを提供することで、安定した収益源を確保でき、経営基盤を強固なものにできます。 |
| 専門性構築の足がかり | 特定のパッケージ製品に特化することで、その製品に関する深い知識や経験を蓄積できます。これが「特定の分野における専門家」としてブランディングする足がかりとなり、次の「導入ノウハウ」へと繋がります。 |
どのようなパッケージ製品を選ぶかは、貴社の強みや今後の事業戦略、顧客層などを考慮して慎重に決定する必要があります。特にERP(統合基幹業務システム)分野の製品は、顧客企業の基幹業務を任せられることで、継続的な顧客企業との接点を構築するのに役立ちます。
2)導入ノウハウを持った人材を育成する
単にパッケージ製品を取り扱うだけでは、他社との差別化は難しいでしょう。重要なのは、そのパッケージ製品を顧客のビジネスに最大限に活かすための「導入ノウハウ」です。単に製品を「売る」だけでなく、「いかに顧客の課題を解決するか」を提案できる人材を育成することが、高付加価値化への鍵となります。
| 導入ノウハウを持つ人材の重要性 | 具体的な効果 |
|---|---|
| 高付加価値サービスの提供 | パッケージ導入は、単にソフトウェアをインストールするだけではありません。顧客の現状業務を深く理解し、パッケージの機能を業務にどうフィットさせるか、あるいは業務プロセス自体をどう変革すべきかを提案できる人材は、コンサルティング能力も持ち合わせています。これが、競合他社には真似できない高付加価値なサービスとなり、競争優位性を確立します。 |
| 差別化要因の創出 | 同じパッケージ製品を扱っていても、導入における深い知見や過去の成功事例、トラブル対応能力は、各社独自の強みとなります。特に特定の業界(例:医療、金融、製造など)や、特定の業務(例:マーケティング、サプライチェーン管理など)に特化した導入ノウハウは、その分野の「エキスパート」として大きな差別化になります。 |
| 顧客満足度の向上 | 適切な導入ノウハウを持つことで、顧客は期待通りの効果を享受しやすくなります。結果として、顧客満足度が向上し、これが口コミやリピート、さらには新たな案件紹介へと繋がり、安定的なビジネス基盤を築く上で非常に有利に働きます。 |
| エンジニアのスキルアップ | 要件定義、業務分析、カスタマイズ設計といった上流工程に携わる機会が増えることで、エンジニアはより実践的なスキルを習得できます。これはエンジニア自身のキャリアアップにも繋がり、ひいては自社の技術力全体を底上げすることに貢献します。 |
導入ノウハウを持つ人材を育成するためには、社内研修プログラムの充実、ベンダー認定資格の取得支援、OJT(On-the-Job Training)による実践的な経験の蓄積、そして上流工程を経験させるための意識的なアサインなどが有効です。
3)顧客との接点を拡大し元請け化を図る
そして、最終的な目標は、エンドユーザーである顧客と直接契約を結び、元請け化を図ることです。これは、利益率の改善だけでなく、ビジネスの主導権を握り、自社のブランド力を高める上で最も重要なステップとなります。
| 元請け化のメリット | 具体的な効果 |
|---|---|
| 収益性の大幅な改善 | 多重下請け構造の最大の課題であった中間マージンの排除は、貴社の収益構造を根本から変革します。直接顧客と契約することで、これまでの案件では得られなかった利益を確保できるようになり、収益性が飛躍的に向上します。これは、社員への適正な報酬、新たな技術への投資、そして事業拡大のための原資となります。 |
| 企業ブランディングの確立と市場でのプレゼンス向上 | プライマリー案件の獲得は、単発の収益増加に留まりません。顧客との直接的な関係を築き、その課題解決に深く貢献することで、長期的な信頼関係が構築されます。これにより、継続的な保守・運用案件や、顧客の新たなニーズに対応した追加案件など、安定したリカーリングビジネスの創出が可能になります。これは、外部環境の変化に左右されにくい、強固な経営基盤の構築に繋がります。 |
| エンジニアのモチベーション向上と優秀な人材の獲得・定着 | 直接顧客と向き合い、要件定義や設計といった上流工程からプロジェクトに参画できることは、エンジニアにとって大きなやりがいとなります。自らの仕事が顧客のビジネスに直接貢献していることを実感できるため、モチベーションが向上し、技術者としての成長を加速させます。また、収益性改善による適正な報酬や、魅力的なキャリアパスの提示は、優秀な人材の獲得と定着にも直結し、貴社のさらなる技術力向上へと繋がる好循環を生み出します。 |
| イノベーションへの貢献と未来のビジネス創出 | 顧客の課題を直接把握し、その解決策をITで提案できる立場となることで、貴社は単なる開発ベンダーではなく、顧客のビジネス変革(DX)を支援する真のパートナーへと進化できます。これにより、最先端の技術動向を取り入れた提案や、新たなビジネスモデルの創出にも主体的に関与できるようになり、社会全体のイノベーションに貢献する喜びも得られるでしょう。 |
この3つの戦略を組み合わせることで、貴社は多重下請け構造という古い枠組みを打ち破り、より高収益で、やりがいのある、そして未来へと続くビジネスを創造できるはずです。
5.国産ERP「GRANDIT」のご紹介
ERP「GRANDIT」は、複数の企業が叡智を出し合って日本企業の成長を支えていこうとの理念を掲げ、ユーザー系SI企業を中核にコンソーシアムを立ち上げました。そして、ユーザー視点の「本当に使いやすい」ERPを開発、コンソーシアムのパートナー企業が販売を請け負うという、これまでにないスキームを作り出しています。
コンソーシアムの最大のメリットは、複数社のノウハウを活かした製品開発ができる点です。パートナー企業がサポートする業種は様々で、各社が独自のノウハウを持っています。それらを結集し、普遍的なものへと昇華させることで、多くのユーザーにとって使いやすい、偏りのない、先進的なERPパッケージの構築を実現しています。
コンソーシアム企業の叡智から生まれた、常に進化するERPであること。それこそGRANDITと他の製品との一番の違いであり、GRANDITの本質的な強みです。
[プライムパートナー制度のご紹介]
https://www.grandit.jp/partner/
6.中堅SIer脱却戦略:プライマリー獲得への道
現在多くの中堅SIerが直面している多重下請け構造という課題に焦点を当て、そこから脱却し、プライマリー案件を獲得するための具体的な3つの戦略を提示してきました。
改めて、その戦略の柱を確認しましょう。
-
メジャーなパッケージ製品を取り扱う
市場に受け入れられた商材で、顧客へのアプローチを容易にし、安定的な収益源を確保します。 -
導入ノウハウを持った人材を育成する
パッケージを顧客のビジネスに最適化する「専門家」を育成し、高付加価値と差別化を実現します。 -
顧客との接点を拡大し元請け化を図る
直接顧客と向き合い、利益率の改善、ビジネスの主導権、そして長期的な信頼関係を築きます。
これらの戦略は、決して簡単な道のりではありません。既存のビジネスモデルを変革するには、時間も、労力も、そして経営層の強いコミットメントが必要です。しかし、多重下請け構造に留まり続けることは、利益率の低迷、人材の流出、そして将来的な事業の縮小という、さらに厳しい現実へと繋がる可能性が高いことも事実です。
貴社が目指す「自社がプライマリーを取る」という目標は、単に収益性を改善するだけでなく、社員一人ひとりのやりがいを高め、企業のブランド力を向上させ、そして何よりも自身の持続的な成長を確実にするための、非常に重要な一歩です。
以下ホワイトペーパーでは、新バージョンGRANDIT V4の詳細を確認いただけます。ぜひあわせてご覧ください。
※記事の内容は、制作時点に一般公開されている情報に基づいています。また、記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。