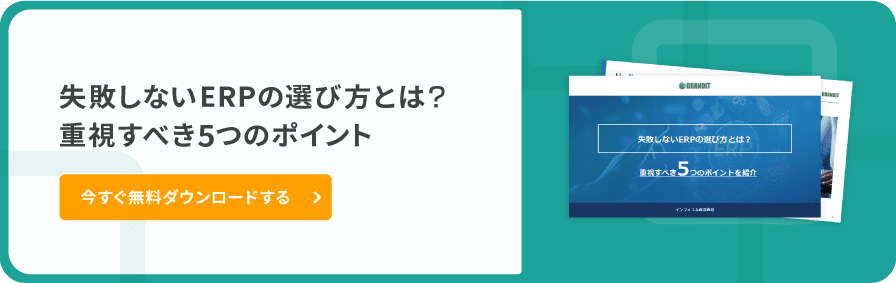成熟市場で勝ち残る製造業DX:ERP刷新に学ぶ経営基盤強化と収益力向上

日本の製造業、特に中堅企業は今、大きな転換点に立たされています。急速な市場の変化、グローバル競争の激化、人手不足や原材料価格の高騰、さらには脱炭素やESG対応といった新たな社会的要請——これらはすべて、従来のやり方のままでは乗り越えられない課題ばかりです。
こうした状況に対し、多くの企業が注目しているのがDX(デジタルトランスフォーメーション)です。DXは単なるITの導入ではなく、企業のビジネスモデルや業務プロセス、さらには組織文化や働き方までも再設計し、変化に強い経営基盤を構築するための戦略的取り組みと位置付けられています。
特に製造業では、ERP(Enterprise Resource Planning)などの基幹システムを土台とした業務のデジタル化・可視化が、DX推進の第一歩とされています。製造から販売、在庫、調達、会計、人事に至るまで、企業活動全体を一気通貫で管理できるERPは「現場」と「経営」を結び付ける中核的な存在です。
1.モデル企業が直面した経営課題
温度センサ(サーミスタ)で世界トップシェアを誇る電子部品製造業の企業をモデルに、同社が直面する市場の変化や経営課題、そしてそれに対応するために実施したERP刷新やDX推進の取り組みを掘り下げていきます。
同社は、サーミスタ(温度センサ)において世界トップシェアを誇る、日本を代表する電子部品メーカーの一つです。高い信頼性と品質管理体制を武器に、自動車・家電・医療機器など幅広い分野に製品を供給し、安定した収益基盤を築いてきました。
しかし、近年の市場環境の変化や経営環境の複雑化に直面し、持続的な成長を実現するためには構造的な課題に取り組まざるを得ない局面に立たされています。以下では、モデル企業が直面した代表的な課題を6つに整理して解説します。
1)主力市場の成熟化と新規領域への展開ニーズ
主力製品であるサーミスタは、すでに世界的に高いシェアを獲得しており、製品自体の性能や品質には定評があります。しかし、市場全体が成熟し、従来のような右肩上がりの成長は期待できない段階に入りました。
特に自動車向けを中心とする需要の一巡や、一般家電市場の鈍化により、新たな製品群や用途開拓、医療・環境・エネルギー分野といった新領域への展開が求められています。
2)受注変動と在庫調整への対応力
欧州のガス供給問題や巣ごもり需要の反動といった外部環境の急変により、主要顧客の在庫調整が発生しました。その結果、受注が一時的に大きく落ち込むという事態が生じました。
このような需給変動は今後も続く可能性があり、柔軟かつ精緻な在庫・生産管理体制の構築が不可欠です。
3)グローバル競争への適応力と営業体制の強化
電気自動車(EV)や再生可能エネルギーなどの成長市場においては、欧米・中国の大手メーカーとの競争が激化しています。これらの市場で競争優位を保つには、技術力だけでなく、提案力・営業力・現地対応力といったソフト面の強化が求められます。
また、地域別で異なる法規制や品質要件に対応するためには、グローバルで一貫した製品開発・販売・サポート体制の整備が欠かせません。
4)M&A・経営統合による変化とガバナンス強化
電子部品業界にも、企業価値向上や事業領域の拡大を目的とした、資本業務提携・経営統合の潮流が押し寄せています。このような動きは、経営の独立性やグループガバナンス、シナジー創出の方向性に大きな影響を与えるもので、外部からの影響が強まる中で、企業としてのアイデンティティと成長戦略をいかに再構築するかが重要な課題となっています。
5)収益力・生産性の持続的強化
グローバル競争に勝ち抜くためには、製品力の強化だけでなく、安定した利益体質の構築が不可欠です。モデル企業でも生産性向上・設備更新・人員最適化を進める一方、営業利益率・ROEなどの財務指標の改善を中期経営計画の中核に据えています。
工場や部門単位でのコスト管理、原価計算の高度化、業務効率化による間接コストの削減などが重要なテーマとなります。
6)人材育成と多様性の推進
新市場への進出やグローバル展開を支えるのは、やはり「人」です。モデル企業では、開発体制の強化や多様な人材の登用、女性活躍推進など組織力の底上げに注力しています。
今後の持続的な成長のためには、若手の育成、ナレッジの継承、多様な働き方の実現といった人的資本への投資が、これまで以上に不可欠となるでしょう。
| 課題カテゴリ | 内容の要約 |
|---|---|
| 市場の成熟 | サーミスタの既存市場が成熟し、新領域への展開が必要な状況です。 |
| 需給変動 | 在庫調整など外部要因による受注リスクが増加しています。 |
| グローバル競争 | 海外メーカーとの競争激化に伴い、営業・現地対応力の強化が求められます。 |
| M&A環境変化 | 統治体制の再構築と経営戦略の見直しが必要な状況です。 |
| 生産性強化 | 財務指標改善と製造現場の生産性向上が必須とされています。 |
| 人的資本強化 | 開発力・多様性・次世代人材の育成が課題です。 |
2.課題解決の鍵としてのERP刷新
このように、同社は市場の成熟化、グローバル競争の激化、M&Aによる外部環境の変化、人的資本課題など、複数の経営課題を同時に抱えていました。これらに対応するためには、個別の業務改善では限界があり、企業全体の構造を再設計する抜本的な取り組みが必要となりました。
そこで同社が注目したのが、ERP(Enterprise Resource Planning)=統合基幹業務システムの刷新です。単なるシステム更新ではなく、「経営の中枢神経」としてERPを再定義し、全社的な業務改革と意思決定の迅速化を実現する基盤として導入を決断しました。
1)ERP刷新の背景にある経営課題の共通項
ERP刷新を決断した背景には、以下のような複数の課題に「共通する根本原因」がありました。
- 情報が部門や拠点、子会社ごとに分断され、グループ全体をリアルタイムに把握できない
- 各種帳票やデータをExcelや手作業で加工しており、作業負担やミスリスクが高い
- 経営層が意思決定を下すまでに時間差や情報のバラつきが発生
- 生産や調達、販売の需給調整にタイムラグがあり、過剰在庫や機会損失につながっていた
- 財務・会計や原価計算などがグループごとに異なる管理方法となっており、連結経営管理が煩雑
これらの問題は、「業務プロセスと情報の分断」が生み出す非効率の典型例です。部分最適の積み上げでは抜本的な解決には至らず、「統合されたデジタル基盤」が不可欠と判断されたのです。
2)ERP刷新の3つの目的
ERP刷新に託した目的は、単なるIT化ではなく、経営・業務・組織全体の変革でした。具体的には、以下の3点が大きな柱となります。
1. 経営判断の迅速化とリアルタイム経営
- グループ全体の財務・販売・在庫・生産情報をリアルタイムで見える化
- 経営層に対してデータに基づく迅速な意思決定支援を可能
- 中長期戦略の立案やM&A判断にも資する情報基盤を整備
2. 業務プロセスの標準化と効率化
- グループ各社の異なる業務手順・帳票類を共通化・自動化
- 属人化した作業や二重入力、紙のやり取りを排除
- 法対応(J-SOXや電子帳簿保存法)への対応力も向上M&A判断にも資する情報基盤を整備
3. 内部統制の強化と経営ガバナンスの向上
- 業務フローや承認ルールを統一し、統制プロセスを明確化
- 子会社も含めたガバナンス体制の一元管理を実現
- 将来的なM&Aや事業再編にも柔軟に対応可能な基盤を構築
3)ERP刷新プロジェクトの全体像
同社のERP刷新は、グループ全体を対象とした「ビッグバン方式」による全面導入で行われました。以下は、刷新の全体イメージを示したものです。
【ERP刷新プロジェクトの構成】
- 導入方式: ビッグバン導入(全社同時稼働)
- 対象範囲: グループ全体(親会社+子会社)
-
導入モジュール:
- 会計(財務・管理)
- 販売・購買
- 在庫管理
- 生産管理
- 人事給与
- 原価管理
- その他、全社業務をカバー
-
主な特徴:
- データの一元管理とリアルタイム連携
- 各拠点の業務プロセス統一と見直し
- 承認フロー・権限管理の厳格化
4)現場の巻き込みと変革マネジメント
ERP刷新の成功には、現場の理解と協力が不可欠です。同社では、以下のような「巻き込み型のプロジェクトマネジメント」を徹底しました。
- 各部門からキーユーザーを選定し、要件定義から参加
- 業務フローの「見える化」と課題整理を全社で実施
- 本稼働前には繰り返しのシナリオテストと教育を実施
- IT部門が単独で主導するのではなく、経営企画・製造・営業など各部門との連携体制を構築
これにより、単なるシステム導入ではなく、「全社的な意識改革」としてのDXを実現することに成功しました。
3.ERP導入によって実現した変化
ERPを全面刷新したことで、単なる業務のIT化にとどまらず、経営と現場、グループ企業を横断した「本質的な業務変革」がもたらされました。ここでは、ERP導入によって実現された具体的な成果について、「経営」「業務プロセス」「情報管理」の3つの観点から紹介します。
1)経営判断の迅速化と精度向上
ERP導入前は、親会社・子会社ごとに情報システムが異なっていたため、グループ全体の損益や在庫状況を横断的に把握するには時間と労力がかかっていました。
特に以下のような課題が存在していました。
- 月次決算の集計作業に時間がかかる(子会社からの報告待ち)
- 製造・販売データのズレによる在庫の過不足
- 経営会議用の資料がアナログ(Excelベース)で作業が煩雑
しかし、ERP導入後はこれらの課題が大幅に改善されました。
【導入後の変化】
- 各拠点・子会社のデータがリアルタイムに本社に集決算処理のリードタイムが大幅に短縮(数日~1週間から翌日集計へ)
- CFO・経営企画部門が「今」の数字で意思決定が可能
- グループ全体の資源配分や在庫配置の最適化が進んだ
| 項目 | ERP導入前 | ERP導入後 |
|---|---|---|
| 情報収集 | 部門・拠点ごとに手作業 | 一元管理・自動取得 |
| 決算スピード | 約1週間以上 | 翌営業日で概算把握可能 |
| 資料作成 | Excel手作業 | ダッシュボードで自動表示 |
| 経営判断の精度 | 過去実績が中心 | 最新実績+予測データで判断 |
2)業務プロセスの標準化と効率化
ERP導入の副次的効果として非常に大きかったのが、業務プロセスの見直しと標準化です。これまで拠点ごとに異なっていた業務フロー、伝票処理、棚卸、受注登録などを洗い出し、ベストプラクティスに沿って共通ルールに再設計しました。
【業務面の変化例】
- 手書き帳票や紙ベースの申請を廃止し、ワークフローを電子化しました。
- 二重入力を排除し、マスター連携による入力ミスを低減しました。
- 棚卸作業や在庫照会がオンラインで可能になりました。
- 製造部門・購買部門間の納期調整をERP上でリアルタイムに連携できます。
これにより、部門間・拠点間の連携ロスが解消され、業務スピードと正確性が大きく向上しました。
3)データ品質の向上と全社的な情報活用体制の確立
ERP刷新により、データの入力から集計、活用に至るまでの一貫したデータマネジメント体制が整いました。各モジュールで発生したデータは、リアルタイムで他モジュールに連携され、「一つの真実(Single Source of Truth)」が組織全体で共有されるようになったのです。
【主な成果】
- 過去にバラバラだった取引先情報や商品コードが一元化
- 原価管理・収益分析が部門単位でも正確に実行
- 人事・労務データと業績データを突合させた生産性分析が可能
- 社員のITリテラシーが向上し、「自分たちでデータを見る」文化が醸成
このように、ERPは単なる情報の管理ツールではなく、「経営と現場をデータでつなぐ共通言語」として機能し始めました。
4)「見える化」が生んだ副次的効果
ERP導入によって得られた「可視化」は、管理部門や製造部門だけでなく、営業・開発といった「非IT部門」にも意識変革を促しました。
- どの製品の利益率が高いのか
- どの得意先が在庫回転率を落としているのか
- 開発リソースをどこに集中すべきか
こうした問いに、感覚ではなく「データで答える」文化が浸透していったのです。
ERP刷新によって得られたこのような成果は、同社が直面していた課題への「第一の回答」として機能しました。しかし、真の競争力強化には、現場の生産性改革という「もう一つの車輪」も不可欠です。
4.生産現場における自動化とデジタル活用
同社のDX推進において、ERP刷新と並ぶもう一つの大きな柱が「生産現場の自動化とデジタル活用」です。これは、同社の競争力の源泉である「高品質・高信頼性な製品を、安定して、効率よく提供する力」を持続させるために不可欠な取り組みです。
ここでは製造現場がどのように変化してきたのか、具体的な施策とその成果を紹介します。
1)自動化設備の内製化による競争力の確保
同社は、サーミスタの生産における素子製造や加工、検査などの主要工程において自動化を積極的に進めています。
特筆すべきは、自動化設備を外注せず、社内で設計・開発・運用までを完結させている点です。これにより、以下のような強みが得られています。
- 設備仕様を製品仕様に完全にフィット
- 小回りの利くチューニングやバージョンアップを迅速に実行
- 機密性の高いノウハウを社外に開示せずに済む
- 長期的な保守・改修を自社主導で実行
2)生産性向上と品質の安定化を両立
同社が自動化に注力する背景には、単なる省人化ではなく「品質の均質化」と「多品種少量生産への対応力強化」という目的があります。
サーミスタは非常に微細な電子部品であるため、人的作業に頼ると微細なバラつきが品質に影響するリスクがありました。自動化により、製造条件の厳格な管理と再現性の確保が可能となり、歩留まりが大きく改善したといいます。
3)設備データの活用によるメンテナンス最適化
生産設備の自動化が進む中で、設備の稼働ログ・センサーデータの収集と分析による「予兆保全」も導入されています。具体的には以下のような取り組みが進められています。
- 異音・振動・温度・通電状況などのセンサー情報を常時記録
- 稼働率の低下傾向や部品の異常兆候を早期に検出
- 予防保全や最適なメンテナンス時期をスケジューリング
これにより、突発的な設備停止による生産ロスを未然に防止する体制が構築されています。
4)製造と経営の距離を縮める情報連携
かつての製造現場は、経営や販売との距離が遠く、「工場の中で完結する現場」と位置づけられていました。しかし、ERPや自動化の進展により、今や製造現場はリアルタイムに経営情報とつながる「戦略ユニット」となっています。
たとえば、次のような連携が可能になります。
- 製造の遅れが販売計画に即座に反映され、営業活動が自律的に調整されます。
- 在庫変動に応じて、調達部門がタイムリーに発注調整を行います。
- 生産効率の変化をもとに、月次収支や原価予測が自動更新されます。
このように、製造情報はもはや「現場のための情報」ではなく、全社の意思決定を支える「企業資産」へと変貌を遂げているのです。
5.DXの本質と中堅製造業への示唆
同社が取り組んだERP刷新と生産現場の自動化は、単なるIT導入や業務効率化にとどまらない、企業変革(トランスフォーメーション)の本質に迫る取り組みでした。
この章では、同社の事例を通じて見えてきた「DXの本質」と、同じような課題を抱える中堅製造業が今後進むべき方向性について整理します。
1)DXは「ITの導入」ではなく「経営の再構築」
多くの企業がDXという言葉に踊らされ、単発のツール導入や部分最適に終始してしまうことがあります。しかし、事例からもわかるのは、DXとは経営そのものを見直す取り組みであるということです。
- ERP導入は「情報をつなげる手段」であり、目的は経営判断と業務変革
- 自動化は「現場を楽にする手段」であり、目的は持続的な競争力の確保
- ITは「変革を進めるための土台」であり、主役は「人と組織」
単なるツール導入に終わらず、プロセス・文化・組織・人材のすべてを再定義する形でDXを進めたからこそ、経営成果として結実するのです。
2)DX成功の鍵は「全社最適」と「現場主導」の両立
DXを進める上で重要なのが、経営トップの強いリーダーシップによる全社最適の視点と、現場の知見や課題感を起点とした現実的な施策の積み上げという両輪のバランスです。
【DX推進、運営体制】
- 経営企画・IT・現場のキーユーザーによるクロスファンクショナルなチーム構成
- 業務フローの可視化と再設計を全社員を巻き込んで実施
- 本社と製造・販売現場を横断したPDCA体制を構築
このような運営があったからこそ、「システムのための業務変更」ではなく、「業務のためのシステム改革」が実現されたのです。
3)中堅製造業にとってのDXの第一歩とは?
モデル企業のようなDXを実現するには、いきなり全社的な投資やビッグバン導入を行う必要はありません。中堅製造業が今すぐ取り組める第一歩は、以下のような「小さな変革」からです。
1. 現状業務の棚卸しと「属人化」「紙作業」の見える化
- 毎日の業務で「誰が、何に、どれだけの時間を使っているか」を洗い出す
- 二重入力や紙帳票などアナログ工程を洗い出す
2. 経営層と現場の対話の場づくり
- IT部門・現場・経営企画が共に「業務改善会議」を開催し、課題を共有する
- ツールありきではなく、「どう変わりたいか」を議論する
3. 部分導入による効果検証
- たとえば、販売管理・在庫管理・原価管理など一部モジュールのERP導入を試行
- 成果や負荷を可視化し、他部門への展開を検討
このように、スモールスタートから全社変革へのステップを構築することが、現実的で効果的なアプローチです。
4)DXを支える人材・パートナーの重要性
システム導入だけではDXは成り立ちません。プロジェクトを推進する「人」の存在と、その人材を育て支援する「外部パートナー」の力が不可欠です。
- ITだけでなく、業務や経営に通じた人材
- 現場と経営をつなぐ「翻訳者」のような人材
- 中堅製造業に理解のあるERPベンダーやSIerの選定
信頼できるパートナー企業と連携することで、業務フロー再設計やトレーニング支援を一体的に実施し、プロジェクトの成功率を高めることができます。
5)「変化を前提にした経営」
かつては「変化に対応する」ことが経営の使命でした。しかし、今後は「変化すること自体を前提に、柔軟で迅速な組織をつくる」ことが求められます。
ERPや自動化設備を整えるだけでなく、それを使いこなし、日々の業務に変化と改善を組み込んでいく文化をつくることこそが、DXの最終ゴールといえるでしょう。
同社の事例は、その実践モデルとして、中堅製造業にとって非常に参考になるものです。
6.中堅製造業の未来を拓く実践的DX
※記事の内容は、制作時点に一般公開されている情報に基づいています。また、記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。