店舗経営等におけるカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラとは?
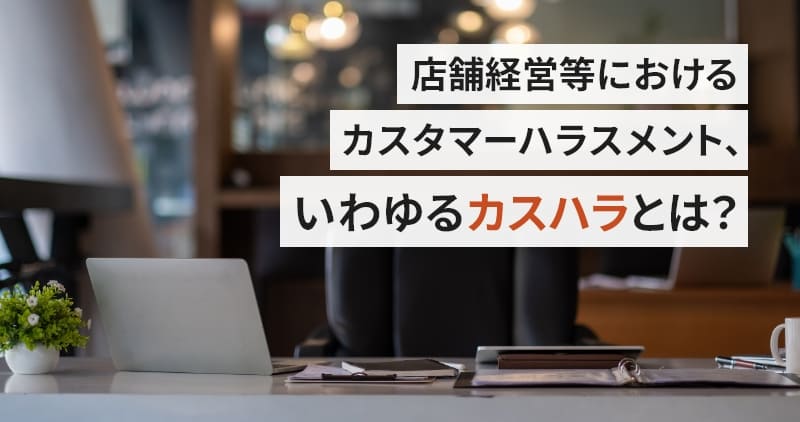
店舗経営等におけるカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラとは?
(ア)定義
厚生労働省の公表しているカスタマーハラスメント対策企業マニュアルによると、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段、態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段、態様により、労働者の就業環境が害されるもの」がカスハラとして定義づけられている。
カスハラが違法性を帯びるかどうかについては、上記の定義に該当するかどうかを判断していくことになるが、言うまでもなく、顧客のクレームの全てがカスハラになるわけではない。クレーム対策が行き過ぎた余り、顧客の正当な要求までもが排斥されてしまうことがないように注意すべきである。
(イ)判断基準
上述のカスハラの定義を分解すると、
① 顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段、態様が社会通念上不相当なもの(手段の必要性と相当性の要件)。
② 労働者の就業環境が害されるもの(結果の重大性)。
③ ①によって②という結果が生じていること(因果関係)
上記のように分解して判断することが可能である。
①については、顧客の主張が正当なクレームなのか、それとも不当な要求なのかを検討することとなる。そして、その検討に際しては、⑴「要求の内容の妥当性」(必要性の要件)、⑵「手段・態様が社会通念上不相当なものである」(相当性の要件)の2つの指標を総合考慮することが求められる。
要求の内容の妥当性を欠く場合に①の要件をみたすことになるのは当然であるが、仮に要求の内容に妥当性があったとしても、それを実現するための手段・態様が不相当であれば、この場合も①の要件をみたすことになる。
そうはいっても、具体例がないとイメージが沸きにくいかと思うので、⑴⑵の具体例についても簡単に触れておく。
(1) 必要性の要件
- 名目の如何を問わず、根拠なく高額な金員を要求する行為
- 商品、サービス等に過失がないことが明らかな事態に対する要求
- 謝罪の強要
- 十分に説明を果たした事項に対するクレーム
(2)相当性の要件
- 脅迫的(暴力的)な言動
- 長時間、連日に及ぶ電話連絡や訪問、居座行為等
続いて、②及び③については、結果の甚大さと因果関係の2点を検討することになるが、 カスハラと評価されうる行為が行われれば、多くの場合、これによって就業環境が悪化することは自明であり、こちらについてはさほど問題にならないケースが多いと思われる。したがって、カスハラ要素を含む顧客に遭遇した場合には、①に係るエビデンスを少しでも多く残しておくことが重要である。
もっとも、例えば顧客が過大な要求を行ってきたがすぐに引き下がったというようなケースでは就業環境が害されたとはいえずにカスハラと評価されない等のケースも考えられる。また、適応障害を発症したスタッフにカスハラ対応以外のストレスが存在していた場合、これもオーナー様の行為と就業環境悪化という結果との間に存在する因果関係が不明慮なためカスハラとはいえなくなる可能性が高まるということもありえる。

公認会計士・税理士
東京都大田区所在RHA法律事務所代表、税理士法人Right Hand Associates 役員税理士。獣医師を志し獣医大学に入学するも、猫アレルギーの悪化で断念。獣医師国家試験受験時に、並行して法科大学院を受験し合格。弁護士登録後は都内弁護士事務所で企業法務を中心とした業務に従事。現在は自身の経営するRHA法律事務所で企業法務・男女問題・相続・刑事事件など幅広く対応している。
