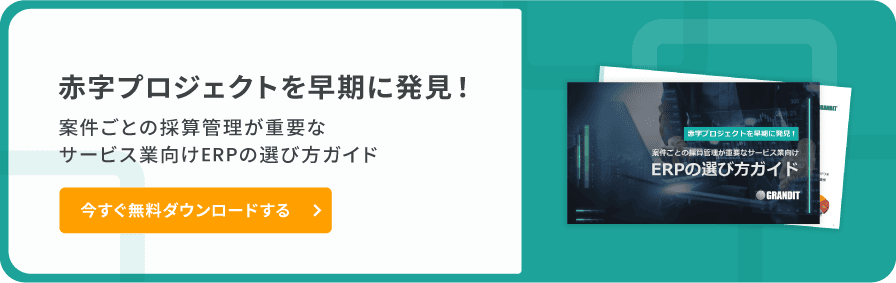“なぜ儲かっているのかわからない”会社は危ない——サービス業に必要な管理会計とは

現在の日本経済は、大きな転換点に差し掛かっています。人口減少と少子高齢化が進み、国内市場が徐々に縮小する中で、企業はこれまで以上に「選択と集中」を迫られています。そうした中で、GDP(国内総生産)の7割以上を占めるサービス産業は、今後の経済成長の鍵を握る存在として、ますます注目を集めています。
とくに中堅規模のサービス業は、日本各地で地域経済や雇用を支える存在でありながら、経営の現場ではまだ多くの企業が「勘と経験」に頼った経営を続けているのが実情です。月次の試算表や財務諸表を確認していても、「この事業はなぜ利益が出ているのか」「どの顧客が高収益を生んでいるのか」「この人員体制で適正なのか」といった問いに対して、明確な答えを持っていないケースは少なくありません。
一方で、サービス業には製造業と大きく異なる特徴があります。たとえば、モノの在庫を持てないという「生産と消費の同時性」や、固定費・間接費の比率が高くコスト構造が複雑であること、そしてその特性から精緻な売上予測や予算管理が必要不可欠であるという点です。こうした構造を無視したままの経営判断は、知らぬ間に収益性の悪化やコストの膨張を引き起こし、企業の持続的な成長を阻害するリスクにつながることがあります。
このような背景から、近年、サービス業においても「管理会計」の導入と定着が重要なテーマとなっています。単なる経理処理ではなく、現場の事業活動に即した経営情報を「見える化」する管理会計の仕組みをいかに構築できるかが、競争力の源泉になりつつあります。そして、その実現の中核を担うのが、ERP(統合基幹業務システム)です。
本記事では、サービス業の中堅企業が直面する会計管理の課題と、それに対する解決策としてのERPの活用法について、具体的な事例や図表を交えながら解説いたします。テーマはズバリ、「なぜ儲かっているのかわからない会社は危ない」。見えないリスクをいかに可視化し、戦略的な意思決定へとつなげていくか——そのヒントを掴んでいただければ幸いです。
1.なぜ「儲かっているのか」が見えないのか?
「毎月黒字だけど、なぜかお金が足りない」「どのサービスが利益を生んでいるか正確にわからない」「人件費が重たいことはわかるが、どこにメスを入れるべきかわからない」——こうした声は、サービス業の経営者や管理者から頻繁に聞かれるものです。
これは、単に経営者の勘が鈍いわけでも、担当者の努力が足りないわけでもありません。問題の根本は、会計情報の見え方である“管理の視点”が不足していることにあります。
1)財務会計の限界と“儲かり方”の不透明さ
多くの企業では、月次の試算表やPL(損益計算書)、BS(貸借対照表)を経理部門が作成し、経営層に提出しています。これらはいわゆる財務会計の成果物であり、対外的な報告や税務処理を目的としたものです。
ところが財務会計は、全社的な利益や資産・負債の状態を集約的に示す一方で、「どのサービス・顧客・部門が利益を出しているのか」といった経営判断に直結する情報の分解・分析には向いていません。
このような状況では、たとえ会社全体が黒字であっても、収益性の低い事業に資源を費やし続けていることに気づけず、機会損失やコスト肥大を招くおそれがあります。
2)管理会計とは「経営の意思決定のための会計」
そこで必要とされるのが、管理会計(マネジメント・アカウンティング)です。これは、経営内部での意思決定や戦略立案を支援するために設計された会計の仕組みであり、現場レベルでの収支を詳細に把握できるようになります。
財務会計と管理会計の違いを整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 財務会計 | 管理会計 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 外部報告(税務、株主、金融機関など) | 経営判断(戦略、予算、現場改善) |
| 対象 | 全社レベル | 部門別、顧客別、プロジェクト別など |
| 会計基準 | 法的に定められたルールに従う | 各社の経営方針に応じて柔軟に設計可能 |
| 作成頻度・タイミング | 四半期・年次(月次) | 必要に応じてリアルタイムも可能 |
| 成果物 | 財務諸表(PL、BS、CFなど) | 損益分析、KPIレポート、シミュレーション等 |
このように、管理会計は経営の“内視鏡”のような役割を果たし、問題が起きる前に兆候を察知し、適切な打ち手を講じるための土台となります。
3)管理会計がない企業は「経営の羅針盤」を持たない航海に近い
管理会計を導入していない、もしくはその仕組みが未成熟な企業は、例えるなら海図も羅針盤も持たずに航海しているようなものです。全社PLの黒字だけを見て「なんとなく順調だ」と判断していても、ある日突然、大型プロジェクトの採算割れや人件費の急増により、赤字に転落するリスクがあります。
特に人材や専門スキルといった「見えにくい資産」を武器とするサービス業では、現場の利益構造を可視化し、早期に打ち手を講じられる仕組みが重要です。
2.サービス業特有の会計構造とは?
日本のサービス業は、今や国内総生産(GDP)の7割以上を占める巨大な産業です。にもかかわらず、製造業に比べると、管理会計や業績評価の仕組みが十分に整備されていない企業が多いのが実情です。その背景には、サービス業特有の「見えにくさ」があります。ここでは、サービス業の経営における管理会計の難しさを3つの観点から整理します。
1)製造業とは異なるコスト構造:間接費・固定費の高さ
製造業では、製品ごとに原価(材料費・加工費・人件費など)を集計しやすいため、「どの製品がどれだけ儲かったのか」が比較的明確に見えます。一方、サービス業では無形の価値提供が主体であり、製造原価のように直接的な費用をサービス単位で把握することが難しいという課題があります。
特に、人件費や設備費といった固定費、間接部門の費用の比率が高いことから、コストの「配賦」が前提となり、その妥当性が常に問われる構造です。
| コストの種類 | 製造業の比率 | サービス業の比率 | 主な項目 |
|---|---|---|---|
| 直接費 | 高め | 低め | 材料費、直接人件費など |
| 間接費 | 中程度 | 高め | 管理部門人件費、通信・設備費 |
| 固定費 | 製品構成による | 高め | 人件費、施設維持費など |
| 変動費 | 比較的高い | 低め | 外注費、交通費など |
この構造により、たとえば同じ売上高でも、コスト構造の違いによって利益率は大きく変動します。つまり、コストの見え方次第で、経営判断の正確性が大きく左右されるのです。
2)サービス業の「同時性」という制約条件
製品とは異なり、サービスは提供された瞬間に消費されるという「生産と消費の同時性」という特徴を持ちます。このことは、会計の観点でも特有の課題をもたらします。
まず、在庫という概念がほぼ存在しません。製造業であれば、売れ残った製品を在庫に計上し、将来販売できる可能性を残すことができます。しかしサービス業では、売れ残った時間や人手は回収不可能であり、時間=コストの無駄になります。
そのため、サービス業においては「売上予算」の精度が非常に重要です。とくに、稼働率や稼働時間がそのまま収益に直結する業種(例:コンサル、派遣、教育、医療など)では、販売見込みの甘さがそのまま損失に直結します。
| 特性 | 影響 |
|---|---|
| サービスの時間的制約 | 人員の空き時間が損失となる |
| 顧客対応が個別最適化されやすい | 標準的な原価管理が困難になりやすい |
| 在庫が持てない | 売上の見込み管理が重要/損失の先送りができない |
| クレーム・再対応の発生 | 追加コストの発生源になり、収益性を圧迫する |
このように、サービス業では「何がどれだけ売れたか」だけでなく、「いつ・誰が・どれだけの時間で・どんなコストで提供したか」を管理する必要があり、会計の粒度とタイミングが非常に重要になります。
3)予算管理の難しさと“精度”の重み
さらに、サービス業では売上や利益の変動が季節や外部要因に左右されやすく、予算の立案・管理の難易度が高いという点も見逃せません。
特に、以下のような課題が頻出します。
- 顧客からの受注タイミングの変動により、売上の前倒し/後ろ倒しが発生
- 突発的なリソース不足や残業による人件費の想定超過
- 売上原価に含まれる要素が多岐にわたり、分析が困難
このような複雑な環境下で、計画と実績を比較・分析できる仕組みがなければ、PDCAサイクルが形骸化しやすい傾向にあります。
4)管理会計は「見えないコスト」と「失われる収益」をあぶり出す
結局のところ、サービス業の本質的な収益性を左右するのは、「何に、どれだけのコストをかけて、どれだけの利益を得たか」を見抜けるかどうかにかかっています。それを定量的に把握し、適切に管理するための手段が管理会計です。
3.管理会計の導入がもたらす経営の変化
これまで述べてきたとおり、サービス業の経営環境は複雑性が高く、かつコスト構造も不透明であるため、「見える化」による情報武装が欠かせません。ここで鍵を握るのが、管理会計の導入によって得られる“経営の可視化”です。
ここでは、管理会計を導入したことで企業が得られる実際の変化について、3つの側面から解説いたします。
1)収支構造の「分解」がもたらす意思決定の質の向上
管理会計では、部門別・サービス別・顧客別・プロジェクト別など、複数の視点で収益とコストを分解・集計することが可能になります。これにより、「全体としては利益が出ているが、実は一部の事業や顧客が赤字を招いている」というような状況を可視化できます。
これにより、以下のような判断が可能になります。
- 利益率の高いサービスに人員を集中配置する
- 赤字部門を縮小・撤退し、固定費を圧縮する
- 高収益な顧客との関係を強化し、契約単価やLTV(顧客生涯価値)を最大化する
このように、収支構造を「点」ではなく「面」で把握することが、戦略的な意思決定の精度を格段に高めます。
2)KPIの定量化とPDCAサイクルの高速化
管理会計の導入は、経営指標(KPI)を具体的に定義・追跡する基盤にもなります。たとえば以下のようなKPIが設定・管理しやすくなります。
- 稼働率(サービス提供者の実働時間 ÷ 総勤務時間)
- 人時売上高(売上 ÷ 稼働時間)
- プロジェクト別利益率
- 顧客別限界利益
これらのKPIを部門やチーム単位でモニタリングできるようになると、「計画と実績の差異」に早期に気づき、修正アクションを打つことが可能になります。これにより、PDCAサイクルのスピードと精度が向上します。
従来のように、月次の財務レポートを見てから次の手を打つ、という“後追い型”の経営から、先読み型・即応型の経営へとシフトできます。
3)収益性の高いサービス・顧客の特定と集中戦略
管理会計により、「どのサービスがどれだけ利益を生んでいるか」「どの顧客との取引が企業の利益構造に寄与するか」が明確になると、リソースの最適配分が可能になります。
たとえば、以下のような施策が実現できます。
- 高収益サービスの価格維持・向上策と差別化戦略
- 利益貢献の小さい顧客の見直しと契約条件の再交渉
- 収益性の低いサービスラインの縮小・統合による固定費削減
結果として、売上至上主義から利益重視の経営へと転換する土壌が整います。これは、とくに売上の変動が大きく、リソースに限りのある中堅企業にとって、持続可能な成長戦略を描く上で極めて重要です。
4)「可視化」が企業文化を変える
管理会計の本質は、単なる数値管理ではありません。現場の行動と経営の意思決定をつなぐ“共通言語”をつくることにあります。数値に基づくコミュニケーションが定着すると、責任ある行動と説明責任の文化が社内に生まれ、結果的に組織の成熟度も高まります。
4.ERPで実現するサービス業の管理会計
ここまで述べてきたように、サービス業の経営において管理会計の仕組みを整備することは、事業の収益性を高め、持続可能な成長を実現するうえで不可欠です。しかし、現実には多くの中堅企業が、手作業中心のエクセル管理や部門ごとのばらばらな集計体制に苦しんでいます。
そのボトルネックを解消し、管理会計を“日常業務に根付かせる”ための基盤として期待されるのが、ERP(統合基幹業務システム)です。
1)「経理」から「経営」への視点転換を支えるERP
ERPは、単なる仕訳入力や財務諸表作成のためのツールではありません。販売・購買・人事・プロジェクト管理など、他の部門データとシームレスに連携することで、日々の業務から発生するデータを即時に財務・管理情報として変換できるのが最大の強みです。
たとえば、以下のような情報をリアルタイムで把握できます。
- プロジェクト別の進捗とコスト構成
- 部門別の売上・利益・予算実績差異
- サービス別の限界利益率や人件費率
- 顧客別の取引採算性(値引率、利益率など)
このようなデータが自動集計され、エクセルのように属人的に集計・加工する手間を大幅に削減できます。
| 項目 | ERP導入前(従来型) | ERP導入後(統合型) |
|---|---|---|
| データ収集 | 部門ごとにばらばら/手作業 | 各部門システムから自動連携 |
| 集計作業 | エクセルベースで時間と手間がかかる | リアルタイムで集計・可視化が可能 |
| 分析の視点 | 全社/月次中心で粗い粒度 | サービス別/部門別/案件別など詳細に分析可能 |
| 報告・共有 | 担当者の負担が大きく遅れがち | ダッシュボードや自動レポートで即時共有可能 |
2)予算管理と実績分析のリアルタイム化
ERPによって、予算と実績の対比がリアルタイムでモニタリング可能になります。これにより、「売上は達成しているが、コストが予算を超過している」といった異常値に即座に対応できます。
特にサービス業では、稼働率やプロジェクトごとの利益率が日々変動するため、月次ベースの管理では変化に追いつきません。ERPを用いれば、たとえば以下のような指標をリアルタイムに確認できます。
- 人時単価別の収益性比較
- 顧客別・商材別の予算達成率
- 拠点別損益とコスト構成の異常検知
こうした情報は、現場のマネージャーや経営企画部門がタイムリーに意思決定を行う上で非常に重要です。
3)業務プロセスの標準化と属人化の排除
多くの中堅企業では、管理会計が担当者の経験やスキルに依存しており、異動や退職によって業務が属人化しやすい傾向にあります。ERPの導入によって、会計処理やデータ集計のプロセスがシステム上に明確に定義され、誰でも同じ手順で操作・分析が可能になります。
また、ワークフローの統一や入力項目の整備によって、「入力のばらつき」や「データの取りこぼし」も防止されます。結果として、管理会計のデータ精度が飛躍的に向上し、“信頼できる数字”にもとづいた経営が可能になるのです。
4)将来シミュレーションと経営判断の高度化
さらに、ERPでは予算の策定とそのシミュレーションも可能になります。たとえば、「稼働率が80%を切った場合、利益率はどう変化するか」「人員を2名増やした場合、プロジェクト別損益はどう変わるか」といった仮説とシナリオにもとづいた経営判断をサポートできます。
これは、変化の激しい事業環境において、“勘”や“過去の実績”だけに頼らない、将来志向の意思決定を可能にする重要な基盤です。
ERPは、もはや「経理部門の道具」にとどまりません。経営判断の精度を上げ、組織全体の行動を数値で導く“羅針盤”として、サービス業の管理会計の中核を担う存在となるのです。
5.導入事例に学ぶ:管理会計が企業を変える
管理会計は理論ではありません。現場で使われ、数字として活かされて初めて、その真価を発揮します。ここでは、実際にERPを活用して管理会計を導入し、組織運営や経営判断に変化をもたらした企業の事例を紹介いたします。
1)ビルメンテナンス業──現場における精密な予実管理を実現
株式会社ボイスは、ビル清掃をメインとした総合ビルメンテナンス業を行っています。ビルメンテナンス業務の原価は、人件費、外注費(外部サービスに委託している特殊清掃)、資材費などで構成されており、清掃の請負契約が決まったら、これらの予算を策定し、日々の現場で予算をオーバーしないようにコントロールしながら「精密に」経費の予実管理を行っていく必要があります。しかし、ERPを中核とした新システムによって「データの一元化」、「予実管理を月次管理から週次管理へ転換」、「経営分析に必要なデータの収集」と「精密な予実管理」を実現することに成功しました。
| 企業名 | 株式会社ボイス様 |
| 事業内容 |
清掃管理業務 設備管理業務 保安・警備業務 サービス管理業務 コンサルティング業務 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 従業員数 | 2,600名(パート含む) |
| 事例URL | https://www.grandit.jp/showcase/detail/bois.html |
2)データが組織を動かす──事例のポイント
本事例のポイントは、ERPによって可視化された管理会計のデータが、組織の意思決定と行動を変えたという点です。
- 「肌感覚」から「証拠にもとづく判断」へ
- 「後追い」から「予防的な経営」へ
- 「売上志向」から「利益志向」へ
これらの変化は、特別な財務スキルがなくても、現場・経営陣が同じ数字を見て共通認識を持つ仕組みさえあれば、どの企業でも実現可能なのです。
6.「儲かっている理由」がわかる企業は、強い
本記事では、サービス業における管理会計の重要性と、ERPを活用した“見える化”の可能性について解説いたしました。GDPの7割以上を占めるサービス産業が、これからの日本経済を牽引していくうえで、その中核を担う中堅企業が、持続的な収益構造を築くことは非常に重要な課題です。
しかし、そのためにはまず、「なぜ儲かっているのか」「どこで利益が失われているのか」を明確に知ることが出発点となります。
これは、製品や在庫、設備のように目に見えるものを扱う製造業と異なり、無形の価値や時間、人の動きが利益に直結するサービス業にとっては、より高度な経営管理の視点が求められることでもあります。
その“視点”を現場レベルに落とし込み、日常の意思決定に活かすためには、管理会計とERPという武器が不可欠です。ERPを中核に据えることで、以下のような企業変革が可能になります。
- 勘と経験に頼らない、データドリブンな経営判断
- 拠点別・顧客別・プロジェクト別など多面的な収益性の把握
- リアルタイムな予実管理と即応的なマネジメント
- 組織全体での共通指標による行動変容と意識改革
これらの変化は、単なるコスト削減にとどまりません。社員一人ひとりが“利益を意識した行動”を取れるようになり、結果として企業文化そのものが変わっていくのです。
最後に、サービス業の経営に携わる皆さまにお伝えしたいのは、「儲かっている理由がわかる企業は、外部環境が変化しても、柔軟に対応できる」ということです。
未来が不透明であるほど、今こそ自社の内側にある“見えない構造”を可視化し、変化に強い体質をつくるべき時ではないでしょうか。
以下のホワイトペーパーでは、サービス業におけるERP選定の際に注目すべきポイントを解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
※記事の内容は、制作時点に一般公開されている情報に基づいています。また、記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。