残業時間の削減に効果がある変形労働時間制|社会保険労務士 川島 孝一
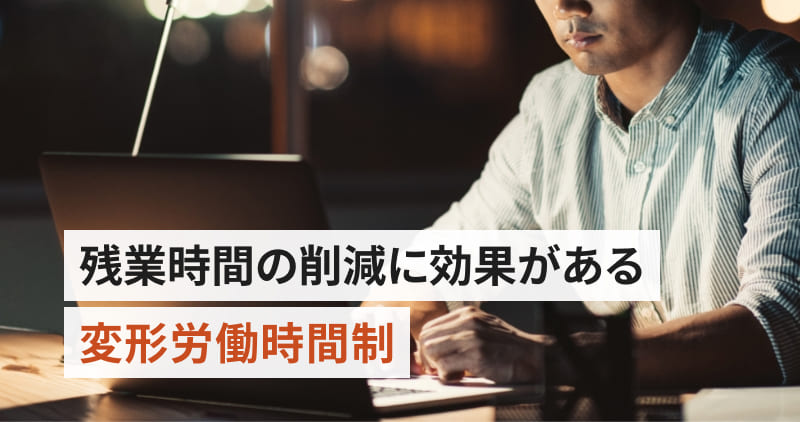
前回、2023年4月より1か月60時間を超える法定時間外労働に対して、中小企業でも50%以上の率で計算した割増賃金の支払いが開始されることの説明をしました。
それを踏まえ、今回は、業務スケジュールにフィットさせることができれば、残業時間を減らす効果がある「変形労働時間制」について解説していきます。
労働時間の原則
労働基準法では1日(8時間)、1週(40時間)の労働時間、休日日数(毎週少なくとも1回)を定めています。原則は、この時間数や日数を超えて従業員を労働させてはならないというルールになります。
しかし、現実的に繁忙期等で労働時間が伸びてしまうこともあるので、36協定を締結して労働基準監督署長に届け出れば、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日における休日労働が認められます。
変形労働時間制は、一定の要件に該当すれば、1日8時間、週40時間を超えて労働したとしても時間外労働にならないという効果があります。
一般的に導入されていることが多い変形労働時間制は、「1か月単位の変形労働時間制」と「1年単位の変形労働時間制」です。それぞれの特徴についてみていきたいと思います。
1か月単位の変形労働時間制とは?
1か月単位の変形労働時間制は、労働基準法第32条の2で「1か月以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、当該変形労働時間においては、1日及び1週間の法定労働時間にかかわらず、これを超えて労働させることができる」と定められています。
これでは少し分かりにくいので、平たく言ってしまうと、「1か月(以内)を平均して1週間の労働時間が週40時間以下になっていれば、 忙しい時期の所定労働時間が1日8時間、週40時間を超えていても、時間外労働の扱いをしなくて済む」という制度です。
導入するメリットのある会社は、以下のようなケースに該当する場合です。
- 月初や月末に業務が集中している
- 週の始めや週末に業務が集中する
- 特定の日だけ営業時間が長い
- ある週は4日勤務で十分だが、ある週は6日勤務する方が効率が良い
1か月変形の所定労働時間
変形期間の労働時間は、平均して法定労働時間を超えないこととされています。そのため、変形期間の所定労働時間の合計は、次の式によって計算された範囲内とすることが必要になります。
1週間の法定労働時間 × 変形期間の暦日数 ÷ 7日
この計算をすると、以下のような労働時間が総枠をとして算出することができます。労働時間の総枠の( )内の時間は、特例措置対象事業場の総枠になります。特例措置対象事業場とは、常時10人未満の従業員を使用する商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業場です。
| 1か月の暦数 | 労働時間の総枠 |
|---|---|
| 28日 | 160.0時間(176.0時間) |
| 29日 | 165.7時間(182.2時間) |
| 30日 | 171.4時間(188.5時間) |
| 31日 | 177.1時間(194.8時間) |
この総枠の範囲であれば、ある日は10時間、他の日は6時間といった勤務体系とすることが可能です。
1年単位の変形労働時間制とは?
1年単位の変形労働時間制は、労働基準法第32条の4で「労使協定を締結し、対象期間として定められた期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、特定された日又は特定された週に法定労働時間を超えて労働させることができる」と定められています。
こちらは、1か月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件として、業務の繁閑に応じて労働時間を分配することを認めるということです。たとえば、年末年始に繁忙期があり夏場は閑散期といったような業種の会社は導入するとメリットがあると言えます。
1年変形の所定労働時間
対象期間の労働時間を平均して1週間の労働時間は40時間を超えないことが条件なので、特例措置対象事業場であっても同じ時間数です。そのため、対象期間の所定労働時間の総枠は、次の式によって計算された範囲内とすることが必要になります。
40時間 × 変形期間の暦日数 ÷ 7日
この計算式で、いくつかの対象期間のパターンにおける労働時間の総枠を算出してみました。
| 対象期間 | 法定労働時間の総枠 |
|---|---|
| 1年(365日) | 2,085.7時間 |
| 6か月(183日) | 1,045.7時間 |
| 4か月(122日) | 697.1時間 |
| 3か月( 92日) | 525.7時間 |
「1年単位」の変形労働時間制と聞くと、対象期間が1年間に限定されていると勘違いをされているケースもありますが、対象期間は「1か月を超えて1年以内」と定められているので、3か月でも半年でも導入することができます。
1年単位の変形労働時間制は、労働時間や労働日数の制限が設けられています。基本となる制限事項は、労働時間は、1日10時間、週52時間まで、連続して労働することができる日数は6日(特定期間は実質12日)までです。また、3ヶ月を超える変形期間の場合の労働日数は年間280日までになっています。
1か月単位の変形労働時間制と違い、かならず労使協定を締結し、その協定書を労働基準監督署に届け出る必要があります。導入する場合は注意してください。
割増賃金の計算方法
通常の考え方であれば、1日8時間を超えた場合と週40時間を超えた場合には割増賃金の支払いをすることなります。しかし、変形労働時間制の場合は、少し計算の方法が変わってきます。
ケース別に見ていきたいと思います。
- ケース① 1日の労働時間を8時間よりも長く設定した日
設定した時間を超えた場合に2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。
たとえば、1日の労働時間の設定が8時間45分の日に9時間30分働いたとすると、45分だけが割増賃金の支払い対象になります。 - ケース② 1日の労働時間を8時間よりも短く設定した日
法定労働時間を超えた時間から割増賃金を支払う必要があります。
1日の労働時間を5時間と設定したのであれば、5時間を超えたすべての時間について割増賃金を支払うのではなく、法定労働時間である8時間を超えた時間から割増賃金の支払いの対象となります。
なお、5時間から8時間までの3時間は、割増はしなくて構いませんが、時間外労働であることには変わりはありません。 - ケース③ 1週の労働時間に対する割増賃金
40時間以上の労働時間を当初から設定していた週は、その設定をした週の労働時間を超えた時間から割増賃金の支払い対象となります。
40時間未満の労働時間を設定していた週は、40時間までは割増なしの時間外労働、40時間を超えた時間は割増賃金の支払いが必要になります。 - ケース④ 変形期間の総労働時間に対する割増賃金
すでに割増賃金の対象とした時間を除き、変形期間の総労働時間が、先ほどの法定労働時間の総枠を超えた場合は、超えた時間についてはすべて割増賃金を支払う必要があります。
このように、状況に応じて割増賃金の計算を行っていく手間はかかりますが、業務の繁閑に応じて労働時間を設定することができるので、業態によっては、残業時間を削減する効果があります。
残業時間を削減しようと考えている会社は、一度検討をしてみてもよいでしょう。
- 第1回:コロナ禍での在宅勤務における労働時間の考え方
- 第2回:コロナ禍での在宅勤務における労災保険の適用
- 第3回:コロナ禍での在宅勤務における通勤災害の考え方
- 第4回:傷病手当金の支給対象期間の変更
- 第5回:60時間超の残業の割増率と代替休暇

川島経営労務管理事務所所長、(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサルタント、社会保険労務士。
早稲田大学理工学部卒業後、サービス業にて人事・管理業務に従事後、現職。人事制度、賃金制度、退職金制度をはじめとする人事・労務の総合コンサルティングを主に行い、労務リスクの低減や経営者の視点に立ったわかりやすく、論理的な手法に定評がある。
著書に「中小企業の退職金の見直し・設計・運用の実務」(セルバ出版)、「労働基準法・労働契約法の実務ハンドブック」(セルバ出版)、「労務トラブル防止法の実務」(セルバ出版)、「給与計算の事務がしっかりできる本」(かんき出版)など。
